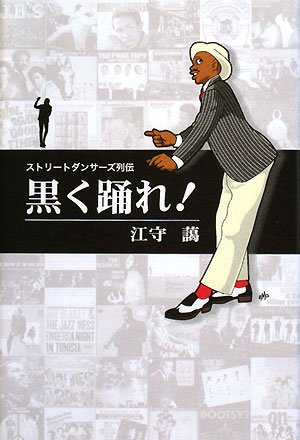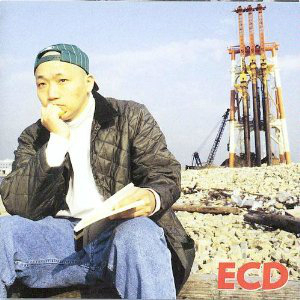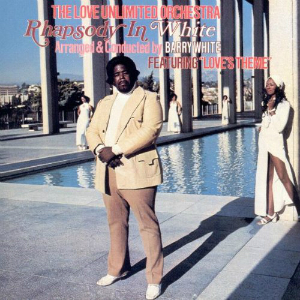『Major Force be with you -30th anniversary- 』レポート
<Major Force>は音楽的に何をしてきたのか? 荏開津広が“嵐の夜”のアニバーサリーを振り返る


ならば、もう一つの軸が藤原ヒロシというプロデューサー/アーティスト/デザイナーであることも、あらためて今回はっきりした。ブラックのボンデージパンツを履いてギターを持ち、自ら「IT'S a NEW DAY」を歌った藤原ヒロシは、言うまでもなく、世界というか、ゲームの規則自体を変えてきた人物だ。パリ中心のシーズン毎のゲームに追いつこうとするのではなく、マルコム・マクラーレンの創造した物語のもうひとつ別の道筋を発見することによって、ファッションからスタイルへと大きな価値転換を行うーー故・川勝正幸が藤原ヒロシについて書いた回想録に『丘の上のパンク』を名付けたように、彼自身もまたそのソフィスティケートされた偶像破壊の手を一回も緩めたことはない。その姿勢は、この日始めてパフォーマンスされたという、彼が手がけたSDPの「N.I.C.E.Guy(Nice Guitar DUB)」のサウンドにだって明らかに響いていた。1991年当時、スムースなギターをヒップホップに導入すること自体も、実に批評的な作業だったと聞きながら思い出す。30年経って、最早そうした感受性のありようを“ストリート”という言葉でも括れないほどに、世界はもう変わったのだ。会場に集まった30代や40代、いわゆるジェネレーションX世代中心のオーディエンスの様子を眺めて思う。

その”N.I.C.E. Guy”のSDPは、この夜(嵐によりすべてのJR列車が20時で運行を止めたあの夜)のために集まった熱意あるオーディエンスとステージ間の通訳を兼ねていて、盛り上げるだけ盛り上げたあと、MCでまた煽ったのだった。高木完と藤原ヒロシの2人がステージに並ぶ姿を「今なら撮影可」だと宣言し、タイニー・パンクスの2人を笑顔にさせて、オーディエンスみんなの胸を(密かに)熱くして、マスターオブセレモニーの面目躍如といったところで去っていった。
濃厚なニューエイジのためのチルアウト・バラッドユニットであるSexy T.K.O.の名曲を、EGO-WRAPPIN'の2人はライブアクトとして熱く果敢なパフォーマンスで披露する。そして、立花ハジメと島武実、そして中西俊夫の娘の花梨がステージに上がって、Plasticsのヒット曲「Top Secret Man」のカバーをやってのけたあたりで『Major Force be with you -30th anniversary- 』は大団円を迎えた。

シンプルなドレスをまとった花梨が、明らかにアマチュアであっても観客たちを魅了することができたのは、<Major Force>のダンスミュージックに則った、パーティという場から音楽を考えていく(ダンス、受け手とのインターアクションの重視、視覚的要素、ハレの場自体の力など……)ことと繋がっていた。
また「Top Secret Man」のロックンロールな楽曲が、ユーモアたっぷりにシンセサイザーのよるレゲエに翻訳され直したのも、<Major Force>が設立された1980年代後半という時代、ロックに替わってダンスミュージックがどんな役割を果たし始めたのかを考えずにはいられなかった。<Major Force>のこのような相貌は、リアルタイムでは理解するのが難しかっただろう。
ライブの最後に高木完が約束してくれたように、<Major Force>の活動はこれからまた盛んになるようだ。
『Major Force be with you -30th anniversary- 』が懐古的でなかったのはなぜか?
ハウスやテクノをベースにしたサウンドが当たり前に日本の日常になっただけでなく、サイケデリックでカラフルなヒップホップ集団・OFWGKTA以後の、リル・パンプやスモークパープといったラッパーによる、ラップ/パンクの夜が明けた時代を、やはり<Major Force>が相応しくも30年ほど先取りしていたからなのでは? と思いながら、僕は急いで原宿Laforetの階段を降りたのだった。
■荏開津広
執筆/DJ/京都精華大学、立教大学非常勤講師。ポンピドゥー・センター発の映像祭オールピスト京都プログラム・ディレクター。90年代初頭より東京の黎明期のクラブ、P.PICASSO、ZOO、MIX、YELLOW、INKSTICKなどでレジデントDJを、以後主にストリート・カルチャーの領域において国内外で活動。共訳書に『サウンド・アート』(フィルムアート社、2010年)。