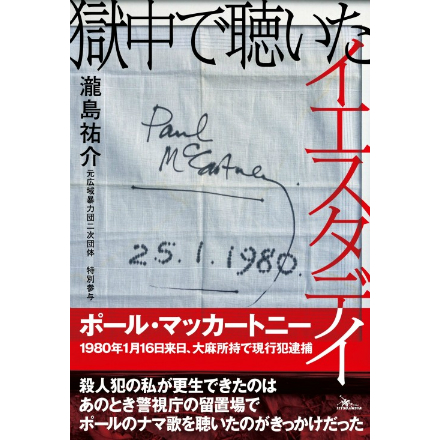s-ken×甲本ヒロトが語る“70年代の熱狂”「火をつけて、燃えるところを見るまでやめられない」


「せめて自分が歩く道だけでも、向こうで目撃したときの気分を持っていたい」(s-ken)
ーー今回のアルバム『Tequila the Ripper』を作ることになったのは、何かきっかけがあったんですか?
s-ken:もともとはs-ken&hotbombomsのアルバムが4枚同時に再発になったことですね。そのときにボーナストラックとして新曲を作ったら、ディレクターに「いまこそ、みんなにs-kenさんの音楽を聴いてもらいたいんです」と言われて。
ーー『Tequila the Ripper』にはhotbombomsのメンバーをはじめ、竹中直人さん、トータス松本さん、東京スカパラダイスオーケストラのメンバーなど、s-kenさんに縁のあるミュージシャンが数多く参加されていて。s-kenさんのキャリアと人柄が感じられる作品ですよね。
s-ken:今回、細野晴臣さんも参加してくれてるんですよ(「酔っぱらいたちが歌い出し、狼どもが口笛を吹く」、 「嵐のなか船は出る」でベースを演奏)。細野さんとは同い年なんです。
甲本:細野さんの初期の作品にも参加されてますよね?
s-ken:そうですね。初めて細野さんと会ったのは26歳くらいのときだけど、あの頃は、みんなが“自分とは違うもの”になりたがってたんですよ。白人は黒人になりたがり、黒人は宇宙人になりたがって。Pファンクの連中もそうじゃないですか。
甲本:宇宙船に乗って登場したりね(笑)。
s-ken:そうそう。僕は自分の周辺に横浜のチャイナタウンぐらいしかないエキゾチックなものに惹かれていたんですけど、そのなかにマーティン・デニーというミュージシャンもいて。それらの音源を細野さんにまとめて貸したら、彼もすごく興味を持って。それが『トロピカル・ダンディー』のエキゾチックサウンドの参考になったということなんです。
甲本:それがYMOになっていくんですよね。なるほど、そこにもs-kenがいたんだ。
s-ken:いろんな音楽が好きだし、根本的にはストリート感ある音楽や文化全部が好きなんですよ、CBGBから出て来たパンクもそうだし、サウス・ブロンクスから生まれたヒップホップもそうですよね。1970年代後半のサウス・ブロンクスは、2年間で放火が3万件もあったんです。家賃が下がって採算が取れないからビルのオーナーが火を付けちゃうんだけど、ヒップホップはそういう場所から始まって、3〜4年で世界中に広がってった。まさにその創成期にニューヨークに住んでいたのは大きいよね。
甲本:そうか。ロックンロールが大好きで、ずっと日本でやってたから、ヒップホップのムーブメントがいまいちピンと来てなかったんです。
s-ken:ただね、最初は血沸き肉躍る感じなんですけど、しばらくするとファッションになるというか、様式化しちゃうでしょ? それはおもしろくないし、せめて自分が歩く道だけでも、向こうで目撃したときの気分を持っていたいと思っていたんですよね。
ーーストリートから自然発生的に生まれた音楽は、ヒロトさんも意識していますか?
甲本:具体的に何かを意識しているわけではないけど、そういうものに影響されているとは思います。東京ロッカーズ、パンクロックもそうだし、いままで聴いてきた黒人音楽もそうだけど、ショービジネス然としたものではなく、つまりはオルタナティブですよね。エンターテインメントの世界があったとして、それとは違う、もう一つの何かがずっと好きだったんじゃないかな。自分でやるときにそれを意識しているかと言えば、また別なんだけど。
s-ken:なるほど。やっぱり、僕がアメリカにいた1970年代後半が一つの境目だったと思いますね。ロンドンからはSex Pistols、The Jam、エルヴィス・コステロ、Dr.Feelgoodなどが一斉に出てきて、ニューヨークからシカゴに渡ったDJがハウスミュージックを興して。その4〜5年にいろいろなものがニューウエーブってことで世界に広がっていった。あの頃の気分を知っている人と知らない人では、何かが違うんですよ。Sex Pistolsなんて、いま聴いてもすごいから。
甲本:吹っ切れてるんですよね、何もかも。
s-ken:クリス・トーマスがプロデュースしているだけあって、よく出来てるんだよね。
甲本:聴くといつも興奮するから、冷静に聴くのは難しいんだけど、『勝手にしやがれ!!』はすごく真っ当な録音なんです。奇を衒ったこと、エキセントリックなことは何もしてなくて、スタンダードな方法で録音、ミックスされていて。Led Zeppelinのレコードと同じくらいのクオリティなんですよね。
s-ken:そこにも理由はあるんだろうね。自分が少年の頃に遡ると、ドノヴァンというシンガーソングライターがいて。『サンシャイン・スーパーマン』(1966年)あたりのアルバムは素晴らしいんだけど、そこにはミッキー・モストというプロデューサーがいたんです。彼が離れたとたん、ドノヴァンのレコードはおもしろくなくなるんですよ。
甲本:なるほど。プロデューサーって大事なんだね。
s-ken:ヒロトはそれを自分でやってるんじゃない? たとえば「セックス・ピストルズのレコードを超えるためにはどうしたらいいか?」と考えることは、もはやプロデュースだし。
甲本:そうか。レコードのことで言えば、<CBS SONY>が出していたロバート・ジョンソンのコロムビア盤の録音がすごいんですよ。僕が初めて聴いたのは20歳くらいだったけど「これを超えるレコード盤は存在しない」と思ったんです。ギター1本と歌だけの録音なんだけど、何も足りないものはないし、とにかく最高で。そのレコードとSex Pistolsの『勝手にしやがれ!!』は肩を並べるんだけど、そのことを理解する人としない人がいるんですよね。
s-ken:確かに「いい音だな」と思うレコードってあるよね。50年代のモダンジャズ、たとえばエルヴィン・ジョーンズなんかを聴いていると、ドラムの音が本当に素晴らしいってことがある。マイク2本で録ってるはずなんだけど、めちゃくちゃいい音なんだよ。
甲本:ルディ・ヴァン・ゲルダー(マイルス・デイヴィス、ジョン・コルトレーンなど、数多くのジャズミュージシャンの作品の録音を手がけた伝説的レコーディング・エンジニア)の録音も素晴らしいですからね。ロバート・ジョンソンの録音のことで言うと、ヒントが一つあって。彼がホテルの部屋で録音している絵が残ってるんだけど、それを見ると、壁の角に向かって歌ってるんですよ。たぶん反響とかを考えて、どこで歌ったらいいか探したんでしょうね。その絵を見たときに「出来ることは全部やってたんだな」と思ったし、すごくヒントになりました。やることやってんですよ、やっぱり。
s-ken:うん、もちろんそうだよね。僕の体験で言うと、アシッドジャズの頃にエスカレーターズというバンドをプロデュースしたことがあって、ロンドンでレコーディングしたんです。せっかくだからって向こうのクラブでライブをやったんだけど、 PAシステムがひどかったんですよ。モニターも貧弱で、ライブもぜんぜん良くなくて。でも、その後、同じ貧弱なPAシステムでクラブの常連の黒人のミュージシャンが集まってきて演奏すると、とてつもなく良い音で、最高のアンサンブルだったわけ。彼らはモニターやPAを頼りにしないで、自分たちの耳でしっかりバランスを取れるんだよね。きっとロバート・ジョンソンも、そういう音のバランスに敏感だったんじゃないかな。
甲本:うん。
s-ken:向こうの一流のエンジニアもそうで、テクニックがあるじゃない。サウンドの歴史を全部知ってるし、わかってるわけ。「The Ronettesの『Be My Baby』の最初のスネアの音」と言えば、ニヤッとするんですよ。で、「この音だろ?」とすぐ作ることができる。一流のエンジニアにとって、フィル・スペクターのウォール・オブ・サウンドは基本中の基本で、それがわかってないとダメなんです。
甲本:そりゃそうですよね。そういえば、フィル・スペクターって、全部モノラルなんですよね。録音してるときもミックスしているときも、使ってるスピーカーは一個だけ。あれがカッコいいんだよな。ちなみに、s-kenさんが最初に興味を持ったことは何だったんですか? 小説とか音楽とか、いろいろあると思うんだけど。
s-ken:いちばん初めはThe Rolling StonesとThe Beatlesですね。あと、フィル・スペクターの師匠みたいな存在のジェリー・リーバー&マイク・ストーラーというソングライター・チームがいて。彼らが黒人のミュージシャンを使った楽曲が好きだったんですけど、ちょっとラテンが入ってるんですよね。
甲本:あ、わかります。ボ・ディドリーなんかも、マンボが入ってますからね。チャック・ベリーも、ところどころにラテンを入れてくるし。
s-ken:The Coasters、The Driftersもそうだけど、ああいうロッカ・ルンバに惹かれたんですよ。The Rolling Stonesも初期にThe Driftersの「Under the boardwalk」をカバーしてるよね。
甲本:なるほど。いまの話でs-kenという人が少しわかってきました。
s-ken:今度のアルバムでもロッカ・ルンバ的な曲もあるからね。
甲本:昔からそうでしたよね。「おお揺れ!東京」とか。
s-ken:(笑)いろいろヘンなことやってたからね。
甲本:その感じは僕もわかります。真っ白でも真っ黒でもなくて、ちょっと肌に色が付いているヤツらがやってることって、見逃しがちなんですよ。あいつらが勝手にやってることって、すごくおもしろいんですよね。