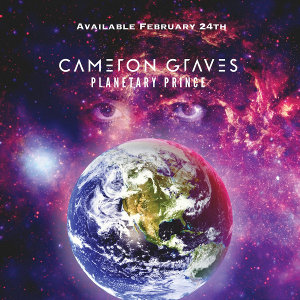『Jazz The New Chapter4』刊行記念対談(後編)
音楽における「教会と教育」の重要性とは? 新世代ジャズ奏者の台頭から考える
「クリエイティヴな発想からすると、教育は『つまらんもんだ』という考えになりがち」(矢野)
ーーこの章を締めくくる唐木さんの論考も興味深かったです。実際に教育を受けている最中の人が、その可能性について言及するという。
柳樂:彼はいま、ウォーリーズというBIGYUKIやマーク・ケリーがいたライブハウスで時折演奏してるようなんですが、ベーシストの席は少ないみたいで。この原稿を書いた直後にめちゃくちゃ上手いシンセベース奏者が入って来て、「これからはシンセベースの時代なんじゃないかって書いたら、本当に俺の席をシンセベースに取られそうだ」と言ってました。やっぱり持ってる人だなあと(笑)。
ーー最後の章では【ベッカ・スティーヴンスと<グラウンドアップ>】として、ベッカの新作『Regina』と、同作をリリースしたSnarky Puppyのマイケル・リーグが立ち上げたレーベル<GroundUP>にフォーカスを当てています。この章を最後に持ってきたのは、もしかすると【21世紀を生きる新生<ブルー・ノート>の軌跡】と重ね合わせているというか、<GroundUP>に未来の<Blue Note>を見ているのかなと思ったのですが。
柳樂:いや、構成上置き所に迷って最後にしただけですよ(笑)。でも、この本にも数多く出てくるエピソードが示すように、『Jazz The New Chapter』は“ミュージシャンの時代が来た”という本なんですよ。だからミュージシャンが自分たちで音楽を作っていったり、プロモーションしたり、人の繋がりで人を集めたり、その系譜上に学校や教会があると。その流れを一番体現しているのは、おそらくSnarky Puppyと<GroundUP>で。彼らの「グレートミュージックだったらなんでもいいけど、グレートミュージックじゃないとダメなんだ」という哲学にも共通する。
矢野:その話はまさに、ドン・ウォズ(<Blue Note>)の話を思い出します。
柳樂:確かに、そういう意味では通ずるものはあるのかな。Snarky Puppyって、いまは30人くらいの集団なんですけど、彼らの仲間になる基準は一つで「上手いやつしか入れない」ということ。だから、彼らが起用するデヴィット・クロスビーもベッカ・スティーブンズもジェイコブ・コリアーも超スキルフルなボーカリストなんですよ。いまはよくCDや配信の売り上げがどうとかで「ライブの時代になった」と言って、演出にどれだけこだわるかという話になりがちじゃないですか。もちろんアメリカでもそういうポップ・スターは多いけど、Snarky Puppyはいかにライブの時代を音楽の力で勝ち抜くか、という気概があるんですよね。
ーーこれまで『Jazz The New Chapter』では、スキルフルな集団というだけではない、コミュニティとしてのSnarky Puppyのすごさについて取り上げてきましたよね。
柳樂:そうですね。ちなみに彼らはノーステキサスの音楽大学が最初の舞台だったり、そこからゴスペル系のミュージシャンがいっぱい入ってきたり、フォークもゴスペルもワールドミュージックも演奏するし、ボーカリストもいるし。そのノウハウを自分たちでシェアして教育の分野に手を広げようとしていたりと、この本で取り上げていることをほぼ全てやっている(笑)。意外とこういうものって存在しなかったのかなと。すごい人を集めたスーパーバンドみたいなものは過去にもいくつもあって、ブランドン・コールマンやカマシ・ワシントン、Thundercatが居るLAの「ウェスト・コースト・ゲット・ダウン」のようなコレクティブ的なものもありますけど、ここまで団体として「運営」しているものは他にないと思います。
ーーしかもそれが30人規模で運営されていて、積極的に世界の方々へ飛んでいくという。
柳樂:非常に意識が高い集団ともいえますね。グラミー賞を取ったあと、メンバーである小川慶太さんとやりとりしましたが、彼らはフェスも主催していたりして。ただライブをやるだけではなく、レクチャーやワークショップ、公開トークイベントも含んだりと、教育も含めた催しになっている。今はアメリカ・マイアミで毎年やっているみたいですが、いずれは世界中でもやりたいと思っているようです。それを世界中で続けたら、その土地でのネットワークもできるし、世界的なライブシーンの発展にも繋がりそうな気がしますね。
矢野:今っぽいですね。その意識の高さというか公共的な意識はどこから来ているんでしょう?
柳樂:でも、デューク・エリントンやデイヴ・ブルーベックがいた頃、彼らはアメリカで儲けた金で、世界中へライブをしに行ってたんですよ。その頃って社会主義と資本主義が対立してたりして、アメリカ文化を広げることで資本主義側が乗り込みたいという政治的な思惑もあったようなんですが、その国策的な試みが大きく作用して、世界中にジャズが浸透したともいえます。さらに、彼らが世界で得た音楽を持ち帰ったことで、アメリカの音楽自体も新たな発展を迎えたり。「ジャズは文化の架け橋」というアメリカ的な意識はいい意味で根付いていると思うんですよね。
矢野:なるほど。そういう意味では、意地悪に言うと、“アメリカ帝国主義”的な集団とも取れるのかな。ただ、単純に破壊的・侵略的じゃなくて、いろんなものを巻き込みながら大きくなっていくような印象は受けますね。
柳樂:平和の帝国主義って感じですかね(笑)。いずれにせよ、ここまで教育がポジティブに捉えられるようになった時代もなかなかないですよね。
矢野:クリエイティヴな発想からすると、教育は「つまらんもんだ」という考えになりがちですからね。それは一方で事実であることは間違いないのですが、少なくともこの本で取り上げているフィラデルフィアの話は、かなり前向きなものだと思います。あれを「エリート主義的だ」と言う人はいるかもしれないけど、その試みが切り開いた可能性や、生み出した豊かなものがあるというのは事実に変わりないですから。
(取材・文=中村拓海)
■柳樂光隆
79年、島根・出雲生まれ。ジャズとその周りにある音楽について書いている音楽評論家。「Jazz The New Chapter」監修者。CDジャーナル、JAZZJapan、intoxicate、ミュージック・マガジンなどに寄稿。カマシ・ワシントン『The Epic』、マイルス・デイビス&ロバート・グラスパー『Everything's Beautiful』、エスペランサ・スポルディング『Emily's D+Evolution』、テラス・マーティン『Velvet Portraits』ほか、ライナーノーツも多数執筆。
■矢野利裕(やの・としひろ)
1983年、東京都生まれ。批評家、ライター、DJ、イラスト。東京学芸大学大学院修士課程修了。2014年「自分ならざる者を精一杯に生きる――町田康論」で第57回群像新人文学賞評論部門優秀作受賞。近著に『ジャニーズと日本』(講談社現代新書)、共著に宇佐美毅・千田洋幸編『村上春樹と一九九〇年代』(おうふう)など。