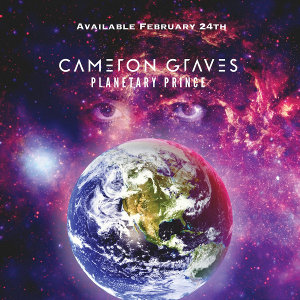『Jazz The New Chapter4』刊行記念対談(後編)
音楽における「教会と教育」の重要性とは? 新世代ジャズ奏者の台頭から考える
ジャズの新潮流についてのガイドブック『Jazz The New Chapter』シリーズの4作目『Jazz The New Chapter4』についての対談。前編では、同著を監修したジャズ評論家の柳樂光隆氏と批評家・矢野利裕氏が、改めて『Jazz The New Chapter』らしさや、同シリーズにおける「モダンジャズ」の位置付けなどについて議論を交わした。後編では、アメリカ音楽における教会と教育の重要性について、新世代のジャズ奏者や彼らを発掘したプロデューサーの発言などを踏まえ、いま一度考えを巡らせた。(編集部)
「レアグルーヴ的に再評価されていたオルガンをもう一度批評的に扱ってみたかった」(柳樂)
ーー教会についての話に戻すと、このテーマは教育としての場所もそうですし、ゴスペルという音楽の機能がこのシーンやアメリカにとっていかに重要だったかが垣間見える内容にもなっています。
柳樂:僕自身、ここ何年かですごくゴスペルに関心があって、それはロバート・グラスパーから派生した興味なんですけど、近年はカニエ・ウェストもChance The Rapperもそこに接近していて、アルバムにいきなりコンテンポラリーゴスペルシーンの大物カーク・フランクリンが呼ばれたりする。でも、実際にカークがチャンスのアルバムでやってることって「語り」だけなんですよ。ライブでも実際に歌わないし。
ーービルボードライブ東京での公演を実際に観ましたが、基本的に歌はコーラス隊が担当して、彼はバンドと観客を扇動することに徹していましたね。
柳樂:それでわかったのですが、ゴスペルが伝えたいのっておそらく聖書のメッセージなんですよ。だから、公演の途中にも演奏はいったん休憩する感じで聖書を読む時間があったりする。アルバムにも必ずそういう語り曲が収録されていて、「メッセージを伝えなきゃいけないみたいなのが前に出た時、それは歌に乗せない」という空気感がある。普通に言葉として言わなきゃいけない、という深刻さと結びついているような気がしました。ケンドリック・ラマーが2Pacの音声に合わせて語りを入れている「Mortal Man」も、重要なメッセージはラップではなく語りにしているという意味では、ある種ゴスペルっぽいなと。
矢野:Public Enemyが「Bring The Noise」でマルコム・Xの言葉を乗せるようなセンスとも通じているんですかね。
ーー教育の話が出たので掘り下げると、『Jazz The New Chapter4』の後半には鍵盤奏者の話として、アートスクールだったり音楽大学だったりでちゃんとジャズ以外のもの、クラシックやヒップホップなど、他ジャンルのことをしっかりと習得させるプログラムが組まれているというのも印象的でした。
矢野:話を一般化しますが、教育制度って基本的にはシステムですよね。徒弟制からなる伝統芸の世界は属人的で、師匠の技をその場で習得しなければいけません。だから、襲名などもする。それに対して、人に属さない教育システムは、テクニックをメソッド化して再現可能なものとします。だからこそ、色んなジャンルへの応用可能性にも開かれます。とはいえ、知性と才能がないと教育に縛られちゃうだけなので、システムとか才能とかさまざまな条件が整って、同時多発的に面白いものが出てきているという現在の状況が生まれたということですかね。
柳樂:同時多発的に出てきたのは、ある種の蓄積が実ったんだと思いますよ。スクールからから出てきたことが目立っていた最初の世代は、おそらく90年代頭くらい、ウィントン・マルサリスを中心としたものなんですよ。彼らは成功こそしたものの、今みたいに新しいシーンを形成するまでには至らなかった。そのあとに出てきたのがブラッド・メルドーやジョシュア・レッドマンなど世代で、彼らは理論的に全く新しいものを作り出したけど、今度は多少難解で一般のリスナーに届かなかった。それらのロールモデルがあって、今に繋がっているのだと考えたいですね。話は少し逸れますが、以前、『外食2.0』って料理の本を読んだら、「肉を調理する温度が年々変わってきている」という話が載ってて。昔は肉に火を通すなら200℃とかだったのが、150℃の方がいいってなって、どれがどんどん進んで一部では65℃がいいってことにもなったという話があって。温度が高すぎると、細胞が壊れてしまい、旨味が抜けてしまうからってことらしいんですけど、そうやって科学が進化していくとそれまでの常識が覆されていく、ということが料理の世界で起こっているそうで、今のジャズシーンはそれに近い感覚を覚えました。
ーー技術の進歩による、必然的な教育の進化があると。で、その固いシステムだけではなく、教会のように開かれた場があるというのが大きいわけですね。
矢野:話がちょっと変わるのですが、ジョン・L・ルーリー、シェリー・A・ヒルの『黒人ハイスクールの歴史社会学』という本の邦訳が昨年出ました。戦後のアフリカ系アメリカ人における中等教育達成率の上昇を計量的に論じた本ですが、ここには、教育制度がユースカルチャーを支えている様子がかいま見えます。だから、この話は、単に「音楽教育が受けられて楽器が上手くなる」という以上に、本当に生活や政治と直結した生々しさを感じるんですよね。メッセージ性の強い曲も多いし、音楽をしなければ生きていけないというリアリティを見出したくなります。
ーー鍵盤奏者の話に戻すと、今回はなぜ鍵盤楽器をわざわざ章立てて取り上げたのでしょう?
柳樂:個人的にはチャレンジだと思っている章ですね。あとはさっき矢野くんが言ってたように、「モダンジャズってどういう位置付けなんですか?」という疑問は一定数あるから、それに対する回答みたいな側面もありますし、鍵盤奏者としてのグラスパーを考えたうえで、ジャズピアノについて深く取り上げてみようと思ったというのもひとつです。あと、僕としてはどうしてもオルガンを取り上げたくて。この章で紹介しているように、鍵盤奏者に左手でベースを弾く人がいるという話から、レアグルーヴ的に再評価されていたオルガンの意味を、もう一度批評的に扱ってみたかったという。
矢野:オルガンは、クラブ音楽のリスナーにとっても重要な楽器のひとつとされていますよね。リチャード・グルーヴ・ホルムスとかジミー・スミスの『Root Down』とかのイメージが強い。モッド~ジャズファンク~レアグルーヴという感じ。
柳樂:そうそう。サンプリングネタとか、踊れるものとして、90年代に浮上しましたけど、音楽的にどうなのかって話があまりになかったので。まぁ、そういうチャラいイメージを一度解体して、違うリスナーにも届けたかったってのもありますね(笑)。
ーーその役割として、宮川純さんのインタビューはすごく興味深く、重要なものになっていると思います。
柳樂:そうなんですよ。いわゆるブラッド・メルドーのような鍵盤奏者とオルガンジャズって、一見遠いところにあるように思えるけど、そうではなかったという答えが示されていますよね。オルガンジャズのイメージを1回解体するというのは、結構ラディカルなんじゃないかなと。つまりオルガン自体がプレモダン的なものを孕んでいて、今はそこに現代性があるんじゃないかということです。そこから鍵盤における左手の重要性にフォーカスして、BIGYUKIのシンセベース論や、唐木さんのベースギター・シンセベースの話になるんですよ。