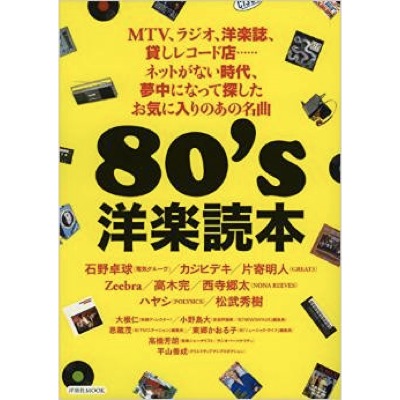来日単独公演記念インタビュー
ニュー・オーダー来日インタビュー:B・サムナーが語るバンドキャリアとイアン・カーティス

ニュー・オーダーの来日公演は最高だった。フェスでは何度も来ていたが、単独公演としてはなんと29年ぶり。それこそ29年ぶりに駆けつけたようなオールド・ファンから、最近知ったような若いファンまで幅広く集めたライヴは、彼らの人間性や辿ってきた人生の道のりがオーディエンスに共振して感動的な世界を形作っていた。相変わらずバーナード・サムナーのヴォーカルはヘロヘロだったけれども(笑)。
ライヴの翌日の5月26日、都内の某ホテルにてバーナード、そして2011年に加入したトム・チャップマン(Ba.)とフィル・カニンガム(Gt.)という若いメンバーが取材に応じてくれた。(小野島大)
「自分の耳が真っ先に反応するのは歌じゃなくメロディ」
――昨日のライヴは大変に素晴らしく、私だけでなくみな大絶賛でした。ご自分たちとしてはいかがでしたか。
バーナード・サムナー(以下、バーナード):とても楽しんだよ。会場の雰囲気がちょっとクラブっぽくてね。そこが良かった。今まで日本では大きなフェスでプレイすることが多かったからね。ああいう親密な雰囲気でやれたのはよかった。
フィル・カニンガム(以下、フィル):あと、ここ数週間ずっとリハーサル続きだったので、ようやく解放されてアルバムの曲を披露できたしね。すごく手応えも感じたし。
トム・チャップマン(以下、トム):お客さんが意外と若い人たちが多いように感じたのも、自分たちにとっては良かったね。
――お客さんはバーナードと同年代の年配の人から若い人まで、幅広い年代の人たちが来ていました。なぜニュー・オーダーは幅広い年齢層にアピールできるんでしょうか?
バーナード:あー、いい質問だね(笑)。長くやってるというのはあるよね。ジョイ・ディヴィジョンのころからのファンも多いだろうし、一方で新作は若い人たちにアピールできたという手応えもある。ダンス・ミュージックの要素が強いから、クラブ通いをする若い人たちにも聴いてもらえてるんじゃないかな。一度ブラジルで14、15歳のファンに訊いたことがあるんだ。「なぜニュー・オーダーを知ったのか?」って。どうやらお母さんがファンで、そこから知ったらしい。ザ・キラーズのブランドン・フラワーズに訊いたら、お兄さんにエレクトロニックの曲を聴かされて、そこからニュー・オーダーにハマったと言っていた。そういう風に世代を超えて受け継がれているのは嬉しいね。
あと、曲がわかりやすく、あらゆる世代に受け入れられやすいというのもあると思うよ。「Love Will Tear Us Apart」も「Blue Monday」も、スタイルは違ってもクラシック・ソングとして、インディーズ・ファンにもクラブ・ミュージック・ファンにも時代を超えて訴える力がある。なぜそのふたつを融合させたかといえば、僕自身がいろんな音楽が好きだから。インディーズ・ミュージックもクラブ・ミュージックも、クラシック音楽だって聴く。ツアー中はもっぱらクラシックを聴いているんだけど、そういう自分たちがやっているのとは違うビートのない音楽からインスピレーションを受けることも多い。そもそも僕が最初にインスピレーションを受けたのは、エンニオ・モリコーネのマカロニ・ウエスタンの映画音楽なんだ。でも若いからパンク・ミュージックをやりたいと思ってバンドを始めた。そうしてひとつのジャンルに限定せずいろんな音楽を交錯させるからこそ面白い。どんなジャンルにも必ず1曲は名作があると思ってるよ。長い答えになっちゃったな(笑)。
フィル:じゃあ僕は短めに(笑)。どんな音楽を好んで聴くかといえば、その時の状況にもよると思うんだ。ツアーの移動中はエネルギーのある音楽を聴いて、ライヴからホテルに戻ってきたらアンビエントな音楽で気を落ち着かせたりね。
――昨日は多くの曲で観客が歌っていました。日本人は英語が苦手なんですが、それでもあなた方の曲は多くの観客に共有されている。なにがそうさせていると思いますか。
バーナード:(黙ってフィル、トムを指さす)
フィル:たぶんメロディだと思う。自分自身音楽を聴くとき、歌というよりは、まずメロディに耳がいくんだよね。自分が曲を書くときもまずメロディが先で、歌詞はあとだ。自分の耳が真っ先に反応するのは歌じゃなくメロディなんだ。歌詞に意識がいくのは最後だね。おそらく観客は歌詞を歌っているんじゃなく、メロディを歌ってるんじゃないかな。メロディは国境を超えたグローバルな言語だと思うから。
――日本では確かにそうだと思うんですが、英国でも歌詞よりもメロディという傾向はあるんでしょうか?
トム:英国では歌うというよりサッカー・ファンみたいなチャントが多いよ(笑)。歌詞を歌ってるといより、ただうぉうぉーと唸ってるだけ、みたいな(笑)。

「実は自分の書いた歌詞にそこまで強い思い入れがないんだよね」
――昨日はよく知られているヒット曲だけでなく、「1963」のような、昔のあまり知られていないような曲もやってましたね。昔の曲の選曲の基準はどういうものなんですか。
バーナード:難しいよ……曲が多すぎるんだよね。贅沢な悩みだと思うけど。
フィル:とはいえ絶対やらないとファンに怒られてしまうような曲を選んでいくとセットリストの7割ぐらいは埋まってしまう。残りは新曲と古い曲だけど、古い曲でやるひとつの基準としては、ライヴ映えするものかな。ライヴで盛り上がる要素は必要で、僕の好きな曲に「Run」という曲があるんだけど、何度かライヴでやってはみたものの、どうもうまくいかないんだよね。アルバムで聴く分にはいいけど、ライヴでやるとイマイチという曲もあって、その曲の本来持っているエネルギーがライヴで伝わるかどうか。その点からいえば、『ミュージック・コンプリート』の曲は全曲ライヴで盛り上げるね。
――昔の自分が書いた歌詞でも、今でも歌える曲と歌えない曲があると思います。今やっている曲は今歌っても違和感がないということですか。
バーナード:実は自分の書いた歌詞にそこまで強い思い入れがないんだよね。それは歌詞の書き方にある。まずトラックを先に作るんだけど、そこから自分が刺激を受けて、この曲のメロディを書きたいと思わせるものじゃなきゃダメだ。メロディができて、そこで初めて歌詞を書くんだけど、僕の書き方はちょっと変わっていて、自由連想法(Free Association)というやり方をとっている。自分の頭をまっさらにして曲を聴く。そこで頭に浮かんだ言葉を歌詞にしていくというやり方なんだ。そこに自分なりの思いを込めるというより、音楽を聴いて連想する言葉を歌詞にしているだけで、そこに感情的な繋がりはないんだよね。その書いた歌詞をしばらくたって読み返してみて、ああ自分はこういうことを言っていたのかと気づくときはある。ジョイ・ディヴィジョンのときも、曲作りで煮詰まったら全員でお喋りして、話すことがなくなったら演奏に戻って、ということをやっていた。これは歌詞の作り方とはちょっと違うけど。
――「やらないと客が納得しない曲」というのは確かにあると思います。エリック・クラプトンだったら「Layla(いとしのレイラ)」、ディープ・パープルだったら「Smoke on the Water」、ニュー・オーダーだったら「Blue Monday」みたいな。そういうお決まりの曲をお約束のようにやることに抵抗はありませんか。
トム:でもやらないわけにはいかないよ~(笑)。やらなかったら暴動がおきちゃう(笑)。
フィル:バーナードは「Blue Monday」をやりたくないみたいだけど(笑)。
バーナード:そういうのは自分だけの気持ちで決めるんじゃなく、お客さんのことも考えないとね。特に東京は4年ぶりのライヴだから、みんなが聴きたい曲をやらないのは失礼だと思う。まあ、もう2度と(「Blue Monday」を)演奏しなくても僕は構わないけどね(笑)。でもまあチケット代を払ってくれた人は聴きたいだろうから、やるよ。
――確かにオリジナル・メンバーのバーナードはそういう責任を負っているかもしれないけど、若いおふたりには関係のない話ですよね。最近の曲だけやればいいのに、と思いませんか。
フィル:もちろん僕たちだって昔の曲をやることに喜びを見いだしているんだよ。特に昔の曲をやった時にお客さんの反応は他では得がたいものがあるからね。昨日の「Blue Monday」をやった時の盛り上がりも凄かったからね。でもリハーサルではそういう昔の曲はやらない。バーニーがあまりやりたがらないから(笑)。でもお客さんは喜んでくれるし、そういう反応がまた曲に新たなエネルギーを吹き込んでくれる。
バーナード:いやいや、そこまで嫌ってないよ(笑)。でもライヴ・セットをひとつの長い曲と考えると、欠かせない重要な一部だと思ってる。