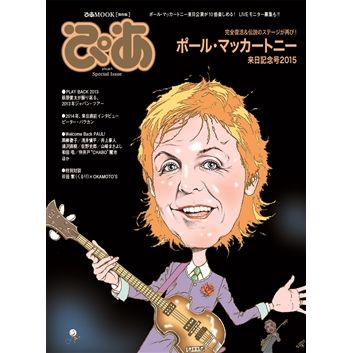市川哲史の「すべての音楽はリスナーのもの」第33回
ジェフ・リンの武器は〈世界一の無垢さ〉だーー市川哲史がELO14年ぶりの新作を機に再分析
とはいえELO時代のジェフ・リン節はあまりに見事で巧みすぎたため、「こういうメロやサウンド好きでしょ?」と背中で言われてるような違和感があったのも事実だ。狙ってるんだろうな、と。
ところがELO以降の彼は選手兼任監督というか、「唄って弾けて作曲編曲もできる」名プレイング・プロデューサーとして立派な実績を積み重ねてきた。
80年オリヴィア・ニュートン・ジョン。84年デイヴ・エドモンズとエヴァリー・ブラザーズ。87年ジョージ・ハリスンにロイ・オービソン。88年ブライアン・ウィルソンやランディ・ニューマン。89年トム・ペティ。91年デル・シャノンとトム・ペティ&ザ・ハーロブレイカーズ。92年リンゴ・スターにジョー・コッカー。94年トム・ジョーンズ。97年ポール・マッカートニー。12年ジョー・ウォルシュ。
やたら大物クライアント揃いではないか。しかも彼がプロデュースした作品のほとんどが、「久々の復帰作」だったり「長年の試行錯誤からの脱出作」だったり「心機一転再出発作」だったり結果的に「遺作」だったりと、ワケあり物件揃いだから面白い。
彼がプロデュースしたサウンドは事前に知らずとも大抵わかってしまうほど、リンの手癖はアクが強い。なので古くからのクライアントのファンから「オーバープロデュース」と嫌われることも、少なくはない。
しかし前述したBD/DVD収録の長編ドキュメンタリーには、リンへの感謝を語るクライアントおよび関係者が勢揃いなのだ。
「俺は再起を図って久しぶりにアルバム作りを始めてた。『ちゃんと生きよう』と頑張ることにしたんだ。で早速ジェフに依頼したら、見事に数曲をプロデュースしてくれた。それを契機に俺は軌道修正できたんだから」(リンゴ・スター)
「ジェフこそロイ(・オービソン)をスタジオに復帰させた張本人さ。それでロイは完全に返り咲いた。ジェフ抜きトラヴェリング・ウィルベリーズだってあり得なかったし――ウィルベリーズでのジェフは過小評価されてる、すごく貢献してたのに」(トム・ペティ)
「ジェフに誘われて、ロスのスタジオにロイと私は曲を聴きに行ったの。ジェフが最初に披露してくれた“A Love So Beautiful”を聴いたロイが泣き出した。結婚して20年、あんな夫を初めて見たわ。ジェフも戸惑っちゃってね、だってロイが座ったまま涙を流してるんですもの」(バーバラ・オービソン)
「ジョージ(・ハリスン)はニューアルバムのプロデューサーを探してたの、8~9年ぶりのレコーディングだったし。誰かの力が必要だったそんな時に、本人に会う前からジェフの音楽が常にジュークボックスから流れてたわ。“テレフォン・ライン”よ(笑)。だから初対面の気がしなかった。ジェフとジョージはとにかく似てたのよ。笑いのツボも同じで北部育ちで年齢も近くて、ジョージが兄って感じかしら。しかもお互いの音楽が大好きだったの、意気投合とはこのことだわ」(オリヴィア・ハリスン)
ジェフ・リンとはおそろしく優秀な〈再生人〉なのだ。
そして彼の行動原理は、かつて黄金の輝きを放っていた頃のロック/ポップ・ミュージックのサウンドを後世に伝えたいだけ、のように映る。そこにはありがちな私利私欲も自己顕示欲も一切ないのだから、まさに奇跡のような話だ。
たとえばジョージ・ハリスンの『クラウド・ナイン』は全編、まるで〈ビートルズあるある〉を片っ端から実現させたようなリンのプロデュースが、世界中の潜在的ビートルズ・ファンをくすぐった。
たとえば〈夢のスーパー・ルーツ・ミュージック・グループ〉トラヴェリング・ウィルベリーズは、ジョージとボブ・ディランとトム・ペティとロイ・オービソンとデル・シャノンの音楽が元々好きなリンが制作の実務を担ったからこそ、アルバムを2枚も世の中に送り出すことができた。
そんな極めて人畜無害な〈デキるオタク〉だからこそ90年代前期、ジョン・レノンが生前カセットテープに遺したデモ音源に他の3人ビートルズが新たな演奏とヴァースを加えて〈ビートルズ四半世紀ぶりの新曲〉を完成させるという、世紀の《ビートルズ・アンソロジー・プロジェクト》の現場監督を任されたジェフ・リンなのだ。
結局このプロジェクトは「フリー・アズ・ア・バード」と「リアル・ラヴ」の2曲を、新たにビートルズのレパートリーに加えた。にしてもプロトゥールスもない時代にレノンのカセット音源のぐだぐだピッチを揃えるなど、リンの几帳面な性格による圧倒的な献身なしでは陽の目を見なかっただろう。それは誰もが認めている。
まあELOが過去にあれだけ売れ、しかも音楽以外に趣味がないばかりか金の懸かる道楽とは一切無縁なのだから、死ぬまで金には困るまい。それでも彼の〈世界一の無垢さ〉は、煩悩の河を死ぬまで泳ぎ続ける運命の我々からすればやはり、信じ難い。
前述のドキュメンタリーによればリンは故郷バーミンガムで、まだ暗い朝7時半から煙草で煙たい不健康なバスに揺られて通う工場で8時間労働の毎日。だからこそ音楽にすがるしかないのは、ロック者の定番コースだ。
しかしながらリンの述懐を聴いてると、正体不明の違和感を覚える。
「子供の頃、父親からクラシックのウンチクを日常的に聞かされてた。曲の構成から楽器の編成からね。でも不思議だったよ、彼はそんな男じゃないんだ。バーミンガムの道路工事をしてた人で――舗道の整備をするような奴がそんな博識だとは思わないだろ? だが本当は賢かった。ラジオから流れる曲に合わせてハモれたしさ、ピアノも指1本で弾いてたよ。そんな親父の影響は受けていると思う」
「この仕事に就けて何が嬉しかったかって、母親を黙らせたことだね。階段をドタドタ上がってくるなり、『起きて!』と怒鳴るんだよ――まだ朝の8時前にだぜ? でもある朝言ったんさ、『母さん待って、僕もう起きないよ、プロのミュージシャンだから』。その言葉を聞いた瞬間のお袋ったら(嬉愉笑)」
サザエさんちかジェフ・リン一家は。両親を大切に想う厨二って、無敵な気がする。
そりゃポップ・ミュージックの無限の可能性を一貫して信じ、常に完璧を期して昔気質の音の再現に励み続けられるだろう。純情無垢はクリエイティヴだ。