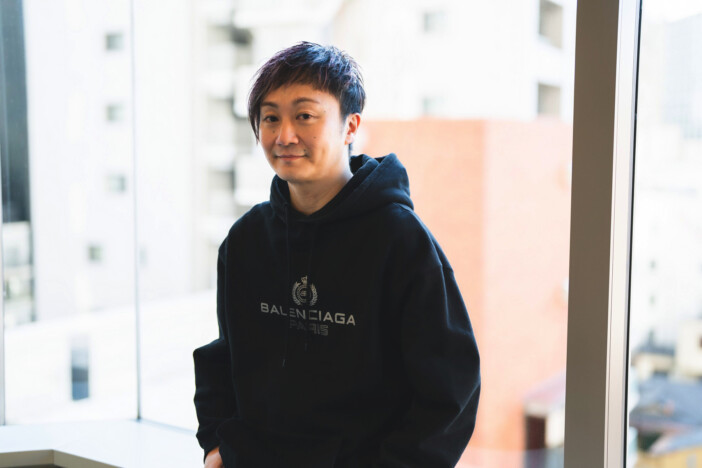ゲームクリエイターの創作ファイル:第6回
舞台脚本とゲーム制作に共通する「完成させること」の大事さ 『ネタバレが激しすぎるRPG』作者・みぬひのめの創作ポリシー

「バトルが楽しくてRPGを遊んでいた」からこそ追求する“バトルの面白さ”
――いまはゲームも個人で作れるようになりました。時代の移り変わりにはどのような思いを持っていますか。
みぬひのめ:ありがたいことだなと思いますね。昔はゲームを作ろうとなれば、プログラムのコードの書き方をはじめ、いろいろな知識が必要でした。でも、いまはゲームに限らず、なにかしらアイディアを思いついた人が手軽に表現できる環境が用意されている。これはすごくいいことだと思います。もちろん、『RPGツクール』でゲームを作るにしてもいろいろと試行錯誤は必要となりますが、プログラムのコードを書くことは求められません。本当に心から「『RPGツクール』があって良かった!」と思っています(笑)。
――今後、『RPGツクール』以外のゲーム制作ツールにチャレンジする展望はあるのですか?
みぬひのめ:現時点ではないのですが、ちょっと違うタイプのゲームを作ろうと思ったときには手を出すかもしれません。『RPGツクール』の制作に慣れていることもありますし、もともとストーリーを書く人間ですので、作るとなればRPGかな、というのもあります。
いわゆるノベルゲームのような、読み物主体のゲームは自分にとってRPGよりも難易度が高いと感じているんです。RPGは探索パートとバトルパートで変化を付けたり、プレイ時間を稼いだりすることができますが、読み物だとそれ以外の飽きさせない何かが必要になってくるので、ハードルが高く感じています。
――『ネタバレが激しすぎるRPG』のバトルの難易度が歯ごたえのあるバランスに調整されていたのも、そのような考え方から来ていたのでしょうか。
みぬひのめ:そうですね。僕自身がバトルが楽しくてRPGを遊んでいたタイプの人間ですので。やはり「そこに何かひとつ面白いものがなければ」と思っているんです。特に『ネタバレが激しすぎるRPG2』はストーリーも含めて、全体的なプレイ時間が結構長めの想定になりましたので、バトルが単調だと飽きちゃうだろうなと考えたんですね。それも含めて、いろいろとこだわりを入れています。本当にできそうなことは全部やりきるというか、「僕が考えた最強のRPG」にするくらいの気持ちで作りました。

――続編のバトルはスキルの重点的な活用が試されるなど、システム面において前作からの大きな変化がありました。それもバトルに対するこだわりによるものだったのでしょうか。
みぬひのめ:そうですね。それこそ一番最初に作った『バトルサガ』が戦闘メインのゲームでしたから、やっぱりバトルが好きなんでしょうね(笑)。
――ちなみにこれまで遊ばれてきたRPGの中で、好きなバトルシステムってありますか?
みぬひのめ:振り返ってみると、『マリオストーリー』かもしれません。アクション性や、仲間を切り替えてコマンドを選ぶ戦略性がありましたので、バトルを楽しんでいたものとしては『マリオストーリー』が一番になるのかもしれないです。
実はクラウドファンディングを超える額を費やして完成した続編
――今回の続編は有料タイトルとして発売されています。前作はフリーゲームでしたが、有料にすると決めた経緯を教えてください。
みぬひのめ:実はクラウドファンディングを始めたときは、無料にするか有料にするかで迷っていたんです。ただ、「そろそろ1回、有料で出すという経験をした方がいいのではないか」「どれくらい買ってもらえるものなのかな」と思い始めまして、有料にすることを決めました。
あと、想定よりもクラウドファンディングで資金が集まってしまって、そうすると相応のクオリティで出さなきゃいけないなという思いになったんです。その結果、調子に乗ってクラウドファンディングを超える額を制作に費やしてしまいまして(笑)。それを取り戻さなくてはいけなくなってしまったという事情もありました。
――これはちょっと答えにくいかもしれませんが、売上はどうなのでしょうか……?
みぬひのめ:赤字は解消しました!
クラウドファンディングを超えた分の額は埋まりましたので、これからついに黒字のターンですね(笑)。
――海外のプレイヤーから「翻訳版を出してほしい」という声は来ているのでしょうか。
みぬひのめ:ありました。実は続編の体験版は韓国語バージョンがどこかに出ていたりするんです(笑)。
ただ、海外版を出すことについてはいま、慎重になっています。無料であれば「勝手に翻訳して、勝手に出してください」でいいのですが、今回は有料ということもあって、お金を払う必要があったり、翻訳のクオリティに関する判断がしにくいところがあるんです。
ゲーム内オプションで言語を変えられるプラグインもいろいろ見たのですが、「これはちょっと難しいかも……」となりまして。あと、仮に翻訳版を出すとなれば、すべてのバグを完璧に取り除いてから出さないと、後々バージョンアップするときにすべて直さなくてはいけない手間もあったりするんです。そのこともあって、慎重になっています。
――この作品のストーリー自体が割と日本語前提であることを思うと、翻訳はすごく大変なのでは……。
みぬひのめ:ですよね……! ただ、韓国語と中国語は意外に翻訳できるようなんですよ。逆に英語がかなり難しくて。前に「英語版を出してくれ」という声をいただいたりしたんですけど、上手くかみ合わなくて出すには至っていないんです。海外版の具体的な計画はないというのが現状ですね。
――なるほど。今後、2025年の4月にはWEB小説の書籍版が出ると伺いました。
みぬひのめ:はい、書籍化が決まりました。最初はWEB小説版をそのまま書籍化するのかなと思っていたのですが、結構いろいろなところを直しています。僕は普通の文学作品を読んできたこともあって、「あ、ライトノベルにはこういう作法があるんだ」と学ぶこともありました。
――その文学作品というのは、どのようなものを特に読まれてきたのでしょうか?
みぬひのめ:一番読んだのは中村文則さんの作品ですね。これまでに出版されたものはほぼ全部読んでいると思います。お話としては暗い感じと言いますか、孤独がテーマになっていたりするのですが。
――続編のストーリーも「孤独」がテーマになっているところがありましたが……。
みぬひのめ:背景などはあまり意識していませんが、雰囲気については影響を受けているかもしれないです(笑)。
ゲームを作り始めたときに考えたのは「絶対にコンシューマの土俵には乗らないこと」
――『ネタバレが激しすぎるRPG2』ではやりたいことをやり切ったというお話がありましたが、次は考えられていたりするのですか?
みぬひのめ:もし次を作るとなれば『ネタバレが激しすぎるRPG2』のエピソードゼロを作ろうかなと考えています。ただ、RPGとしてこれ以上、何かこだわったものを作れるかはちょっと分からないです。もちろん、ストーリーはまた何か驚かせられるようなものを考えたいと思っているのですが、システム面がちょっと分からないです。
――あと、いまのところ『ネタバレが激しすぎるRPG』が続いていますが、ほかの「すぎるRPG」の新作は考えられているのですか?
みぬひのめ:いくつかアイディアはありまして、できれば今年中にも時間ができたときに作りたいなとは思っています。本当は昔のように30分ほどで遊べるくだらないゲームを作りたいんです。けど、忙しさの度合いを見て、となりますね。
――舞台の方も今後、変わらずご活動されていく形で?
みぬひのめ:はい。今年も6本ほど舞台の仕事があります。そろそろ舞台の仕事は少しセーブしようかなと思ってもいるのですが、これからも年5~6本はやっていくのだろうなとは思っています。
――制作するゲームのジャンルについても、引き続きRPG中心としていく方針なのでしょうか。
みぬひのめ:RPGを作っていきたいですね。せっかくここまで伸びてきたので、またみなさんに楽しんでもらえるようなゲームを作っていきたいと思っています。ただ、これまでよりも時間がかかるかもしれません。規模感が大きくなってきていますので……。
実際、制作中は「二度とやらない!」と思ったりもするんです(笑)。続編はボイスなどのデータを全部詰めて、切り分けたりして……ものすごく大変だったので。でも、そう思いながらきっと、次もやるんだろうなと思います。
――最後にお伺いしたいのですが、みぬひのめさんにとって、個人でゲームを作るうえで大切にしている姿勢などはありますか。
みぬひのめ:私が個人でゲームを作り始めたときに考えたのは、「絶対にコンシューマの土俵には乗らない」ということです。特にフリーゲームの場合、真面目にクオリティの高いRPGを作ると、「これだけのものが出せるなら、もっとクオリティの高いゲームがコンシューマにあるよね?」と比べられてしまうことがあると思うんです。
自分が作った『速すぎるRPG』は「どう考えても、コンシューマゲームを作る会社はこんなゲームを出さないだろう」という考えで、思いついた面白いアイディアを第一にしました。そうすることで「なんか面白そうなことをしている人がいる」と認識してもらえたりするので、コンシューマの土俵には乗りにいかない方がいいと考えています。
あとは、抜くところは抜いた方がいい、でしょうか。「速いRPGを思いついた!」となったら、「速い」という部分にこだわりつつ、バトルやストーリーに深みを持たせるところは捨ててもいいのでは、という考え方です。こだわる人は敵や背景のグラフィックを最初から作ったりしますし、その面白さもあるのですが、時間がかかってしまいます。「俺はストーリーを見せるんだ!」と思ったらストーリーを重点的に頑張る、というのが挫折しないコツのひとつかなと思います。

――何よりもまず、完成させることが大事である、ということですね。
みぬひのめ:そうです。完成させることがとにかく大事ですね。世に出してみることによって、反応も分かりますから。その結果として「あ、これはそんなにウケるんだ」「こういうところでつまずいてしまうのか」というのも分かる。「じゃあ、それを活かして次を作ろう」とやっていくんです。
それと、最初は短いゲームを作るのがいいと思います。いきなり長いゲームを完成させられる人もいますが、かなりの確率で挫折しますから。世に出さないゲームをずっと作り続けるよりも、まずは短いゲームで1回、完成させるという体験をして「よし、俺はゲームを完成させられるんだ! 作れるんだぞ!」と思ってから、少し長いゲームを作るのがいいと思います。
これは僕自身がそうだったということもあります。今回の続編はプレイ時間が12~15時間となっているのですが、いきなりその規模のゲームを作るのは絶対に無理でした。短いゲームを完成させてきた体験があったからこそ、やり切れたんだと思います。
――まさに小さいものから徐々に積み重ねていくのが大事ということですね。それも舞台脚本の経験が活かされているのでしょうか。
みぬひのめ:そうですね。最初のころはわずか5分の台本も書いていました。完成させることが大事で、かつなるべく早く人目に出した方がいいと思うんです。そこで「反応が薄かった」「あまり受けなかった」と学習して、「次はどうするか?」と考えて行動していくんです。
あと、これは舞台でも言われたりすることで、「入口から遠いところに出口を置いておくといい」というのがありまして。『ネタバレが激しすぎるRPG』がそうなのですが、「ネタバレしてくだらなそうだな」という入口から、最終的には「あれ? なんか深い話だったかも……」と、最初の予想どおりに終わらない方が、ゲームをプレイする人の体験としてはいいものになるのではないでしょうか。
前半をくだらなくして、後半に深い話をするようにしたら、その差もあって退屈しないと思いますし、ずっと深い話ばかりされると結構、おなかいっぱいになっちゃったりしますからね。そうした工夫をしていくと、いい体験が出来上がるのかなと思っています。
※1 『RPGツクール3』:1997年にアスキー(現:エンターブレイン)より発売されたPlayStation向けにRPG作成ソフト。それまでスーパーファミコン向けに展開されてきた「RPGツクール」シリーズとしては、初めてのPlayStationプラットフォーム向けタイトル。
※2 『マリオストーリー』:2000年に任天堂からNINTENDO64(ニンテンドウ64)向けに発売されたアクションRPG。背景が3DCG、キャラクターが2Dドットのグラフィックが特徴で、後の『ペーパーマリオ』シリーズの原点となった。2025年現在は『NINTENDO 64 Nintendo Switch Online』でプレイ可能(要「Nintendo Switch Online + 追加パック」加入)。
※3 『RPGツクール4』:2000年にPlayStation向けに発売された「RPGツクール」シリーズ第4弾。サイドビュー戦闘、属性の概念といった新要素の数々を売りにしている。
※4 『RPGツクール5』:2002年にPlayStation 2向けに発売された「RPGツクール」シリーズ第5弾。シリーズで初めての3D機能の追加と、キーボード操作への対応を売りにしている。また、シリーズでも随一の制作自由度を誇ることから、ゲーム制作においては一定の技術力が必要とされる。
※5 『ゼノサーガ』シリーズ:ナムコ(現バンダイナムコゲームス)より発売されたPlayStation 2向けRPG。2002年から2006年にかけ『エピソードI[力への意志] 』『エピソードII[善悪の彼岸] 』『エピソードIII[ツァラトゥストラはかく語りき]』の三部作が発売された。開発は2025年現在、任天堂の完全子会社で『ゼノブレイド』シリーズを代表作とするモノリスソフト。
PCゲーム『ネタバレが激しすぎるRPG2―親友の真の姿は大魔王―』販売ページ(BOOTH)
考えるのは常に「鋭利な刃を心にブッ刺す」こと “泣きゲー”のパイオニア・麻枝 准が貫く創作の信念
リアルサウンドテックの連載「ゲームクリエイターの創作ファイル」では、“ゲーム作り”にフォーカスしてクリエイターたちにインタビュー…