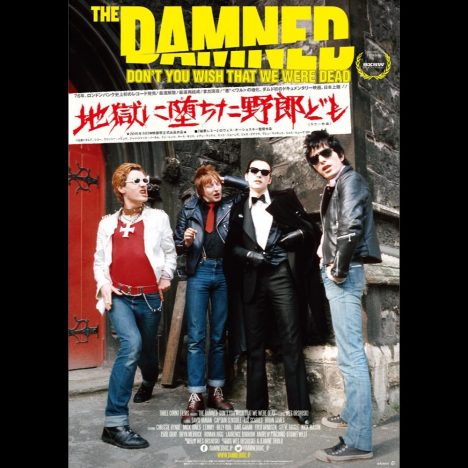イギー・ポップの音楽への姿勢は70歳を過ぎても変わらないーーISHIYAの『ギミー・デンジャー』『アメリカン・ヴァルハラ』評

パンクというアティテュードを確立した開拓者であるイギー・ポップを語る上で、ザ・ストゥージズの存在は欠かせない。

そのザ・ストゥージズ時代からのイギー・ポップの歩みを、自身やメンバーのインタビューを軸に辿っていくドキュメンタリー映画『ギミー・デンジャー』のDVDが、3月28日にキングレコードから発売される。タイトルになっているのがザ・ストゥージズの曲名であることからもわかるように、本作はイギー・ポップの長い音楽人生の中でも、ほぼザ・ストゥージズ時代のみについての映画になる。だが、イギー・ポップという人間は年齢を重ねた今もなお、挑戦し続ける姿勢を持ち続けている。
2016年にイギーは、ソロアルバムとして18作目の『Post Pop Depression』を発売した。このアルバムはイギー自らが自費でレコーディングを計画し、ジョシュ・ホーミ(クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジ/イーグルス・オブ・デス・メタル)にプロデュースを依頼した。そして、UKアルバムチャート初登場3位、USアルバムチャートでは17位という、イギー・ポップ名義では最高位を獲得するほどのヒット作になった。このアルバムの、制作過程からツアーまでを追ったドキュメンタリー映画『アメリカン・ヴァルハラ』が、4月14日より新宿シネマカリテで公開される。

「シンプルであること」は、パンクの中で最も重要な位置を占める要素であるが、その要因となった逸話が『ギミー・デンジャー』内で語られているのは非常に興味深い。イギーは、子どもの頃に観ていたテレビ番組「スーピー・セールス」が大好きで、その番組で子供に手紙を書くように呼びかける言葉「手紙を書くときは25語以内」を鮮明に記憶しており、ドラムからボーカルへ転身した際の歌詞制作の基礎としたようだ。ごく短く、1語も無駄のないザ・ストゥージズでのイギー・ポップの研ぎ澄まされたシンプルな歌詞は、パンクに絶大なる影響を与えた。「NO FUN」や「1970」などのほかにも、多くのパンクバンドが数々の名曲をカヴァーしていることを知っているファンは多いだろう。その影響力の下に、パンクバンドが存在していることも『ギミー・デンジャー』には収められている。
ステージダイビングというパフォーマンスを発明したのもイギー・ポップだということや、あの唯一無二のボーカリストが音楽活動を始めた当初はドラムだったという衝撃の事実を、マニアックではないがイギーの大ファンである筆者は『ギミー・デンジャー』によって知った。イギーの創世記からザ・ストゥージズ再結成までが収められた『ギミー・デンジャー』を観ることで、ザ・ストゥージズとイギー・ポップをより深く知ることができる上に、4月18日より上映される現在のイギー・ポップが映し出された映画『アメリカン・ヴァルハラ』を、さらに深みが増した視点で鑑賞することができるだろう。

イギーの最新アルバムである『Post Pop Depression』のレコーディングからツアーまでを追ったドキュメンタリー映画の『アメリカン・ヴァルハラ』は、バンドという形態で楽曲を作成し、レコーディングをしてツアーを行うことのすべてが詰まっていると言っても良い映画だ。バンドをやったことのない人間にも、そのあり方が非常によくわかる作品になっている。
良い作品ができる見本のようなバンド形態は、ジョシュ・ホーミのプロデュース力と、ミュージシャンたちの魂を、イギー・ポップという神のような存在がすべてを受け入れることによって昇華して形成されていく。その様子が手に取るようにわかり、バンドをやっている人間には羨ましくもあり、見習う部分が多い映画でもある。

親密なコミュニケーションをとるために、人生やバンドの先輩であるイギーのとる行動がいちいち素晴らしい。イギーが初めてジョシュに「俺と曲をつくらないか?」とメールを送ったあとに、ジョシュからの返信が途切れた際にも、イギーは粋な計らいをみせる。憧れのアーティストであるイギー・ポップからのメールに戸惑うジョシュの緊張感や葛藤も詳細に描かれる中、ジョシュを乗り気にさせるために、イギーは彼の好きな曲についての秘話などを、あえて電子メールではなく紙に書かれた膨大な資料で送る。「そこがミソだ」と語る、イギーの経験に基づいた作戦による贈り物は、ジョシュを驚愕させ、このバンドへのモチベーションが尋常ではないものへと高まる。
ジョシュ・ホーミと初めて会う際にもイギーは、空港へ迎えに行こうとするジョシュを「家の前で会おう」と断り、1人新しいメンバーの家の前でバッグを持って立っていたようだ。その姿を想像するだけで傑作であると同時に、新しいメンバーの信頼が生まれることが容易に想像できる。「どうせ遅刻すると思った」と言い放つユーモア溢れる気遣いは、心を開きあった友人関係である姿が見え、このアルバム制作過程がどれだけ親密に行われたかがわかるシーンである。
メンバーも、ジョシュのバンドであるクイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジのディーン・フェルティタと、アークティック・モンキーズのマット・ヘルダースに決まり、レコーディングをすることになる。ジョシュが選んだのは、カリフォルニア州ジョシュアツリーという、砂漠のど真ん中にある「ランチョ・デ・ラ・ルナ」というレコーディングスタジオだった。レコーディングという状況は、ただでさえその制作過程から録音に到るまで、バンド全員が一つのことに集中し、演奏力や結束力が高まるものだが、食事などの生活をともにしながらのレコーディングは、より一層バンドの一体感や結束力が生まれる。砂漠のど真ん中で、何もない場所であれば尚更だ。
また、レコーディングをする際に、非常に重要な役割としてエンジニアの存在がある。このスタジオのエンジニアであり、住人でもあるパトリック・ハッチソンという人物も、アルバム『Post Pop Depression』にとって欠かせない人物であることがわかる。「俺が何をつくろうと、誰も知ったこっちゃない。他のヤツらがどう思おうと俺には関係ない。俺の内側に何があるか見たいだけだ。友達と家族以外には何もない。だから音楽を作るんだ」作品中に彼が語るこの言葉が、心に響かない音楽家は存在しないだろう。
そんなパトリックは、料理も得意なためにメンバーの食事も担当する。メンバーで一緒に食事をしながら、生活を共にするバンド形態は『ギミー・デンジャー』で描かれている、デトロイトで共同生活をするザ・ストゥージズと何ら変わりがない。