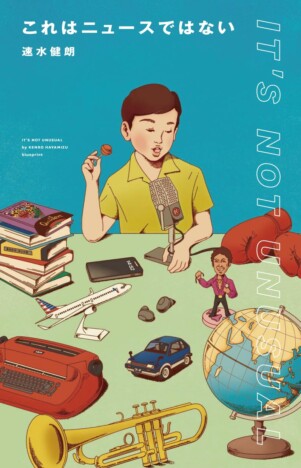高梨臨は“頼りになる”ヒロインだーー小栗旬の“悪の体現”支えた『代償』の演技

30分台の回もあれば、1時間を超える回もある。そんな先の読めない伸縮に、ドクドクと鼓動が高鳴り、早く次が見たいという欲望の血流があふれ出る。全6話から成るHuluドラマ『代償』は、地上波ドラマではありえない自由奔放なフォーマットに、禁断の描写、テーマを交え、さらに映画にはおさまりきらないボリュームと連続性で視聴者を虜にする、破格の吸引力を誇る作品だ。
少年時代に出逢い、家族を奪われ、精神をズタズタにされた。そんな忌まわしい相手が、いまは弁護士として成功している青年の前に現れる。男は、弁護士に、自身がかけられている強盗殺人事件の容疑の弁護を依頼する。一度は断ったものの、同僚で婚約者の女性に危険が及ぶ可能性を察し、忘れたかった過去に向き合い、男を断罪することを決意する。
そんな物語の中で、小栗旬は、恐ろしいほどの知能犯である男に、逆に、徹底的に追い詰められていく主人公を力演している。構図は、アート型連続殺人をおこなう犯罪者に囚われていく刑事を演じた、現在公開中の映画『ミュージアム』に近いが、小栗の芝居を噛みしめる上では『ミュージアム』以上の妙味が『代償』にはある。なぜなら、基本的に『ミュージアム』の刑事の精神構造は一枚岩だが、忌まわしい過去にホルマリン漬けにされている『代償』の弁護士は脆さの裏返しとしての虚勢に満ちており、ガタガタとドミノ倒しのように崩れ果てていく“反転”のダイナミズムを生きているからだ。

小栗は、もちろん正義も演じられるが、悪を体現したときに、鈍い光を放つ。たとえば、若き日に14歳の冷酷な超知能犯を演じた『イズ・エー』(2003)などは忘れがたい妙演なのだが、自身の後ろめたさに蓋をして生き延びてきた『代償』の弁護士がふと見せる、無自覚な悪のほころびは、この俳優がほんとうに久しぶりに見せてくれた得難い魅惑だと思う。
だが、ここでは、その小栗を支えるヒロインに扮した高梨臨について考えてみたい。
役どころもそうなのだが、演技のアプローチとしても、高梨は小栗を支えている。小栗が“反転”を体現しているとすれば、高梨は“不動”をあらわしている。そのことによって、主人公の激しい揺れ動きが顕在化する。
このヒロインは、主人公が働く弁護士事務所の社長の娘であり、いわゆるお嬢様に属するタイプの女性だ。おそらく、順風満帆の人生を歩んできており、だからこそ、主人公が陥っている底なし沼のような地獄についても想像が及ばない。

高梨は、ヒロインのそうした性格を欠落としてではなく、かけがえのない個性として表現している。このお嬢様はお高くとまっているわけではなく、世の底辺に馴染みがないからこそ、性善説をまるごとに飲み込むことができている。
本来であれば、世間知らずの一言で一蹴されようなキャラクターが、いわゆる無垢な個性ではなく、むしろ頑丈な人物として成り立っている。一途であり、一本気であることに、無理がない。見事な造形だ。
もちろん、心情的には揺らぎもある。秘密を抱えているのになかなか明かしてくれない恋人への不安。そして、容疑者に人間性を見い出し、寄り添うとする様。彼女のうつろいは、物語の展開に大きく付与するが、作品の都合で動いている印象が皆無だ。それは、高梨がヒロインの芯と骨格をしっかり作り上げているからだろう。