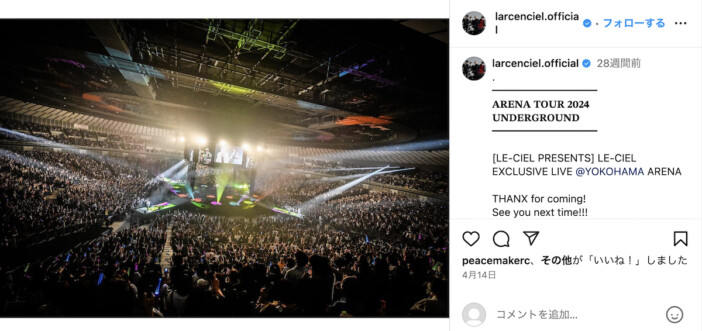L'Arc-en-Cielの根底にある“美”の正体 識者3名がモンスターバンドの魅力を語り尽くす

インディーズ時代から根底にある“美意識”

ーーみなさんがL'Arc-en-Cielのすごさに触れたきっかけ、当時の印象について教えてください。
東條:出会いは1993年にリリースされたアルバム『DUNE』のインタビューでした。最初は「女の子がいるの?」っていう印象でした(笑)。とくにhydeさんは髪の毛も長く、ステージでも白いワンピースのような衣装を着ていて、まるで中森明菜みたいで。でも見た目やパフォーマンス以上に衝撃的だったのは、kenさんが書いた「White Feathers」という曲。黒い衣装を着てダークな曲を歌っているバンドは当時たくさんいたけど、この曲を聴いて「白い曲を書くバンドが出てきたぞ!」と衝撃を受けました。ライヴでは空から白い羽がぶわーっと降る演出もあって、こんな天国みたいなところに連れて行ってくれるバンドがいるんだというのが最大の驚きでしたね。
後藤:私はいわゆるL'Arc-en-Ciel世代なので。中学生のころにテレビで「flower」のMVを見てハマり、その後の3枚同時シングルや2枚同時アルバムリリースなどを夢中で追いかけていました。音楽とは何かもよくわからないまま、ものすごくクオリティの高いものをキャーキャー言いながら聴いていたと思います。バンドと言えば楽曲も歌詞もアートワークもあれくらい作り込まれているものだと思っていたら、L'Arc-en-Cielが特別にすごかっただけなんだと後々気づきました(笑)。今思えば、貴重な時代を体験していたと思います。
大前:私は世の中に流れているヒット曲として耳にすることはたくさんありましたが、深く知るようになったのは仕事がきっかけです。出会いは2004年に公開されたhydeさん出演の映画『下弦の月~ラスト·クォーター』のインタビューで、L'Arc-en-Cielとして仕事で携わったのは、『TOUR 2008 L'7 ~Trans ASIA via PARIS~』のライヴ レポートを書かせてもらったのが初めてでした。船の演出を始めとした壮大な舞台装置の上に美しいメンバーたちがいて、非常にドラマチックな楽曲たちを演奏していて、フィクションじゃなく現実でこれを表現できる人たちが他にいるだろうかと思うほど圧倒的な美だったんですよね。それから1990年代の作品とかも遡って聴いていくうちに、本当にすごい曲を作るバンドなんだなと知りました。


ーーこれまでのL'Arc-en-Cielのキャリアの中で、みなさんが印象に残っている作品やライヴを教えてください。
東條:忘れられないのは、やっぱり『1999 GRAND CROSS TOUR』と『20th L'Anniversary LIVE』の味の素スタジアムですね。『1999 GRAND CROSS TOUR』は、一体どれくらい制作費がかかっているんだろうと思ってしまうほど、とにかく壮大なセットを野外に打ち立てたんです。野外ライヴを積極的にやらなかった彼らが、こんなにどデカい場所でやっていること自体がすごかった。L'Arc-en-Cielの空に抜けていくような気持ちいい曲たちを、夜空を見ながら聴いて解放感を味わう楽しさも感じられたライヴでした。20周年の味スタは、豪雨の中でカッパを着ながらライヴを見て、メンバーたちもびしょぬれになりながらパフォーマンスしたんですよね。2日間でL'Arc-en-Cielの歴史を全て見せるという壮大で感動的なライヴだったんですが、お互いにずぶ濡れになりながら一つになっていく光景は今でも忘れられないです。
後藤:私は『AWAKE TOUR 2005』です。テーマが反戦や平和への願いで、生身のダンサーやパフォーマーも出演する演劇のようなライヴだったんですよね。ラストの曲が「星空」なんですが、曲中に一回暗くなって、最後のサビでステージが明るくなったらお花畑になっていたんですよ。その光景があまりに美しくて、ボロボロ泣きました(笑)。自分の中でライヴというものの概念が変わった瞬間でしたね。ここまでメッセージ性があるライヴはL'Arc-en-Cielの中で珍しいほうだと思うんですが、絶頂を極めてなお彼らが挑戦的なテーマを持って、華やかなだけではないライヴを作り上げたということがすごく印象に残っています。
大前:『30th L'Anniversary LIVE』で「星空」をアリーナにせり出したサブステージで披露したときは、お客さんの灯すライトがまさに星空みたいでしたよね。この時期の世界情勢から、傷ついた人に寄り添う気持ちがあったと思うんですが、MCで明確に言葉にするのではなく、“目が覚めたら平和な世の中になっていたらいいな”というようなお話をさりげなくしていました。こうやって一人ひとりが幸せであろうと思いながら生きていくことが、この美しい光景に繋がっていて、これを守るためには平和でなくてはいけない。そのことを、彼らは反戦の旗をあげるのではなく、こういうふうにライヴで表現するんだと、とても心を打たれました。
また、30周年はコロナ禍で声が出せない代わりに、お客さんはグッズのバットマラカスライトで思いを表現していましたよね。その色でファンの皆さんの曲に対するイメージが伝わってきたし、あの情景を見て、中断されてしまったツアーもあったけどL'Arc-en-Cielとファンの思いは繋がっていて、苦しさも乗り越えてきていたんだなと思いました。

ーーでは最後に、30年を超えてもなお、L'Arc-en-Cielがファンから愛され続ける理由はどんなところにあると思いますか?
大前:私が思う彼らの魅力は、まず4人の天才コンポーザーが集まっていること。それぞれがミリオンヒットレベルの実力を持っているバンドって他にいないですから。4人の拮抗した力の持つ天才の集合体だからこそ、一人ひとりの個性が楽曲のバリエーションに繋がっていると思います。
そして、hydeさんの作詞もすごいですよね。時代を重ねても古くなるワードが入っていないので、30年前の曲を今聴いてもかっこいいと思えるし、浮かんでくる情景は綺麗。それは世界中にファンがいる理由にも繋がっていると思います。ただ、hydeさんが抽象的な歌詞を書いているというよりは、hydeさんが言葉というツールを使って作曲者が音で立ち上げた心象風景を“翻訳”し、普遍的な曲を描き出しているイメージですね。私たちはhydeさんの歌詞をパスワードにしてL'Arc-en-Cielの曲の世界に入っていけるんです。それは言語の壁を超えるので、世界中の人が聴いて美しいと思える。さらに言えば、日本古来からある“もののあはれ”の概念(=物事に触れて感じられる、しみじみとした情趣や感動)と、ラルクの美の概念には通じるものがあるとも感じています。
東條:今回の、WOWOWのライヴ映像を見ていただいてもわかると思いますが、バンドとしての美意識が高いんですよね。きちんとルックスも整えて、楽曲の美しい世界観を壊さない意識がメンバーの中にあると思うので、ヴィジュアルを含めてのクオリティが落ちない理由の一つは、そこにあるんじゃないかなと思います。年を重ねても「渋くなったね!」じゃなくて、「かっこいい~! 美しい~!」って今でも心から言えますから。だからこそ曲に浸れるんですよね。
後藤:L'Arc-en-Cielのクオリティを彼ら自身がずっと維持してくれているというのは同感ですね。ずっと見上げさせてくれていて、地に降りてこないというか。ファンのみんなと一緒にいるよという気持ちはあると思うけど、肩を組んで一緒に歩いて行くというよりは、ずっと夢を見させてくれる存在なんです。キャリアを重ねると、間口が広がって少しずつファンとの距離が近づくバンドも魅力的ですが、彼らはいい意味で一定の距離を保っていて、歌詞やライヴの表現においても俗世に寄り過ぎず、気高い存在でい続けている。そこが唯一無二の魅力なんじゃないかなと思います。
※1 https://natalie.mu/music/pp/larcenciel03
■番組情報
『L'Arc-en-Ciel LIVE 2025 hyde BIRTHDAY CELEBRATION -hyde誕生祭-』
5月13日(火)午後6:00~
WOWOW ライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信
※放送&配信終了後~WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり