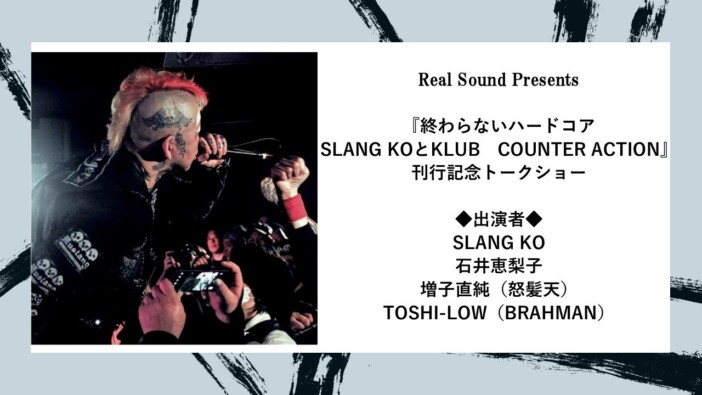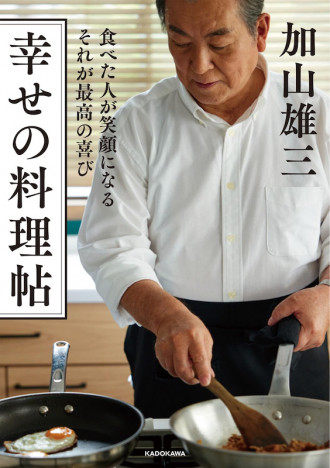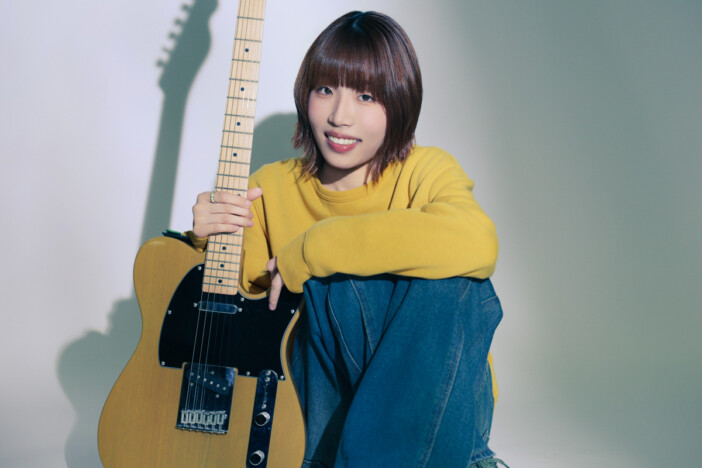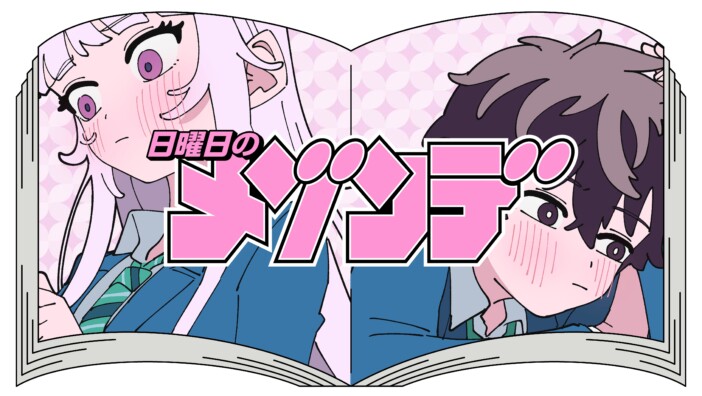BRAHMAN TOSHI-LOWはなぜ死生観と向き合い続けるのか “終わり”を受け入れ力強く前進する結成30周年

バンド結成30周年イヤーに突入したBRAHMANが、7thアルバム『viraha』を2月26日にリリースする。本作は、『梵唄』以来約7年ぶりのフルアルバム。4時間に及んだ伝説のワンマンライブ『六梵全書』(2024年11月4日横浜BUNTAI)にてアルバム6作品分、75曲の披露を終えた後、最後の1曲としてMVがサプライズ公開された新曲「順風満帆」を始め、全11曲が収録されている。
アルバムタイトルの『viraha』は、ヒンディー語で“離れたことで初めて気づく相手の大切さ”という意味を持つ言葉だ。BRAHMANとして歩み始める直前から今まで数々の仲間の死と直面してきたTOSHI-LOW(Vo)。これまで残されてきた「旅路の果て」などの楽曲と同様に、2月7日に先行配信された収録曲「charon」にも、そういった影響が色濃く反映されている。年齢やキャリアを重ねていくということは、同時に“終わり”へと向かっていくということ。しかし、そういった現実を見つめることが、『viraha』というアルバムに込められた前へと向かうパワーの根源となっている。
今回のインタビューでは、TOSHI-LOWにアルバム全体像や「charon」の話を起点に、自らの死生観、バンドの現在、そしてこれからについて赤裸々に語ってもらった。(編集部)
「簡単にできるから、みたいなものに俺らが思う“良いもの”はない」
──『六梵全書』、4時間で75曲、本当にお疲れ様でした。今回のアルバムはあのライブをやる前に大体は完成していたんでしょうか?
TOSHI-LOW:ほぼほぼできてたよ。
──30周年を迎えて、今BRAHMANがいる地点が、このアルバムに示されている?
TOSHI-LOW:ずっと、「今」でしかないと思っているから。それが高みにいるのか下にいるのか、はたまた違う次元にいるのか、自分たちではわからないけど、そこにいるということに関しては突き詰めているかな。
──今回のアルバムの楽曲は大体どれくらいのタームで書かれているんですか?
TOSHI-LOW:コロナ禍にちょこっと作ったのがあって。
──「Slow Dance」がそうですね。
TOSHI-LOW:でもほとんどはここ一年、二年で書いた曲かな。
──前のアルバムから7年経って。自分の中でこういう部分の意識が変わってきたとか。周りの状況で変化があったとか。そういうのは何かありましたか。
TOSHI-LOW:常に変わるもん。一緒に演ってくれる人も変わるし、状況も変わっている。でもフィジカルな表現が好きというのは変わらない。ハードコアパンクとか、肉体をもってやる音楽が、まだやっぱり好きなんだろうなというのはあるよ。
──今回のアルバムは非常にハードコア色が強く、ラウドで激しい曲が多いですね。自分たちの肉体性、肉体を使った表現に対する執着みたいなものを改めて認識した?
TOSHI-LOW:執着なのかな。そもそもそこでしか考えていないんじゃないかな……。精神性から広がっていくスピリチュアルとかそういうものではないと思っているし。無限に広がっていく電子音楽みたいなもので自分たちを表現しようとか思わないしね。どちらかというと4つしかない音色の中で、ライブハウスで再現できる表現っていう縛りは、結成当時からあると思っているし。
──揺るがずにある。
TOSHI-LOW:あるよね。ただ、違う鳴りを求める時もあるから、そういう時は、前のアルバムだけど、管楽器を入れてもらったりとか。俺以外の人の声もね。そういうのもあるけど。根本的にバンドのフォーメーションを変えるものではないと思ってる。
──今まで、根本的な部分を広げていこうという意識に向いた時期はあったんでしょうか? いろいろな音楽を取り入れてみようとか。
TOSHI-LOW:あると思うんだよね。自分たちの知っているもの以外からインスピレーションを受けてとか。でも結局、翻訳しないといけない。例えばピアノが入っている音楽に感銘を受けたとしても、じゃあピアノを入れてこうしようっていう考えにはならない。その旋律をどうやってギターとベースで置き換えるか、みたいな。ずっと翻訳してやってきたし。それは民族音楽に関してもそうで。例えば不思議な中近東の音が鳴っているようなものを、どうしたらギターでできるのかなとか、歌の訛りみたいなものでできるのかとか。だからあくまでもインスピレーションをもらうだけで、音楽を移植しようという考えはたぶん一回もないかもしれない。
──今回、インスピレーション源になったようなものって具体的にあるんでしょうか?
TOSHI-LOW:どうだろう。メロディというよりは世界各地におけるリズムというか。そういうものの方に耳が行っていた気がする。
──日本の民謡とか音頭とか、盆踊りに通じるリズムも感じました。
TOSHI-LOW:トルコとか中近東みたいなリズムがかっこいいなと思って、そういうものをやっていたら結局、和モノになっていくの。それが自分たちのDNAなのか何なのか。シルクロードを戻ってしまうというか。西洋音階以外のバンドも、フジロックに行くと多いじゃん。ああいうスケール感も大好きで。土着な感じというか。それを聴いて取り入れようとすると和モノになっていくというか。
──今回はそういう土着的なリズムを取り入れながらも、すごくストレートなロックもやっている。象徴的だったのはMotörheadのカバー「Ace Of Spades」ですね。資料に何も書いてなかったから、音を聴いてびっくりしました。
TOSHI-LOW:「Motörheadやってる!」って思うじゃん。すごいドンズバやってるなと思ったら後半のアレンジで「は?!」っていう感じを出したかったんだよね。もともとイカれている曲を、もっとイカれたものにしようとしたらああなったというか。「狂った祭り」みたいな。前半は世界中にあるMotörheadのカバーとそこまで変わらないと思うの。だから後半に向けてどうなっていくか、変化をつけるか。
──あの曲を選んだ理由は何かあったんでしょうか。
TOSHI-LOW:フジロックで改めて歌う機会があって(池畑潤二率いるROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA)。歌詞を読んだらめちゃめちゃかっこよくて。イカれてるなぁと思って。みんなに愛されている理由が、端々の歌詞に感じられて、かっこいいなって。
──あの歌詞は一応、ギャンブルのことを歌っているみたいですけど、どういう風に解釈したんでしょうか?
TOSHI-LOW:あのギャンブルが勝っているようには俺は聞こえないんだよね。「俺の手にあるのはスペードのエースで、お前の負けだ」っていう歌だけど、本当はそうではない気がする。どちらかというとギャンブル用語でいうブラフ(ハッタリ)っていう、そういうものなんだけど、そこに対して一ミリの恐れもない。負けていたとしても、突っ張り通すかっこよさ。そういうイカれ方に聞こえるというか。
──それがTOSHI-LOWさんの生き方に重なる。
TOSHI-LOW:そう生きている人たちはやっぱりかっこいいじゃん。勝てるから勝ちに行くのではなくて。どんな手であろうが、どうなろうが勝負に行くっていう姿勢。ギャンブルってイカれてるな、でも人生ってそもそもイカれてると思うし。ギャンブルをしなくてもギャンブル的なものはいっぱいあると思うし。そんな人生を賭けるような歌に聞こえてしまって。
──俺はリスクを恐れない生き方をしているんだぜ、という。
TOSHI-LOW:もし自分で何かを取捨選択していくんだったら、この歌のように生きたいというか。俺だって、音楽ができるから、得意だから、素質があるからって音楽をやっているんじゃないから。
──勝ち目があるから音楽をやっているわけではない。
TOSHI-LOW:ではない。本当にそう。自分でケツを叩いて「やってやる!」っていう感じでやるのがかっこいい生き方だなと思うし。今回のアルバム全体に関しても、「こういうのも良いけど、こういうのも良いよね」っていうような曖昧な感じではなくて。「良いものはこれだ!」っていうのはある。はっきり言えば、この曲の反対側が良いと思っている人に好きになってもらわなくても構わないというか。
──反対側にいる人。
TOSHI-LOW:リスクを選べない人。レミー(Motörheadのリーダー)じゃない側の人たちに、この曲の良さをわかってほしいとは思っていない(笑)。

──30年間常にリスクを背負ってギリギリの淵に立ってやっている。
TOSHI-LOW:ギリギリの淵……かどうかはわからないけど。良いものってギリギリを狙っていかないと出ないと思っているから。この間の『六梵全書』もそう。「できるからやる」んじゃない。できるかできないかみたいなところをやり切ったから。でもそうじゃない人もいる。簡単にできるから、上手にできるから、100%再現できるからやります、みたいなものに俺らが思う「良いもの」はない。だから常に自分たちの中で新しいものだったり変化なりを求めてきたと思うし。
──そういう意味で今回、自分たちに課したものとは何でしょうか?
TOSHI-LOW:より、個人として向き合うことじゃないかな。
──何に?
TOSHI-LOW:バンドでも、音楽でも。それは人間や人生でもいいし。コロナっていう100年に何回っていう疫病が来て、自然災害も常に襲ってくる。その中でみんなで何かというよりは、個としてどう生きるかが問われてくる。バンドは集団なんだけど4人の個の集まりだと思っているから。各パートがそれぞれ強く表現できないと。お前が弱いからここカバーするね、みたいな感じのバンドだと強い表現にならない。
──もたれあっていてはね。
TOSHI-LOW:今まではあったの。俺はシンガーとしてはダメだけどバンドとしてはOKみたいな逃げが。そういうのじゃ今回のアルバムは表現できなかったから。各メンバーも、自分のパートとしっかり向き合った何年間だったんじゃないかなと。
──向き合ったというのは具体的にはどういう?
TOSHI-LOW:練習するとか、楽器の特性を知るとかね。今まで勢いでやっちゃっていたのをちゃんとした理論をもって、ここをこう押さえるんだみたいな。一個一個すべて。
──TOSHI-LOWさん、以前も同じようなことを言ってましたよね。
TOSHI-LOW:おお。
──各自の修練があって、自分を高めていった結果としてこういうものができたんだ、常に自己革新しているみたいな話。BRAHMANには常にそういうものがありますよね。
TOSHI-LOW:でも、今までよりももっと強いよ。今までは、それでもパフォーマンスできちゃえばOKみたいな。そういうのではちょっとなくて。実は音楽的にみんなやったというか。
──今回は特に。
TOSHI-LOW:デカかった気がする。己が持っている独自の理論じゃなくて、普遍的な共通項として、音楽的な部分における自分のパートの位置みたいなものをちゃんと探っていた。別にこのアルバムのためだけではないけど。
──常にやっていること。
TOSHI-LOW:だから強くなれたんだと思う。ここ数年、ライブハウスだけじゃなく、ホールでやることもあって。ライブハウスなら喜ばれることも、違う角度から見られたときに耐えうる演奏やパフォーマンスかどうか、考えざるを得なかったと思うんだよね、全員。
──ちょうど3年前に中野サンプラザでライブをやりましたよね。「Slow Dance」の時のツアーだったと思いますが、着席で、普段のライブハウスとは違うライブをやった。
TOSHI-LOW:押せ押せでやれないハコだったから、静かな部分を聞かせるには、今まではゆるっとやっていたところをみんなで「ハッ」って、息を合わせないといけなかった。自分たちの曲をもう一回丁寧にやったことで、静かに聞こえるような、ミッドな感じの曲がこんなにふくよかなんだなってわかって。で、その時に、ちゃんと鳴らすとかちゃんと歌うことの大事さがわかった。今までは雰囲気を出せればOKだと思っていたのが、やっぱり旋律を追えないと自分たちが作りたかった雰囲気が出せなかったんだなと。レコーディングではできているんだよね。だけどライブにおいてはなんとなく流してしまっていた部分を、あのライブではやったの。で、ハードな部分も同じように丁寧にやったら、それはもっと良いに決まっている。
──うん、そうですね。
TOSHI-LOW:上手にやるとかBPMを合わせるとかだけじゃなくて。ハッキリとパスを出しあっていかないとチーム力が低くなるということに、何となくみんな気づいて。この何年間かはそういうことを丁寧にやった気がするかな。
──その成果が今回のアルバムでは出ている。ハードなラウドな演奏であっても、そういう意味では以前と違いますね。
TOSHI-LOW:そう思う。