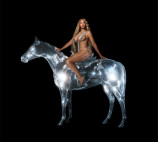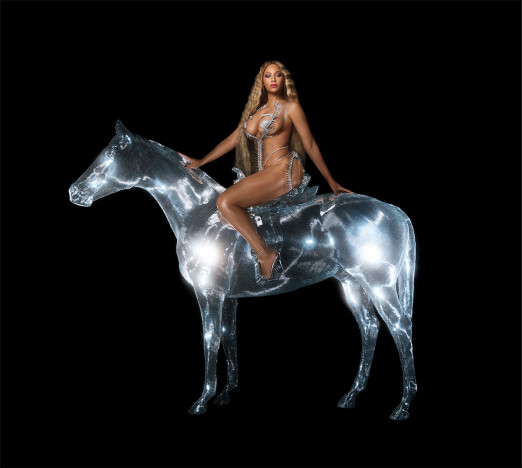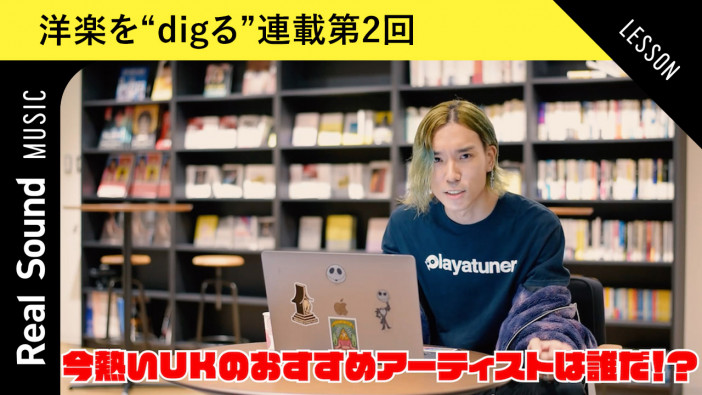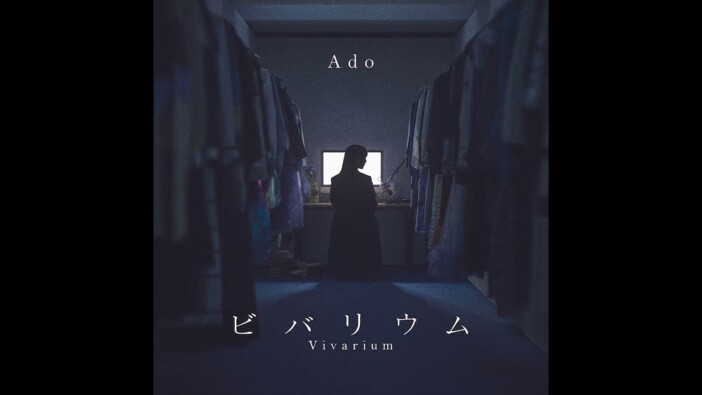“Rina Sawayama中心史観”で考える一大潮流 エルトン・ジョンとのコラボからフォロワーアーティストの登場まで
Yamato Watanabeがリスナーに促す根源的な「SELF LOVE」は、唯一のカバーにして最新リリース曲である「ハナミズキ (feat. 一青窈) [Cover]」でより緻密に模索されている。彼の楽曲を愛聴するぼくとしては、むしろRinaからの影響が感じづらいかに思えるこのナンバーを推薦したい。カバー曲として全体の構成がほんとうによく考えられている。
オリジナル版のピアノとストリングスによるメロウな掛け合いが、ボーカル(しかも英語詞!)とギターのチルな電子音に置き換わる。4拍子(あるいは2拍子)中、いいアクセントが刻まれながら、ハイハットがさりげなく囃し立て、バスドラムがすぐに主張を強くする。いきなり日本語詞に切り替わる瞬間がすごい。リリックには〈刻一刻と迫る死 時間は全然待ってくれNEZO って書いたのは俺だったのに〉とある。これは自身のヒップホップナンバー「NEZO」のフレーズを自ら引用したもの。ヒップホップ的なパターンミュージックに再構築する感性の鋭さが、このラブソングにも切実な社会性を宿す。本人による自歌解説文にはこうある。
「毎日を大切に過ごそうと思っていたのに。出来なかった。僕には出来なかった」
ここには「SELF LOVE」の“その先”が書かれている。第一に自分、第二に他者の存在に思いいたる。そんな心の動き以上に社会的なメッセージがあるだろうか。この曲がヘビロテ曲になった頃には、リスナーそれぞれの「SELF LOVE」が見つかるのではないか。「ハナミズキ」は言わば、「NEZO」からの引用を過去形(記憶)として落とし込み、現時点での集大成をカバー形式によって結実させた現在そのものであり、またそこから腰を据えてさまざまなビートとたわむれながら新境地を開いてみせようとするアーティスト本人の未来(本人の言葉では「Brand-new World」)を鮮やかに提示している。試行錯誤の過程でかすかなアフロ・ビーツを援用するあたり、J HusやStormzyなどUKラッパー勢の表現を取り込む貪欲さも見逃せない。例えば、渋谷HAREMのショットライブでライムしシャウトするエッジーなストリートスタイルは、「SELF LOVE」をよりストレートに投げかけてくる。8月19日リリースの最新ヒップホップナンバー「F.D.O.」もまた現代社会への問題提起が織り込まれ、ネット社会の“過剰摂取”に警鐘を鳴らす野心作だ。遠く故郷の日本のクラブシーンでフォロワーアーティストが頭角を現し、Rinaのサウンドが図らずもJ-HIPHOPにすら影響を及ぼすケミストリーを興味深く思う。
“Rina Sawayama中心史観”で考える一大潮流
Rina Sawayawaとはつまり、台風の目のような存在ではないのか。Rinaの周囲をぐるぐる回る綺羅星のようなアーティストたちが激風を吹き荒らしている。例えば日系アメリカ人のMitski Miyawakiや88rising所属で全米チャートを賑わせる猛者のオーストラリア系日本人・Jojiなど先行アーティストたちも、今や“ハリケーンRina旋風”の真っ只中にいる気がする。インディーズ界隈で活躍するMitski、謎めいたイメージを醸し出すJojiに対してRinaのアリーナポップスター的なスケール感は圧倒的でもある。
年少ながらUKではすでにポップスターの称号をほしいままにしているデュア・リパとの比較も欠かせない。デュア・リパ自身はロンドン生まれながら、両親の故郷・コソボからの移住経験があり、自らのルーツを追体験しながら男女差別に果敢に取り組む。エルトン・ジョン『The Lockdown Sessions』では、2020年代仕様のリミックス「Cold Heart (PNAU Remix)」を収録し、Rinaとはアルバムメイトでもある。世界的な知名度ではデュア・リパに軍配が上がるものの、(偽史的ではあるが)“Rina Sawayama中心史観”によって新たな音楽地図を描くというダイナミックな見立ても面白いのではないだろうか。
ポップアイコンの範疇にはおさまりきらないRinaの闘志と革新性を考える上では、英国レコード産業協会が主催する音楽賞をめぐる変革を思い出してもいい。国籍基準が設けられているブリット・アワーズとマーキュリー賞に、英国在住で日本国籍のRinaがノミニーにならなかったことから協会と根気強い対話が続けられた。エルトンからの援護射撃を受け選考基準変更をもぎ取った功績は画期的だった。今年のブリット・アワーズで女性グループとして初めてFLOがライジング・スター賞を受賞したのもRinaによる変革あってこその快挙と考えることもできる。デビューシングル「Cardboard Box」(2022年)は、女性の気高さをリリックに込めた社会的メッセージ性に満ち、Rinaフォロワー的アティチュードの片鱗を見出せる。UKに限らず世界の音楽シーンのいたるところで、血縁や人種によらないRina Sawayamaフォロワーアーティストが一大潮流になるのではないかとぼくはひそかに思っている。
連載「lit!」第30回:ハウスやレゲトンの活況、ビッグネームの新作リリース……2022年グローバルポップの動向を総括
今回第30回目となる連載「lit!」では、この2022年という激動の1年におけるグローバルポップの動向の総括を試みたい。当然なが…
エルトン・ジョン、60年以上にわたって成し遂げ続けてきた偉業の数々 イギリス最終公演となったグラストンベリーも振り返る
歴代最高の興行収入でツアー活動を引退したエルトン・ジョン。1962年にバンド活動を、その5年後にソロ活動を開始した彼は、60年以…