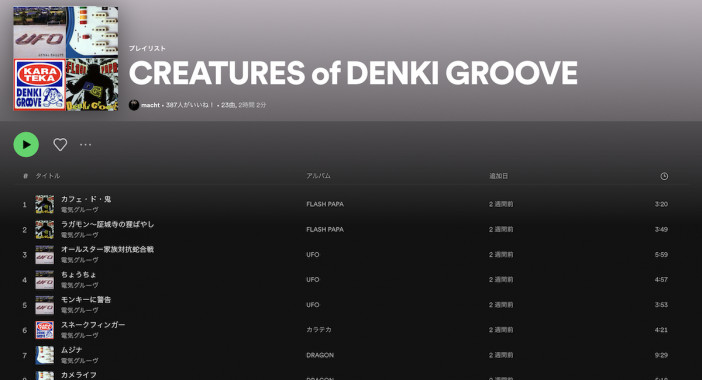スピッツが届けるノスタルジーではない煌めき “二人だけの国”を飛び出し、万人に開かれた草野マサムネの言葉
ノスタルジーは美しいけれど残酷なほど人を選ぶ。それは若きスピッツの曲を聴くたびに思うことだ。煌めきをちりばめたギター、軽やかで爽やかなドラミング、憂鬱がほんのり滲むベース、草野マサムネ(Vo/Gt)のピュアで繊細な声……そのあまりにも少年性に富んでいて神秘的な音楽は“僕”と“君”以外は介入できない閉塞的な世界を作り上げていた。だからこそ、青春時代に純粋に愛し愛された経験のある人にとっては琴線に触れる特別なものになってるのだろうし、学生時代からすでに大きく踏み外してしまった私みたいな人間からすれば嫉妬の対象でもある。だってどれだけ目を凝らしても、手を伸ばしても、私にはわからない。
「行き詰まった気持ちから解放され、悲しみや切なさが癒されたリスナーは数え切れないくらいいるだろう」とApple Musicにはスピッツのことが書かれているけれど、本当にその通りだと思う。きっと“僕”も“君”もこの世にはたくさんいるはずだから。でも私はあの頃のスピッツを聴くとき、その“側(がわ)”にいる第三者について考えてしまう。
“僕”と“君”/“それ以外”という明確な隔たり。草野マサムネによるあまりに美しく特別な愛の言葉を目の前にして、強い欲望が蠢かないわけがないのだけれど、“それ以外”になってしまえばどれだけ手を伸ばしたって触れることはできない。そういう第三者が見えてくるからこそスピッツの音楽は余計に切なく響く。〈誰も触われない 二人だけの国〉(「ロビンソン」)なんて口ずさむときヤケに複雑な感情になるのもそのせいだ。
とまあ少々歪な聴き方である気もするけど、そんな自意識のようなものが働いてしまうところにかつてのスピッツの魅力があると私は思う。だって他のアーティストでこんな感情になることはほとんどない(あるとすれば小沢健二かもしれない)。
でも、なぜ執拗に“かつて”とか“あの頃”とか過去形にするのかといえば、ここ数年のスピッツは目を向ける先が明らかに変わっているからだ。大きな扉が開いて、誰もがスピッツの世界に出入りできるような、そういう風通しの良さがある。
「醒めない」を聴いたときに初めて思った。ロックを初めて聴いた少年期の衝撃と興奮を真空パックさせたようなあの曲には、現在進行形の彼らの高揚があったし、もはやそれは生そのものへの祝福だった。軽快なビートと管楽器の音色が、この社会を生き抜いてきた全ての人を労ってるかのごとく高らかに響く。このとき、私は初めてスピッツの世界に触れられた気がした。
それからずっとその扉は開いていて、今では誰もがスピッツの魔法にかかることができる。最新作『ひみつスタジオ』も、もちろんそう。