【浜田麻里 40周年インタビュー】第3弾:初のレーベル移籍&長年にわたるライブ活動休止に至った背景とは? 世界的な活動の裏で抱えた“理想の環境とのギャップ”
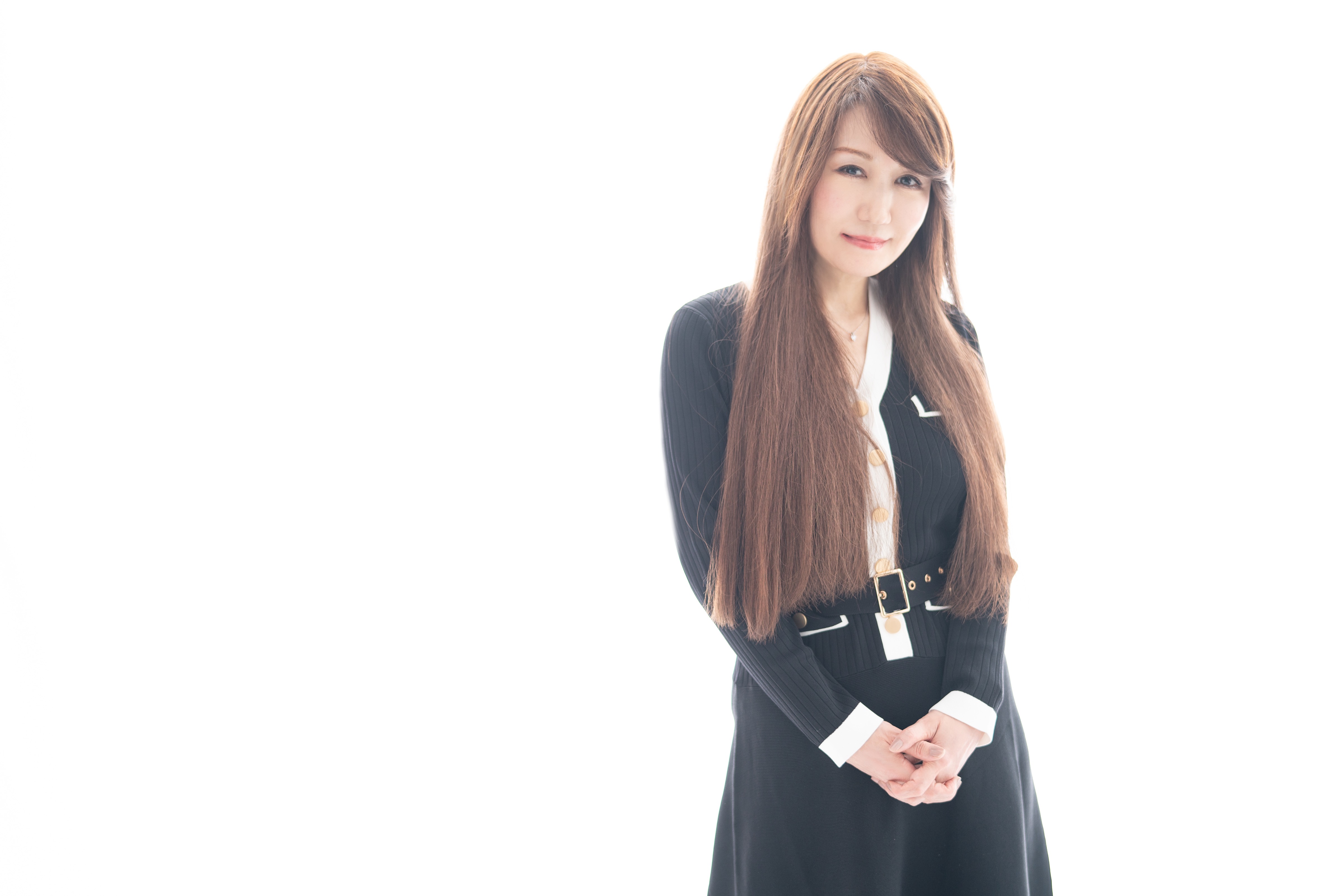
「かけ離れたイメージを持たれないため、日々が究極の選択に」
――当時の日本の音楽市場、あるいはロックシーンは、麻里さんにはどのように映っていたんでしょう? 世の中的にはバンドブームと呼ばれる現象もあった時期です。
浜田:当時の詳細まではわからなかったです。記憶もないんですよね。『IN THE PRECIOUS AGE』(1987年)の頃からは日本にいない期間がすごく長くなっていましたし、コンサートツアーも長いものでしたので。当時の日本のバンド事情なんて考える暇もなかったですし、正直に言うと、元から興味もないんです。バンドブームですか……全然実感はないですね。そういえば、『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』(日本テレビ系)で、まだアマチュアの頃のX(後のX JAPAN)が「早朝ヘビメタ」とかって、寝ている人のところに行って急にハードな演奏をするという企画をやって話題になってましたよね。私にはあの番組から「失恋ヘヴィメタル」でライブをやってくれという熱心な依頼があったんですよ(笑)。
――失恋ヘヴィメタル(笑)?
浜田:そう(笑)。その頃の私は一般にはだいぶポップになったねと言われて、歌番組などにも出ていましたけど、自分の中ではどこかで一線を引いていて、バラエティ番組には出ませんでしたし、気持ちはストイックなままでした。番組の企画内容は、失恋したばかりの人たちをお客さんとして、海岸に設置された会場に集めて、私のライブで号泣しながらヘッドバンギングさせるという(笑)。確かに企画としてはテレビ的に面白い映像が想像できますし、お笑いとしての場面も浮かびます。もし私が視聴者だったら、きっとプッと笑ったと思います。なぜそれを覚えているかというと、私以外のスタッフ全員、出てほしいわけですよ。視聴率がすごくいいゴールデンタイムの人気番組だから。そんな中、だんだん自分に対するスタッフの考え方に疑問を感じるようになってきていて。一つ仕事の選び方を変えると、まったく違う未来に繋がってしまう。本人とはかけ離れたイメージを持たれてしまう。日々がそういう究極の選択になりました。だから、いまだに頑固だとか怖いとかって言われてるんでしょうけど、そういうことを一切やらずにきたのが自分なんですね。それこそ今もアルバムが出るたびに、「こういうテレビ番組はどうでしょうか?」といった話は必ずあるわけですけど、視聴率がすごく高い人気番組からのオファーだったとしても、ほぼやっていないんです。お声掛けいただけるのは光栄で、とても嬉しいと思う反面、お受けできない自分もおります。スタッフですら「こんな番組を断るんですか!?」みたいな感じだと思います。
――それこそ昔は音楽番組であっても、ロックミュージシャンはテレビに出ない時代がありましたよね。前回もその件を伺いましたが、麻里さんの場合、出演する/しないの基準はどこだったんですか?
浜田:自分はロックの世界の人たちはテレビに出ちゃいけないみたいな風潮を壊したと思ってるんですね。本当に短い時間だから、それを実感してくれる人はかなり少ないんですけど、だからこそ、自分はそういう中で出演することを当時は選んだんです。やっぱり何かを起こしたい気持ちがすごく強くて。ただ、歌番組に出ることが普通になってくると、誰もがそれをやり出すわけですよね。観てくださる視聴者の皆さんにとっても、私をテレビで観ることが驚きでもなんでもなくなる。そうなると、私はもう違うところに行きたくなる。その流れですね。
「“浜田麻里はヘヴィメタル”と言われてるけど、最初はアイドルだったんだよね」みたいなことをよく書かれるんですけど、アイドル活動をしたことは一度もないんですね。それこそバラエティ番組に括られるものだとしても、ライブがついてくるような深夜帯の番組でしたし。ライブがないもので言えば、たぶん『笑っていいとも!』(フジテレビ系)の「テレフォンショッキング」と、久米(宏)さん時代の『ニュースステーション』(テレビ朝日系/現『報道ステーション』)くらいです。昔から音楽と離れた活動はしたこともないし、ピンナップみたいなものはあったにしろ、自分があえてそれをやりたかったということもなく。
――ヘヴィメタル界のアイドルみたいな言われ方はあったと思いますが、当時は今以上にシーンが男性社会であり、女性は目立つ存在だったという程度の話ですからね。
浜田:そうですね。時代の風潮というのは恐ろしいもので、その時代の常識みたいなものと全然違う見解を堂々と言ったところで、何も理解されないような空気感ってあるじゃないですか。時代を経てからでないと気がつかない空気感です。そういう中で、本当は違うんだけど、もういいやと思って「そうなんです」なんて流したほうがいい場面っていうのはたくさんあって……昔のインタビュー映像で、「今、アイドルと言われてどうですか?」という質問をされて、「あ、嬉しいですね」みたいな感じで答えてたりするものがあるんですよね。半分ちょっとキレた顔をしてるんですけど(笑)。それを撮ったのは、松本孝弘さんの弟さんで、当時は家族ぐるみで仲が良かったんですけど、身内みたいな立場の人ですら、そういう感じでしたからね。逆に、90年代のインタビューで、「デビュー当時の売れない頃と比べて今はどうですか?」という女性インタビュアーの質問に対して、「いや、初期もそれなりにファンの方々がいて、そこそこ成功してましたよ」と答えたら、「ははは。ご自分でそう思われているなら、それでいいですけど」とか平気で鼻で笑われることもありました。時代感というのはそういう空気のことで、この仕事を続ける自分のメンタルを守る意味では、かなり強靭でいないと務まらないんですよね。生放送の歌番組で、演奏直前の歌の前振りのときに、黒柳徹子さんに「脱・ヘヴィメタル宣言!」と叫ばれてしまったこともありますしね。もちろん宣言したことはありません(笑)。
――(笑)。
浜田:またちょっと脱線しましたけど、だんだんに次のフェーズのことを考えてはいたと思います。『TOMORROW』のときは、自分の印象として、やっぱり新しい会社だったし、当時、新卒の若い宣伝チームが凄いパワーだったんですね。「Precious Summer」が『熱闘甲子園』(テレビ朝日系)のタイアップになったりしたこともヒットした要因の一つだとは思いますけど、彼らがすごく頑張って、いろんなところに音源を持っていってくれたりなど、地道なプロモーションの努力が、あの時分の成功には結びついていたと思います。嬉しかったですね。
――『TOMORROW』には今もすごく人気の高い「Paradox」も収録されていますよね。
浜田:そうですね。「Nostalgia」で増崎(孝司)くんのマイナー路線の曲が一つの自分の色になって、その流れで作った「Paradox」が今も人気曲として残ってるんですよね。それから、『TOMORROW』のときはツアーがとても楽しくて。少し抑えて50本弱ぐらいだったかな。満足度の高いツアーができて、それもよかったと思います。それが後に完全崩壊するわけなんですけど(笑)、そのときは本当にいいツアーができた実感がありましたね。バンド全体の結束力も強く、少しでもいいものにしようというやり取りも積極的でしたし、それがお客さんにも伝わったのだと思います。お客さんも楽しそうでした。
――「Precious Summer」の作曲は織田哲郎さんですよね。これはどういう流れなんですか? つまり、ビーイング系人脈だということです。
浜田:そう。織田さんとはデビュー前から面識があったので、特別すごく売れてる作曲家の方にお願いした感覚はなかったんですよ。たぶん、北島(健二)さん以上に織田さんのほうが、事務所関係のパーティとかでお目にかかる機会は多かったような気はしますね。織田さんが持っていらした音楽番組に出たりしたこともあったと思います。実はMCAビクターのサブのA&Rの方が、織田さんと麻雀をする間柄で(笑)、そのときに「浜田麻里の曲を書きませんか?」「ああいいよ、いいよ」みたいなやり取りがあって、実現したんですよ。ちょうど『熱闘甲子園』のタイアップ依頼があったときで、いいタイミングだなと思ったんです。自分で言うのもアレですけれども、ビーイングとしては私が成功すれば成功するほど、可愛さ余って憎さ百倍みたいになっていたところがあったので、クレームは来ましたね(笑)。






















