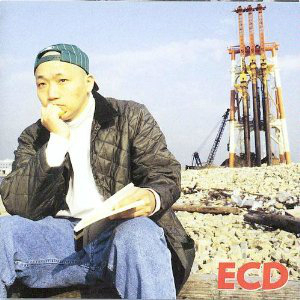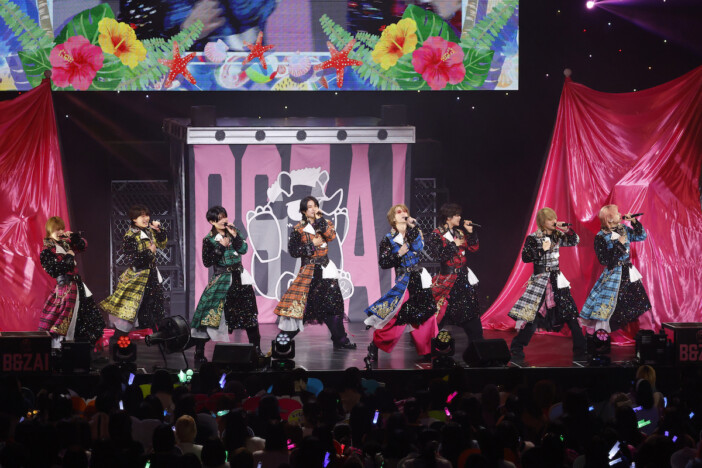荏開津広が内田裕也の功績を振り返る
内田裕也のロックとは何だったのか? 「シェキナベイベー」ディコンストラクション
しかし、ロックの巡礼者たる内田ゆえにその巡礼遍歴の限界は見えなかった。彼の予想より遥かに早く、グローバルで左翼的な理想主義を掲げたティーンたちのロックは終わっていったのだ。内田裕也への追悼として、ポピュラー音楽研究家の増田聡氏がTwitterで的確に述べていたように、『日本語ロック論争』は日本語ロックの可否を論じたものではない。イデオロギーについての、時代の趨勢を左右する考えについての論争である。そして増田氏が以前、その著書 『聴衆をつくるーー音楽批評の解体文法』(青土社/2006年)でも触れていたように、論争ののちの時代、内田が熱望して思い描いていたようなロックは結局、日本では起こらなかった。
1970年代半ば以降、日本では“産業ロック”、英語圏では“アリーナロック”、“コーポレートロック”と呼ばれる種類のバンドが全盛期を迎えていた。商業的な成功、つまり集客力を誇りながら、内田と同世代で”ロックンロール”していたのは、『Love You Live』、『Some Girls』、『Emotional Rescue』といった作品群で、新しいテクノロジーを使いこなしながら自分たちの出発点であるリズム&ブルースを巧みに召喚し続けることに成功していたThe Rolling Stonesのほか、数えるほどしかいなかっただろう。同時期の内田は、ジョン・レノンが1975年に発表したアルバム『Rock'N'Roll』の方法論を踏襲したパフォーマンスを続けながら、レコーディング作品では頭脳警察のPANTAが書いた内田の代表曲「コミック雑誌なんかいらない」などの楽曲で”ロックンロールのソングライティングをアップデートしようと試みていた。
『日本語ロック論争』について、後からやって来て内田裕也を審問しようとする人々が見逃している単純な歴史的事実がある。その重要な登場人物の1人、細野晴臣がマーティン・デニーの「Fire Cracker」をシンセサイザーを使ったエレクトリック・チャンキー・ディスコとしてアレンジし、シングルを世界で400万枚売るというコンセプトでYellow Magic Orchestraを作ったことーーつまり、グローバルな共通基盤としてのダンスミュージックの実践において、最終的には英語を使ったということだ。その後、小室哲哉からSuchmosまで、ダンスを意識しながら極私的でドメスティックとされるものとグローバルな成功を求めるものとの中間に位置するアーティストはすべて英語と日本語を併用している。2010年代の終わり以降も、それはまだまだ続くだろう。
彼が1964年に歌った〈Shake it up, baby〉の日本人アクセントは、〈シェキナベイベー〉とカタカナで強調されテレビで流布されていた。ロックンローラーというより、芸能人というイメージの方が先に立つような見せ方でもあったが、そうした扱いにことさら苛立つ様子も見せなかったのは、彼が日本のシステムを熟知していたからであろう。カタカナの〈シェキナベイベー〉も、テレビという装置のなかでの異化的効果になればとの諦念に近い想いもあって、意識的に放っておいたように思えるのだ。あの頃、みんなが信仰していた”ロックンロール”が、ポップ・ミュージックにおける異化的効果だったとするならば。
内田裕也さん、安らかに。
■荏開津広
執筆/DJ/京都精華大学、立教大学非常勤講師。ポンピドゥー・センター発の映像祭オールピスト京都プログラム・ディレクター。90年代初頭より東京の黎明期のクラブ、P.PICASSO、ZOO、MIX、YELLOW、INKSTICKなどでレジデントDJを、以後主にストリート・カルチャーの領域において国内外で活動。共訳書に『サウンド・アート』(フィルムアート社、2010年)。