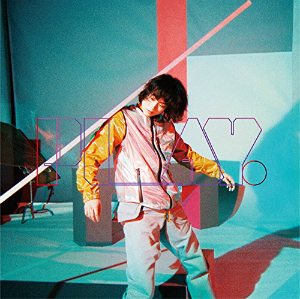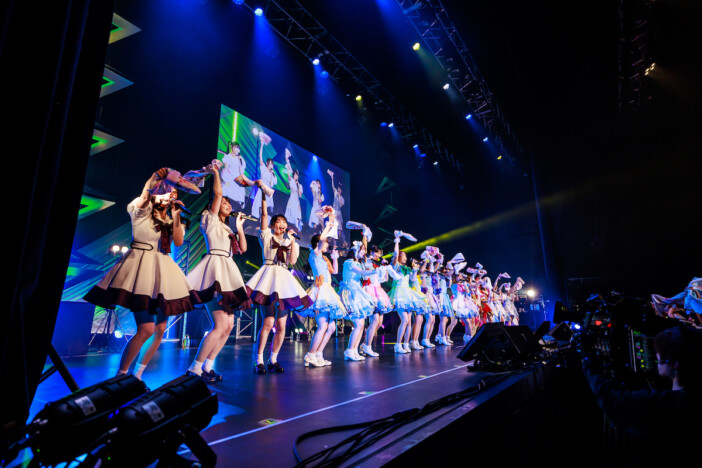レジーのJ-POP鳥瞰図 第21回
菅田将暉の音楽活動に感じる時代の空気 “偽りの自分/本当の自分”を無効化する存在に?
触発され、触発し合う『PLAY』

3月21日にリリースされた菅田将暉の1stアルバム『PLAY』。すでにリリースから1カ月近くが経ち、柴田隆浩(忘れらんねえよ)や渡辺大知(黒猫チェルシー)など、ロック畑のミュージシャンが提供した楽曲が話題を呼んでいる。
そんな作品にあってひときわ耳を引くのが、フジファブリック「茜色の夕日」の弾き語りでのカバーである。彼が音楽に関心を持つきっかけになったという曲を、アコギ一本というシンプルなフォーマットで大事そうに歌うこのテイクには、菅田将暉という人物のパーソナルな領域が描き出されている。
以前『LOVE LOVE あいしてる』(フジテレビ系)で吉田拓郎の「今日までそして明日から」を歌っていた際にも感じたが、その朴訥とした歌声と歌詞を噛み締めるような彼の歌唱法は、フォークロック的な楽曲や情景描写を大事にする歌詞との相性が非常に良い。志村正彦在籍時のフジファブリックがまさに「茜色の夕日」などでトライしていた詩情豊かな世界を明確に受け継いでいる存在はまだ現れていないように思うが、菅田将暉にはそういった表現者になり得るポテンシャルが感じられる。
ところで、筆者が最初に彼の音楽活動に目が向いたのは、2017年1月に出演した『ミュージックステーション』(テレビ朝日系)でのグリーンボーイズとしてのパフォーマンスである。映画『キセキ –あの日のソビト-』の劇中グループとしてのこの日のステージで振りまいていたスター性には目を見張るものがあった。それ以外にも映画『何者』でもバンドのボーカルを演じるなど、菅田には比較的音楽に近しい役が複数割り当てられており、それゆえ「歌手デビュー」ということにそこまでの唐突感はないと言うことも可能である。
一方で、「人気俳優が歌手デビュー」というケースは、単純な状況論でだけ言えば「CDバブル時代の遺物」といったような趣もなくはない。性別を問わず少し人気が出るとすぐにCDを出す風潮がかつてはあったし、そこから何か特別なものが生まれるでもなくフェードアウトしていく事例も多々あった。菅田将暉に関しては前述のような音楽との親和性があり、またステージ上でのオーラには目を引くものがあったとはいえ、「昔よくあった成り行き任せの音楽活動ではないか」という疑念もデビュー当時においては完全には拭いきれなかった(デビュー曲があまりにもストレートなギターロックだったことも警戒心を強めるきっかけとなった)。
ただ、どうやらこの人にはやはり何か特別なものが備わっているようである。
「僕が菅田将暉という人間に対してものすごく興味があって、どうやらその人は歌を歌うようであると。実際に弾き語りをしている映像を見ていたら、この人となら何か美しい曲が作れるんじゃないかなと思った」
「デュエットという形で一曲作ることができて(注:「灰色と青」)、ひとつ音楽家として違うところにいけたような気がした」
(3月8日放送の『NEWS ZERO』での米津玄師のコメント)
当代一流のミュージシャンである米津玄師にここまで言わせる菅田将暉の魅力の源泉、それは周囲を触発する力ではないかと思う。
この人となら、何か面白いことができるのではないか。『PLAY』に関わったクリエイターにはこんな予感が共通していたように思える。各自がポジティブなインスピレーションに沿ってそれぞれの「菅田将暉像」を描きつつ、そこに菅田が自分の色を加えていくという形で作り上げられていった作品だからこそ、完全な自作自演ではないにもかかわらず『PLAY』には菅田将暉のパーソナリティが一貫して表現されているかのような統一感がある。
強烈な存在感を持ちつつも、そこに他人の色(しかも特定のパートナーでなく、あらゆるタイプの複数の人の色)が入り込む余地がある。どちらにも寄らないバランス感覚のある佇まいは、とても現代的であると言える。最近で言えば自身でアウトプットの舵取りをしながら「チームで動いている」という意識の強い三浦大知からも同様の雰囲気を感じるが、エゴと協調性のさじ加減に時代の空気を感じる。