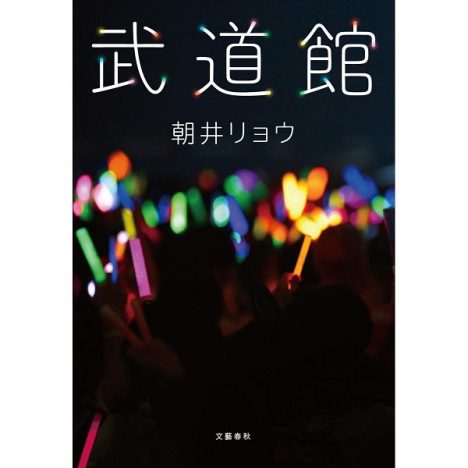香月孝史『アイドル論考・整理整頓』 第二十回:続・アイドルと『恋愛禁止』
須藤凛々花の結婚発表を機に、“アイドルの恋愛禁止”を改めて考える
もっとも、AKB48グループは「恋愛禁止」を曖昧に温存することによって生じた規範のほころびを、むしろ物語として利用しながらグループやメンバーの活性化を促してきた。HKT48の指原莉乃が、決してトリックスターでも邪道でもなく、48グループを正統に代表し最も社会から受け入れられるタレントになる契機も、おそらくは規範のほころびが物語化された時点に求めることができるだろう。そしてまた、彼女の歩んでいる道程や存在の大きさ自体が、現在あるような規範が本当に温存されるべきものなのかという問いかけにもなっている。
ただし、引いた目で見ればそれは、指原莉乃という個人の卓越したバランス感覚とタフさが事態を好転させたにすぎない。彼女の“スキャンダル”としてなされた「報道」は、一人の人格に対して非常に暴力的な性質のものであったことは忘れられるべきではない。組織が内包する規範が“スキャンダル”あるいは“物語”として機能し続けるとき、その価値観のいびつさを体現するのはメンバーたち自身である。「恋愛禁止」という規範そのものの是非とはまた異なるレベルで、もうひとつの問題はこの点だろう。
社会的に強い拒否反応を喚起する規範に関して、遵守であれ異議申し立てであれ何らかのスタンスを表明し、さまざまな反響の矢面に立つのは常に、組織全体についての決定権をもたないメンバーたちだ。もちろん、群像劇の中で彼女たちの主体性が発露していくのは、48グループの大いなる美点である。しかし、大きないびつさや理不尽さをはらむ価値観を温存したうえで、その規範の中で10代を過ごす人々に、規範自体への価値判断を託し、矢面に立たせることはとてもあやうい。この先、議論や風向きがどちらに向かうのであれ、そのことは自覚されなければならない。
「恋愛禁止」という古典的かつ錯綜しがちなテーマがとりあげられる際、その議論はアイドルというジャンルに対する感覚的な嫌悪を正当化するためになされるべきではないし、多様なアウトプットの可能性を持つこのジャンル全体を、単一のイメージで覆って否定されるべきでもない。だが、「恋愛禁止」が平和な箱庭の中で幸せに共有されているものだと思い込むこともまた、ある意味でこのジャンルを軽んじることになる。どの立場から発される言葉であれ、文化としての敬意を払ったアプローチがなされるべきだ。
■香月孝史(Twitter)
ライター。『宝塚イズム』などで執筆。著書に『「アイドル」の読み方: 混乱する「語り」を問う』(青弓社ライブラリー)がある。