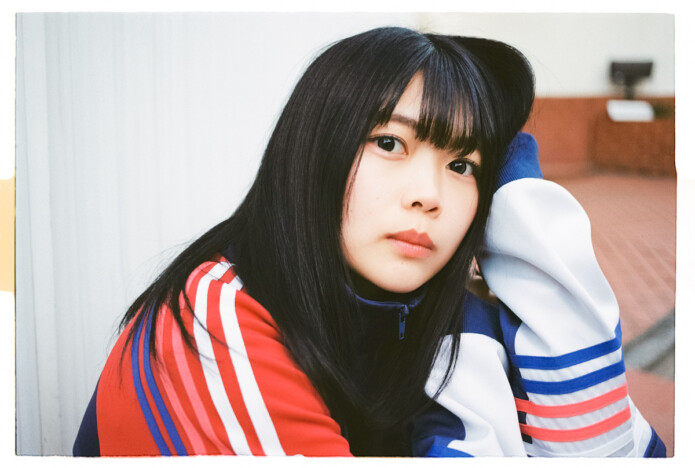石田ショーキチが語る「激動のシーン20年」(第1回)
デビュー20周年の鬼才・石田ショーキチ登場 Spiral Lifeと90年代の音楽シーンを振り返る

――新しいロックを表現していく上で、壁のようなものはありましたか。
石田:ずっと戦っていましたよ。わかりやすい例で言うと、インタビュアーの方に「日本人なんだから、日本語で歌詞を書くべきだ」と説教されたことあるんです。洋楽を聴いて育った僕たちにとって、英語の歌詞表現は当たり前のこと。そもそも表現したいことがあるからやるのに「日本人なんだからこうやれ」なんて“べき論”を言われたことに腹が立って、取材中に喧嘩になったこともあります。そういう同調圧力が、当時の音楽業界にはたくさんありました。だけどSpiral Lifeは、そういうものに対して突っ張って、自分のルーツに正直にやってきた。
今では自分の好きなことを好きなように表現するのが当たり前で、それはいいと思います。当時もそういうことを考えてきた人たちはいたんでしょうけれど、それをビジネスレベルで形にすることが得意なレコード会社は少なかったと思います。その中で(所属していた)ポリスターは、「好きなようにやりなさい」と言ってくれる特殊なメーカーだったので、僕はラッキーでした。あそこじゃなきゃできなかったと思います。
――先日、長くポリスター社長を務めた細川健さんが亡くなりました。
石田:細川さんが、(当時のレーベルプロデューサー)牧村憲一さんに好きなようにやらせてくれた。Spiral Lifeにとって、それがすごく大きかったです。牧村さんは音楽の生き字引で、日本のポピュラーミュージック史に残る、本当に偉大な方です。あの方がいなかったら、出てこなかったアーティストは山ほどいると思います。
――石田さんは95年結成のScudelia Electroでの活動も含め、プロデュースの分野でも活躍の場を広げていきます。もともとプロデューサーになりたい、という思いはあったのでしょうか。
石田:僕は18~19歳の頃からプロデューサーになりたいと思っていました。きっかけは、意外にもユーロビート(笑)。当時、第二次ディスコブームが巻き起こっていて、ディスコで掛かるヒットチューンの流れのひとつに、イギリスのストック・エイトキン・ウォーターマンというプロデューサーのチームがありました。衝撃を受けたのは、Dead Or Aliveというグループの12インチシングルのエクステンドリミックス(クラブで掛けるための長いミックス)。それまでの「リミックス」は「ミックスをもう一回やり直す」というのが当たり前でしたが、そのリミックスは、演奏をごっそり差し替えていてコード進行も全く違うものになっていたんです。それを聴いて「こんなこともしていいのか!」と。
それまではヘヴィメタ小僧だったのですが、いきなりディスコDJをやるようになって、打ち込みを始めて、ダンスミュージックにどっぷり浸かっていきました。そこからトラックメイキングやエンジニアリングという裏方的な制作の魅力に取り憑かれて、宅録するようになったんです。
――いずれはプロデュースワークをしていこうと考えていたんですね。
石田:グループとしての活動を始める以前に、寺田康彦さんなどと組んでプロデュースを始めていましたからね。Scudelia Electroは、もともとプロデュースチームとして始動していたところがあります。まんまストック・エイトキン・ウォーターマンのような構造がほしかったんです(笑)。
――そんな中、Spiral Lifeは96年に解散。デビューから3年、ファンとしては「もっとやってほしかった」と思います。
石田:僕らとしては3作でやり尽くしたところはありました。僕にとっては世の中に出るきっかけになったし、車谷くんとしてはそれ以前のキャリアをリセットして、音楽的な立ち位置を再構築したかった、というのもあったと思う。ある意味ではお互いを利用し合ったということで、それが思惑通りにすごく機能した。だから、「もういいんじゃないか」ということで別れることになったんです。
第2回:「2004年頃、時代が変わった」石田ショーキチが語る、音楽ビジネスの苦境とその打開策
(撮影=金子山 取材・文=神谷弘一)