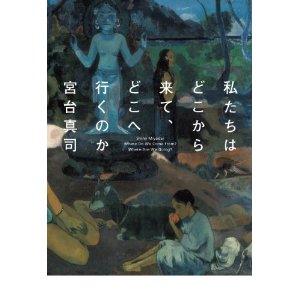メジャーデビューシングル『帰り道』インタビュー
anderlustが小林武史と目指す“枠にとらわれない”ポップス「懐かしいけど新しい感覚を」

男女ユニット・anderlustが3月30日、シングル『帰り道』でメジャーデビューを果たした。同ユニットは、女性ファッション雑誌『NYLON JAPAN』と<Sony Music>によって2014年に開催されたオーディション『JAM』のミュージック・パフォーマンス部門でNYLON賞を受賞したシンガーソングライター・越野アンナと、ベーシスト・西塚真吾によるもので、小林武史がプロデュース・楽曲制作に全面協力している。映画『あやしい彼女』の主題歌でもある表題曲を含む同シングルは、90年代後半から2000年代のJ-POP的な親しみやすさと、海外育ちの越野が持つ洋楽的なエッセンスを巧みにミックスさせた作品に仕上がっている。今回、リアルサウンドでは2人にインタビューを行ない、それぞれの音楽的ルーツや彼らの目指す“枠にとらわれない新しい形の音楽表現”について、存分に語ってもらった。(編集部)
「ブラーの『Parklife』に耳馴染みの良さを感じた」(越野)
――越野さんは2012年まで海外在住、西塚さんはプロミュージシャンとしてChayや大原櫻子のサポートをしていたりと、これまで個人としては様々なキャリアを歩んできています。まずは、そんな2人のルーツとなる音楽を教えてください。
越野アンナ(以下、越野):ブラーやジャミロクワイ、ビートルズは、自分の原点といえる音楽です。とくにブラーの『Parklife』は大好きな一枚で。自然に聴く機会が多かったからか、ブラーに耳馴染みの良さを感じました。
西塚真吾(以下、西塚):僕は、兄が音楽好きだったこともあり、小学生のころにL'Arc~en~Cielや、LUNA SEA、X JAPANなどがなんとなく耳に入ってきましたが、それ以降は、YUIさんや斉藤和義さんなど、ソロシンガーも好きになったり。
――それぞれが楽器を持って、プロを目指すようになったのはいつごろですか。
越野:ピアノは小さいころからずっとやっていました。ギターは作詞作曲のために、2年前くらいから弾き始めて。作曲は基本的にピアノでしたが、最近はアコースティックギターを使うことも多いですね。歌に関しては、幼いころからずっと歌っていました。
西塚:僕も小さいころからピアノを習っていました。でも、中学生になって「モテたい」という気持ちから、バンドを組むことになって(笑)。高校生の頃にプロを意識したのですが、その当時はYUIさんの楽曲を愛聴して「この人と仕事をするんだ」としか考えられなかったくらい、音楽に夢中でしたね。
越野:私がミュージシャンとして生きていくことを意識するようになったのは、12~13歳くらいの経験が大きいです。このころ、よく耳にする曲を「私だったらこうするのに」と、どんどん改変していて。ある日、友だちにそのなかから1曲を聴かせたらすごく感動してくれて、音楽のもつ力の大きさを実感し、作曲活動をするようになったんです
――楽曲を改変するというのは、どのようなステップで?
越野:楽譜に起こすとか、音源を作るというわけではないのですが、ピアノで曲のコードを確かめて、全然違うメロディを付けたりしていました。

――そこから先にプロミュージシャンとして西塚さんが世に出たわけですが、越野さんとはどのようにして出会い、anderlustを結成したのでしょうか。
西塚:僕が音楽をやっていく中で、どんどん色んな方と知り合っていって、そこからの縁で、越野のサポートに入ったのがきっかけです。
越野:真吾さんと出会ったのは、私が雑誌『NYLON JAPAN』とソニーミュージックの合同オーディションでNYLON賞を受賞して、新しい表現方法を模索していたときで。会話して意気投合した流れで、ユニットを結成しようと決意しました。
――“新しい表現方法”とは?
越野:何をもって新しいとするのかは、今も模索中ですが、その時から考えていたのは“アートを用いること”で。ライブ中にお客さんとその場でMVを作ったりするなど、音楽だけにとらわれず、どんどん可能性のある表現方法を見つけていけたらいいなと考えています。
――だから映像クリエイターも「状況によってはメンバーになるかも」という形で募集しているわけですね。
越野:そうですね。今回の募集については、一般的なミュージックビデオとは逆の作り方をしようというところからアイディアが生まれました。なので、エントリーしていただいた方に映像を先に作ってもらい、そこに私たちが曲を書いていくんです。
――今回の作品には、楽曲プロデューサー・(一部楽曲の)コンポーザー・アレンジャーとして小林武史さんの名前もクレジットされています。制作自体は、小林さんも含めた3人でどのように進めているのでしょうか。
越野:私は作詞・作曲を担当しているのですが、まずは思いついたメロディをボイスメモに録音して、ギターやキーボードで起こしてコードを付けながら、『Ableton Live』で音源を作っていきます。
西塚:僕は音のクオリティを下げないよう、プレイヤーとして徹しています。一音一音に対して妥協しないよう、しっかりとコントロールするのが役割ですね。
越野:そこで上がったデモを小林さんに渡して、添削してもらいながら形作っていくというのが、今の制作スタイルです。
――小林さんと共作詞のものも多いですが、こちらに関してはどうでしょう。
越野:場合によって違うのですが、大抵は小林さんからテーマをいただいて、それに私が詞を付けて、添削してもらうというキャッチボールです。「こういう表現方法を入れたらいいんじゃないか」とか「こういうフレーズはどう?」と提案いただくこともあって。
――越野さんは海外に住んでいた年数のほうが長いわけですよね。個人で作詞するときには、英語から思いつくのでしょうか?
越野:場合によりますね。基本的に曲作りをするなかで、一緒に歌詞を思いつくんですけど、実際にはそこからかなり変えますし、「A.I.」は全編英語詞だったものを日本語に直しました。「風船ep.1」は日本語で作ったもので、小林さんとのやり取りで変わったところはありますが、最初の形はある程度残っています。
――これからキャリアを重ねるなかで、得意な英語詞を使う可能性もありますか?
越野:そうですね。ただ、いまは日本で勝負するわけなので、聴いてる方に届きやすい日本語を選んでいます。その先のことはあまり考えていなかったのですが、海外へ出るタイミングなら、英語詞を書きたいですね。