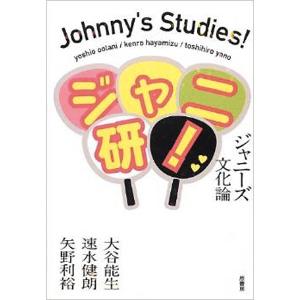戦後サブカル史におけるポピュラー音楽ーー円堂都司昭が「終末」と「再生」をキーワードに紐解く
2000年代以降、「終末」と「再生」の象徴は初音ミクだった
―80年代文化を考察するパートでは、『AKIRA』が破滅後の東京をある種の解放のイメージで描いているとお書きになっています。作品ひとつの中で「終末」と「再生」のイメージが共存していることもあると。
円堂:そうですね。『AKIRA』の話でいうと、消費主義が進んだ80年代の浮かれた感覚があったから、「終末」と「再生」がワンセットになるにしても、いくら破壊しても再出発できるというポジティヴな感覚が強かった。時代ごとに「終末」と「再生」のブレンドの仕方に違いがあるように思います。現在は『AKIRA』の頃ほど楽天的になれないですし。
―「ブレンドの仕方」はその後、たとえば2000年代以降はどう変わったのでしょう。
円堂:2000年代以降に目立ったのは、格差社会化です。かつて80年代には“一億総中流”と人々は思っていたのだから、大きな変化です。音楽について考えると、CD販売が減少する一方、音楽とつきあううえでネットの影響力の増大が、顕著になりました。既存のビジネスモデルの凋落と、ネットを介した新たなビジネスモデルへの期待という、多くの業界が直面した「終末」と「再生」の問題が、音楽に関してはわかりやすい形で現れた。その象徴が、初音ミクだったといっていい。人の声をもとに作られてはいるけれど、人の命は持っていない彼女をヒロインにして、渋谷慶一郎は死をテーマにしたボーカロイドオペラ『THE END』を作りました。でも、無料が普通であるネット空間でどんどん曲が作られ、流行していったゼロ年代後半を代表するヒロイン、初音ミクは、既存の音楽業界にとっては、自らの死を予感させる悪しき象徴だったかもしれない。でも、音楽を作りたいと思う新世代にとっては、彼女がいるから出発できるという希望を持たせる存在でもあった。世代や立場によって、ネットに対する認識にも格差が広がった時代でした。
―そして2010年代以降ではまた変わってきているように思うんですけれども、いかがでしょうか。
円堂:2011年に3.11という大きな出来事がありましたが、4年たってみて、私は思ったほど変わらなかったと感じています。原発事故の直後は電気に関する議論があったので、アコースティックな音楽がもっと流行するのかと思ったらそうでもなくて……。当時は、なるべく以前と変わらない方向に、みんなが持っていきたかったのでしょう。東日本大震災後、世間が日常を恐る恐る取り戻そうとする中、サントリーのCMが坂本九の「上を向いて歩こう」、「見上げてごらん夜の星を」をイメージソングに使いました。彼は、戦後の高度経済成長期を象徴する歌手ですよね。バブル景気崩壊後の“経済敗戦”の後遺症が深刻化した90年代後半には、負けから立ち上がるイメージのある曲「明日があるさ」をウルフルズやRe:Japan(ダウンタウンの浜田雅功など吉本のお笑い芸人たちのグループ)がカバーし、ヒットしました。これも坂本九の曲です。
毎年、卒業や入学の春になると、何曲も「桜ソング」がリリースされますけど、大震災後にNHKが放送するようになった支援ソングは「花は咲く」だったし、松任谷由実がチャリティプロジェクトに使ったのは「春よ、来い」だった。大震災の「終末」的光景から「再生」しようとした時、「春夏秋冬」といういつものサイクルがあらためてクローズアップされたわけです。敗戦から高度成長へという過去のサイクルを象徴する坂本九の曲が、国が危機に陥るたびに再注目されるのも、それに似ています。日本人は、いつものサイクル、過去のサイクルを引用することで、危機から日常を取り戻そうとするのだな、と思いましたね。