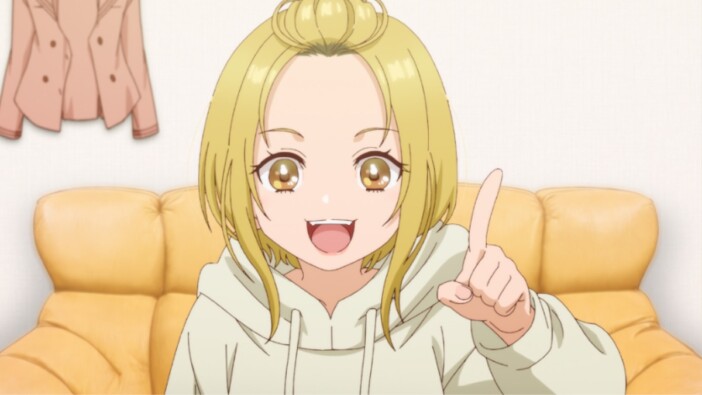『うたミル』原作・山中拓也に聞く、ゲームシナリオとアニメ脚本の違い 「“作り物っぽさ”を徹底して削ぎ落とした」

「アカペラ」をテーマに、女子高校生の青春と日常を、アカペラ初心者の声優陣の成長ととともに描く音楽プロジェクト『うたごえはミルフィーユ』(以下、『うたミル』)。オーディオドラマからスタートした本作のテレビアニメが7月17日~9月18日にかけて放送された(全10話)。
そんな『うたミル』の制作を、ポニーキャニオンとともに企画・原作・シリーズ構成・脚本にいたるまで担当したのは山中拓也氏。“人の心の闇”へと踏み込むジュブナイルRPG「Caligula -カリギュラ-」(以下、「カリギュラ」)シリーズを手掛けたことで知られるゲームクリエイターは、『うたミル』に数々の“アニメらしさ”からかけ離れた試みを盛り込んだと明かす。
『うたミル』はいかにして生まれ、そのハーモニーのなかにはどのような思いが込められていたのか。アニメの見どころやオーディションの裏話、さらにはゲームクリエイターをルーツとする山中氏がアニメに向き合って感じた違いなども含めて、たっぷりと語ってもらった。
奇跡的な巡り合いを経て、キャスト陣の歌声はいまや遙か高みへと
――はじめに、『うたミル』にまだ触れたことがない方に向けて本作の見どころや特色について教えてください。
山中:アカペラを題材とした作品自体は過去にもありましたが、『うたミル』の大きな特徴はキャラクターの演者が実際にライブでアカペラができることです。
これはアニメを観てくださっている方にはなかなか想像しづらい部分なのかなと思いますが、アニメやゲームなどの二次元コンテンツでアカペラをやるとしたときに、メンバーそれぞれのパートを歌声を個別に収録して編集で合わせれば、確かに“アカペラ音源”にはなります。対して『うたミル』は、実際にメンバー6人が対面で揃って生でアカペラをすることができるため、ライブでのアカペラ体験を提供することができます。特に生のアカペラと、多重録音の違いというものを物語に込めようと思っていたので、そこのこだわりは必須のパーツでした。
――音源を重ねるのではなく実際にその場で重ねるとなると、相手の歌声を聴きながらそれに合わせるといった技術も必要となりますよね。
山中:そうなんです。歌が上手な人が集まればアカペラができるわけではなくて、アカペラがうまくなるためにはアカペラをやるしかないので。本当に難しいことなんですが、毎週練習を積み重ねて、それこそ『全国ハモネプ大リーグ(ハモネプ)』に出場できるくらいにキャストの皆がアカペラに打ち込んでくれていることは、『うたミル』というコンテンツにとっての唯一無二の宝になっています。アカペラに本気だからこそ、作品としての本気も伝わるものだと思うので。そこのこだわりを持ち続けることこそ、アカペラ経験者の自分が制作の中心にいる意味だと思っています。
――そんな『うたミル』ですが、山中さんはいつごろからどのような形で制作に携わっていたのでしょうか?
山中:もともと僕が作っていたゲーム「カリギュラ」のアニメ化をポニーキャニオンさんがやってくださっていたご縁で、そこから仲良くさせていただいて。僕はゲームのお仕事が中心だったわけですが、企画をたくさん作っていくなかで「これはゲームではない媒体のほうが相性がいいかも」といったものも生まれるんですよね。
その中のひとつに、僕が大学時代にアカペラサークルをやっていた経験をもとにした企画がありまして。人生においてアカペラをやっていたのはそのサークルに在籍していた期間だけではあったのですが、なんとなく忘れがたい思い出として残っており、何かしら自分の作品にしたいと思っていたんです。
それをオーディオドラマ+声優さんのアカペラという形でやっていく企画としてポニーキャニオンさんと作ることになり、この度ありがたくアニメ化させていただけることになったという経緯でした。本当に最初の企画書は2019年に作っていて、自分が独立したのがその前年ですから、ちょうどゲーム以外の企画も作っていこうと思い始めた時期ですね。
――コンテンツをキャストのみなさんの成長と同時進行で届けていくというアイデアは、当初から想定していたものなのでしょうか?
山中:はい。『うたミル』で提供したい体験とは、まさに公式YouTubeチャンネルでお届けしているようなキャストのみなさんの練習ドキュメンタリーのような、生身のキャストさんの苦労や壁にぶち当たる姿と作品の内容がある程度連動するようなもの。作品のなかでのキャラクターの成長と、キャストの成長を重ね合わせて楽しめるものを目指していました。アニメのなかで「音色が合わない」といったアカペラの専門的なお話――本来ならば省略してもよさそうなところまで描いているのもそのためです。
ものすごく幸運なことに、キャストのみなさんは本当に歌がうまいのは勿論、アカペラに対して情熱を持ってくれているし、プロ意識も高くて……。
本当に、こんなことを言ったら申し訳ないんですけれど、これほどまでにうまくなる予定ではなかったんです。本来ありえない速度で成長していて、作中のキャラクターたちの実力をとうに凌駕してしまっているので、演じてもらう際はちょっと初々しい感じでレベルを落としてやってもらうという、ものすごく難しいことをやってもらっています。
――ボイスパーカッションを担当するウルル(宮崎閏)役の花井美春さんをはじめ、ほかにもオーディションで印象的なエピソードがあれば教えてください。
山中:花井さんは本当に驚きでしたね。もちろん声優さんにボイスパーカッションの経験者がいるわけではないので、一種賭けの部分はありました。花井さんの持ち前のリズム感と耳の良さ、そういった多種多様な才能に賭けたわけですが、あそこまでのレベルになるとは誰も想像していませんでした。経験者ほど驚くと思います。類まれなる努力の結果だと思います。
そこでいうと、ウタ(小牧嬉歌)役の綾瀬未来さんがオーディションに応募してきてくれた当時は、まだ15歳だったんです。あれほど肝が据わった15歳はいないなとオーディションに立ち会って思いましたし、本人的には緊張やプレッシャーはあるのかもしれないですが、傍目から見ていてお芝居も歌も本当に堂々とされていて。そんな方にセンターを務めてもらえたことは、『うたミル』にとっての大きな財産のひとつかなと思います。
やはり自分で脚本を書いている以上は自分の作品らしいお芝居を求めてしまうわけで、極力二次元的な誇張の少ない自然主義なお芝居をやりたいと思っています。コメディー的なシーンでも変にツッコミ役を立てないだとか、現実の会話に近いテンポになるようにこだわって作っています。そういった部分でもうたミルキャストの6人は相性のいい方、そして自分のやりたいことを理解してくれる方と出会えたという感覚があります。
――たしかに、なかでもウタは非常に特徴的なしゃべりかたをするキャラクターですよね。ズバズバと言いたいことを矢継ぎ早に口にしたり、ほかの人がしゃべっているところにいきなり「ごめんなさい」とカットインしたりと。
山中:ちょくちょくアニメっぽくないという感想をいただくことも多いんですが、それは僕がアニメ畑で育ってきていないことも大きいと思います。アニメのテンプレートやフォーマット的な表現にあまりこだわりがないんです。
やや話が逸れますが……これは自分のコメディー論のようなところで、“二次元のお笑い”とは、すでにある“くだり”を楽しむ傾向があると思っていて。ネットミーム的な。たとえば、みんなで同じシーン同じタイミングで「バルス」って言うのが楽しいみたいな、そういったお決まりのくだりを共有することで安心するというように。
僕はそういったノリにいまいち乗り切れない人間だったので、できるだけ独立した「存在しない」くだりがやりたくなっちゃって。そういう手癖から、いままでにないような不思議な空気感が生まれているのかなと。いまの時代的には、“バズり”が生まれにくい難しい試みでもあるとは思いますが。
――売れるかどうかだけが重要ではないというスタンスは、ゲームクリエイターとしての山中さんから一貫しているものなのですね。
山中:本当によくないところです(笑)。キャラクターのヘイトコントロールみたいな話も近年はよく聞きますが、そこもあまり気にした記憶がないです。キャラクターたちが画面の向こう側の人間に好かれるかどうかを彼女たちが気にする必要などないわけで、その子がその子らしく生きている姿を好きになったり嫌いになったりしてくれればいいかなと思っています。
――3~4話にかけての、ウタとクマちゃん(熊井弥子)のやり取りにもただならぬ説得力のようなものを感じました。
山中:もしかしたら問題解決のための最短距離みたいなものを、もっと早く通れる展開もあり得たかもしれないし、アニメとして、物語として劇的な展開にできる可能性もあったかと思います。ただ、そこは物語のためにキャラクターが存在するわけではないと考えているので、キャラクターのためを一番に考えてあげたかったんです。
そういったスタンスを、総監督である佐藤卓哉さんも、ポニーキャニオンさんも一緒に目指してくださったので本当にチームに恵まれたと感じています。
「カリギュラ」シリーズのなかで人の心をテーマに描いていたころから、やはり人の心の問題を安易に劇的に解決するお話を書きたくないという思いがありまして。人間が可能な範囲で、理解できる速度で、コミュニケーションを主体に解決していくとなると、あのような展開と顛末が彼女たちにとって最良だなと思えたというのもありますね。
――「カリギュラ」のお話が出ましたが、ゲームのシナリオとアニメの脚本を比較したときの違いや、ゲーム制作の経験がアニメ制作に活きたポイントなどがあれば教えてください。
山中:誤解を恐れずに言えば、ゲームのシナリオというのはおもしろくしやすいと感じました。プレイヤーがボタンを押す経験であったり、敵を倒してともに成長していく没入感であったりが、インタラクティブであるという部分が物語体験を何倍にも輝かせてくれるんです。
その点、アニメは視聴者が受け身にまわることになる媒体ですし、限られた放送時間の中でそれぞれのキャラクターをその子らしく生き生きと描くということは、ものすごく高い技術が求められるなと思いました。ゲームだとテキストを増やすことは容易ですが、アニメでは尺の関係でひとつのワードあたりの重要性が高まりますから、そこへの集中力は試されましたね。今もなお、いろいろ勉強中ですね。うたミルに限らずたくさん機会をいただけるように頑張ります。
――だからこそ、『うたミル』には心に刺さるキャラクターの発言ややり取りが無数にあったように思います。山中さん自身は、印象的なエピソードやセリフで思い浮かぶものはありますか?
山中:そこでいうと、ウタは1話の段階では視聴者から徹底的に嫌われていいと思って書きました。社会のなかでうまくやっていけないというところからスタートするキャラクターなので、そうした姿が単に「かわいい」「おもしろい」の感想だけで終わってしまったとしたら、それは失敗だなと思っていたので。
初見の方がウタの姿を見て、「キツイな」「この子を見るのがストレスだな」と思えるような描写になっていないと、“周囲とうまくなじめていない”というウタの現状に対して誠実ではないという思いで、好き嫌いが極端にわかれるキャラクターとして書いた。そういう意味で、視聴者のみなさんには負荷をかけることになりましたが、それも『うたミル』という物語を見守っていただくうえでは必要なものだったと思っています。最適化された作りではないことは理解しつつも、ウタが最後にどういう成長をするか、という助走距離を長くとりたい気持ちがありました。
――アニメが中盤に差し掛かる6話では先輩バンド的な立ち位置の「Parabola」の面々が登場したり、「アカペラ部」のなかでも激しい衝突が起こったりと大きな展開を迎えていきましたね。
山中:『うたミル』が大会に勝つことを目指すお話だったら、誰が正義なのかもわかりやすく結論付けられると思います。ただ『うたミル』はそういった形をとっていませんし、現実においても多くの部活は勝つことだけが目的ではなかったり、そもそも何かに勝つこと自体を目的としていなかったりしますよね。
「アカペラ部」もコンクールや何かが待ち受けているわけではないし、各々の目的意識という部分も正解が存在するようなことではない。作品の方向性に沿って目的を示すのはお話づくりのお決まりだと思いますが、でも現実には目的なんてないことのほうが多くないですかと。目的がないことって世の中にたくさんあるよねということを、それでも物語になりえるということを、逃げずに描きたかったんです。
――まさにアニメのなかでウタが「何のために歌っているのか」を問われたときに、個人的に「ここでアニメ的なズバッと腑に落ちる回答が出るものだろう」と期待していたこともあって、呆気にとられました。
山中:そうですね。そういった曖昧なものを言葉巧みに言語化して定義する行いって、ある意味すごく楽な道で、気持ちのいいことだと思うんです。でも、現実はそうじゃないもんなというところを、そのまま描写したっていいじゃないかという思いがあります。
これまではゲーム制作者として、しっかり白黒をつけるまではいかなくとも、ゲームである以上はそういった気持ちよさを感じてもらえる瞬間をつくってきたところがありますから、なおさら違うメディアでは違うことをしたいと思っていましたね。
今泉力哉さんという映画監督さんがいらっしゃって、僕はその方が大好きなのですが、今泉監督は「主人公を成長させない」というこだわりを持っているんです。僕はそこまで徹底できないなとも思ってしまうんですが……そのお言葉の裏側には、やはり人生とは劇的なものではないし、物語のように展開があって何を得るものではないケースが多いから、観た人に疎外感を与えてたくないという意図があるのだと思います。僕も、観終えた後でみなさんが現実に持って帰れる程度の気づきだったり感慨だったりを描いていきたいなと。
――勝つだけが部活ではないというところはありつつも、「Parabola」のメンバーたちは恐ろしいまでの風格を漂わせており、リアルタイムで見守っていた当時は「どのような展開が待ち受けているのだろう」と身構えずにはいられませんでした。
山中:「Parabola」はライバルバンドとして紹介されがちなのですが、そもそもライバルと言えるようなレベルにはいない人たちなんです。部活動としての「アカペラ部」に対して、プロビジネスの域にいる「Parabola」は視座がもう違っていて。アニメはあくまで「アカペラ部」のお話で、「Parabola」のお話は原作のオーディオドラマにて展開していますので、興味のある方はぜひチェックしていただければと思います。
「アカペラ部」と「Parabola」の構造は非常にマニアックでして、「アカペラ部」がみんなで顔を合わせてできる元来のアカペラだとしたら、そこからある種乖離した音楽文化として、より多くの人に届けるために多重録音のクオリティを突き詰めた現代的なアカペラというものが現実の潮流としてあり、それをやるのが「Parabola」なんです。
あまり語るのも野暮なので短めに留めておきますが、出たままの歌声を一発勝負で重ねるアカペラと、「声だけ」という魅力でありつつも最大の弱点を現代技術で解決しているプロフェッショナルな多重録音音源としてのアカペラがどう違うのかというところまで、せっかく『うたミル』を機にアカペラに触れてくださるなら感じてもらいたかったという背景もありました。

――(取材時点では)絶賛放映中の『うたミル』ですが、山中さんは原作者の立場から彼女たちの歩みをどのように見守ろうと考えていますか?
山中:先程話したウタへの反応や、クマちゃんの声がTikTokで笑われていたりとか、そういった反応は実際に現実に彼女たちが受けてきた反応だと思うんです。もしかしたら、彼女たちを知っていけばその言葉を後悔するかもしれないし、彼女たちを揶揄する言葉に怒りを覚えたりするかもしれない。そういうところがしっかりリンクしてくると思うんです。そういった体験をお届けできたらという思いがありますので。
あらためてアニメという媒体が特殊だなと感じたのが、「今期のアニメをすべて評価しよう」という目線を向けているお客さんが多いことでした。Tier表をつけてみたり、ですね。良し悪しの話ではなく、シンプルに特徴的だなと。ゲームはお金を払うことがある意味儀式化していることもあり、期待しているから買うし、買った以上は向き合おうという気持ちが少なからず生まれるのか、そこは大きな違いだなと思いました。
アニメでは無料だからとりあえず観てみようという感覚の方も多くいらっしゃるからこそ、身内びいき的なものがなくフラットに受け取ってもらえる人の比率がゲームよりも高まるのだとすれば、深いなと。そういった環境で、ある種競技的に勝ち方の最適化が見つかりつつある。その中で自然主義のうたミルがどう受け入れられるのかすごく興味深かったです。たとえ表面的に観て彼女たちにもどかしさを感じるだけで終わったとしても、そういったモダモダした気持ちを楽しんでもらえたら自分の作品らしくていいのかなと思います。
「恋っていいな」という気持ちを届けたい―― 『KANADE』シナリオライター浅生詠インタビュー
新作ビジュアルノベル『KANADE』が、6月12日にフロントウイング25周年記念作品第2弾としてPC向けに発売予定だ。今回は発売…