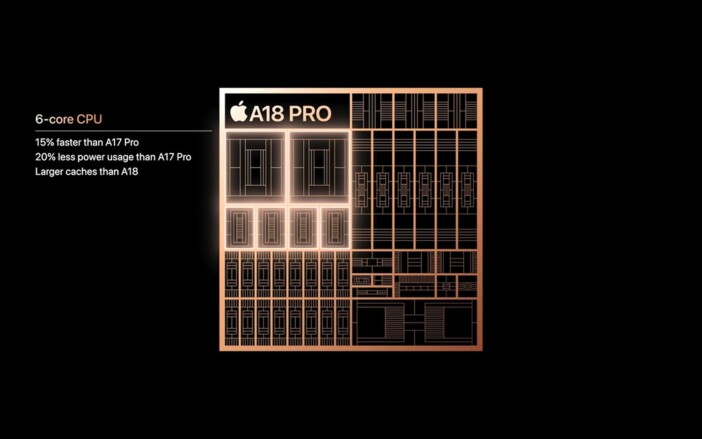ゲーム原作の映画化における「出口」はどこか——映画『8番出口』がたどり着いた“体験”の描き方

『8番出口』とカメラワーク

映画『8番出口』は、電車に乗る主人公・迷う男(二宮和也)の一人称主観視点で始まる。この、いわゆるPOV(Point of view)視点は原作で採用されている唯一のカメラアングルでもあり、原作経験者は否応なく本作が「ゲーム『8番出口』の映画化」であることを意識させられる。
その後、主人公は電車から降りて地下鉄の構内を歩き回り、やがて気づかないうちに舞台となる無限回廊へと出る。そうして、それこそゲームよろしく、何度かループを繰り返していくうちに事態の異常さに気づき……といったところでカメラが切り替わり、POVを離れて正面から主人公を捉えたショットへと移行する。

さらにその後、カメラは主人公の後ろ姿を少し離れたところから追うアングルへと変わる。以降は細かい変化を織り交ぜつつも、この三人称限定的で長回し気味の視点がこの映画におけるカメラの主なモードとなっていく。

単純にゲームプレイの見た目上の視覚と映画の視覚を一致させることだけを考えるならば、最初の一人称主観視点だけをつらぬいていればよい。なぜ三人称視点が中心となったのだろうか。
ビデオゲームと映画の最大の違いはインタラクション、つまり、コントローラーのボタンを押してゲーム内でレスポンスが生じるかどうか、というのはよくいわれるところ。このインタラクションの不可能さがプレイ体験の再現における最大の障壁といってもいい。
ところが、この点、ゲーム『8番出口』は比較的有利なポジションにある。
どういうことか。ゲーム『8番出口』は、ジャンルとして「短編ウォーキング・シミュレーター」を謳っている。(※2)
ウォーキング・シミュレーターのジャンル的な歴史や思想性は興味深いものの長くなるので割愛するが、ここで重要なのはジャンルのオリジネーターである『Dear Esther』(2008年, 2012年)がゲームに求められるほとんどすべてのインタラクションを剥ぎ取り、「一人称主観視点で三次元空間内を歩く」以外の操作をできなくした事実だ。
ゲーム『8番出口』もゲーム内で取れる行動は歩行のみである。戦闘も会話もなし。ジャンプもできなければ、ファイヤーボールも投げられない。事実上、プレイヤーに求められるのは“目撃すること”だけだといっていい。これは、他のビデオゲームよりも映画の体験に近い。
さらにループものであることもプラスに働くだろう。もともと、ループものの映画はループを脱するためにゲーム攻略的な試行錯誤を描くものが多い。特に近年の日本の実写作品ではその傾向が強く、『MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』(2022年)や『リバー、流れないでよ』(2023年)などでは、ループに気づいたキャラクターたちが力を合わせてループの原因をロジカルに突き詰めていく。試行錯誤の過程そのものが物語のリソースとして利用できるというわけだ。
では、そのウォーキングシム的な一人称主観視点を映画に移植して、ループもの的な攻略を行い、ゲームで起こった異変をオーディエンスに目撃させれば原作の体験と一致するのか。
残念ながら、そうはならない。
原作ゲームでカメラを動かすのは、プレイヤー自身だ。映画では、そのコントロールが映画に奪われてしまう。同じ目撃行為でも映画は「見せられてしまう」のに対し、ゲームは「自分で見てしまう」という点で決定的に違う。たとえば、カメラの背後に不吉な予感を感じたときに映画では次のカットで強制的に振り向かせられてしまうが、ゲームではプレイヤーが振り向くという動作を選ばないかぎりは永遠にその正体を確かめることはできない。

だからこそ、映画『8番出口』も異なる戦略を取った。まず、観客に「観客であること」を意識させた。それが二番目のカメラアングルである正面からのショットだ。このとき、移動する主人公の頭上で普段は「地下広場」と書かれている案内サインが、「引き返せ引き返せ引き返せ引き返せ」と表示されたはっきり不穏な「異変」に変わっている。しかし、正面を向いている主人公からは死角になっている。彼にはわからない。いや、そこにあるんだから振り向いてよ、ニノ!
……と、観ている側が心のなかで行うこうしたツッコミは、まぎれもなくプレイヤーの立場でなく「観客的な立場」に発している。そう、このカメラの転換においてプレイヤーになっているのは映画内部にいる主人公だ。
ついでにいえば、誰かの顔の向こうに舞台となる空間を見る、といった構図は一部のYouTuber/VTuberのゲーム実況動画を想起させる。実況動画はプレイヤーである実況者と観客のツッコミやコメントが同時に展開される場だ。原作ゲームのバイラルな認知度向上に大きな影響を与えたのがゲーム実況文化だった、という背景は観客たる原作ファンの意識に埋めこまれているところだ。この点は見逃してはならない。
“MOD”としてのカメラ
そうしていったん、プレイヤー=主人公、観客=観戦者としてくっきり分けておいて、三度目のカメラの切り替えとなる追尾的な三人称限定視点へと移るとどうなるか。主人公の視点と観客の視点がほとんど重なるという点では一人称主観視点と似ているが、観客にとって他者である主人公がはっきりと画面に映るぶん、移入の度合いは下がる。やはり、彼がプレイヤーだ、と。
と、同時にその主人公と視点を共有することで、映画内で語られていくことになる彼についての(映画オリジナルの)物語へと感情を乗せやすくなる。主人公に「異変の頻発する箇所を指さし確認させる」などといった原作プレイヤーあるあるを取り混ぜ、プレイ体験的な共感への目配せも忘れない。
一見すると迂遠でしちめんどうな序盤におけるカメラの二転三転は、実は映画の物語を語るために必要な精妙な手続きであり、最終的に選ばれる背後からの三人称限定視点は観客に「プレイヤーでありながらも観客でもある」という矛盾した立場をするりと受け入れさせるための絶妙な距離だったのだ。
なおレトリックを推し進めるならば、こうしたカメラの自在な変更もまたビデオゲーム的であると形容しうるだろう。ゲームには「MOD(Modificationの略)」と呼ばれる、制作者以外のだれかが非公式にゲームの内容に手を加えるというユーザー中心の改造文化がある。そのなかには、まさにカメラのアングル変更のMODも含まれるのだ。
たとえば、オープンワールドアクションRPGである『Borderlands 3』(2019年)は通常プレイ時には一人称視点で固定されているのだが、ユーザー制作のMODを導入することで三人称視点に切り替えられる。ふだんは三人称で、射撃のエイム時だけ一人称に切り替える、といった小器用なバリエーションまである。
映画『8番出口』も、「公式」たるゲーム原作で唯一の視点だった一人称主観視点を変更することで、映画制作陣の独自の解釈(MOD)を加えたものとみなせる。
跳ぶカメラ
そのような、映画とビデオゲームのメディアの境界に自覚的な、極めて批評的な手練手管でもって、映画『8番出口』の移植は完成された……かに見えた。
ところが映画後半でその完成が崩される。もう一度、カメラが新しいアングルに移動するのだ。
どこに?
別のキャラクターに。

ゲーム『8番出口』には、ほとんど唯一といっていい登場人物がいる。それが、「おじさん」こと歩く男(河内大和)だ。通路に毎回現れ、プレイヤーとは逆の方向に歩き去っていく。それだけの存在だ。ゲーム中では、たまに異変化することもあるものの、基本的には話しかけることもできなければ触れることもできない。関わりを一切持てない。
映画版では、ある瞬間に、その歩く男へとカメラの視点が切り替わる。歩く男もまた『8番出口』の異常空間に閉じ込められ、主人公同様にその謎に苦しんだ、という物語が挿入される。
危うい均衡の上に成り立っていた「プレイ体験の再現」が、この切り替えによって打ち壊される。なにせ、原作では歩く男視点でのプレイなどできないのだ。だれも、想像すらしなかっただろう。たしかにゲームには本来操作できないキャラをプレイアブルにするようなMODもあるにはある。だが、これはゲーム『8番出口』のオリジナルな体験からあまりにかけ離れている。
体験の複数性、物語の複数性

映画を観ながら、急に足場を失ったような寒々しさに愕然とし、やはり「映画の一貫性」など妄想にすぎないのか、などと絶望していると、また視点が主人公=迷う男へと戻される。
そこで彼は、ある異変に気づく。
それは、さきほど致命的な見逃しをしていた「案内サイン」の異変だった。
迷う男と歩く男、ふたりとも明確な気づきのきっかけを与えられながらも、歩く男のほうはスルーしてしまい、迷う男のほうは立ち止まって振り向くことができた。
いわば、同じプレイヤーでのループごとの違いではなく、異なるプレイヤー間でのプレイの違い。
ここでわれわれも立ち止まって振り返ってみよう。
憶えておいでだろうか。映画『8番出口』にはゲーム実況的な瞬間がある、と書いたことを。「原作ゲームのバイラルな知名度向上に大きな影響を与えたのがゲーム実況文化だった」ということを。
現代における「ゲームの体験」とは単にゲームプレイのみを含めない。eスポーツや配信者のゲーム実況の視聴もビデオゲームという文化の輝かしい一部を成している。
ゲーム『8番出口』とは、まさしく配信者ごとのプレイやリアクションの差異を楽しむことでプレゼンスを高めてきたのではなかったか。(※3)
『8番出口』の実況配信は発売直後から盛り上がって現在まで続き、ガチャピンからHIKAKINまで、有名配信者および芸能人が(一部は映画のプロモーション絡みもあろうが)こぞって動画を投稿している。映画宣伝として声優の花江夏樹が映画を「実況」したCMも公開されている。花江は自身も過去に『8番出口』のゲーム本編の実況も行っており、こちらも150万再生以上を記録している。個人制作の国産インディーゲームで、再生数100万超の動画がならぶというのは、かなり稀なことだ。
ゲームはプレイヤーごとに固有の体験を持たせる。『8番出口』はメカニクス中心のゲームであるがゆえに、その体験は一定ではない。初見でクリアに成功するプレイヤーもいれば、何時間も0番出口に戻されつづけるプレイヤーもいる。そうした個別の体験をオーディエンスが外から眺めること、それは“そのプレイヤーの物語を読む”行為にほかならない。
監督の川村元気は、『8番出口』というゲームについて「この真っ白な空間で起きていることは人生のメタファーなんじゃないか」と解釈し、そこから物語を膨らませたと語っている。本作における人生とは物語だ。
人生=物語の複数性は映画において大いに意識されている。前出のインタビューで川村はテーマについてこう語る。
小説のほうで詳しく書きましたが、「無関心の罪」はこの物語のテーマの一つです。例えば人を殺すとか、おカネを盗むとか暴力を振るうこと、セクハラとかパワハラみたいな罪って、顕在化していますよね。だけど、現代人が日常的にもっとも頻繁に起こしている罪って、暴力や戦争や差別などに対して「見て見ないふりをする」ことじゃないでしょうか。その「無関心の罪」は、地下通路の異変を気付かずやり過ごしてしまうことと、重ね合わせて描くことができるんじゃないかと思ったんです。(※4)
監督自身の手がけた小説版においては、映画で見えづらい主人公の細やかな内面が描写されているのだが、そこにおいて主人公は異物だとみなしていた歩く男について、彼にも人間性や苦悩があったのではないかと思いを馳せるくだりがある。
それは別のプレイヤーのプレイを眺められるゲーム実況時代の想像力にも擬せられる。
ことここに及ぶと、映画版の物語は映画であることの必要から求められたものではなかった、ということにさえなってくる。ゲーム作品とその周辺までを含めた、ゲーム文化を描くために迷う男や歩く男の物語が要請されたのだ。(※5)
そこまでやってはじめて、現代におけるゲームの体験の再現に至ることができた。
『8番出口』の出口について

かくして、映画『8番出口』は、「ストーリーの再現」でも「プレイ体験の再現」でもない第三の「ゲーム原作の再現」を見出した。それは、三十年以上に渡るゲーム原作の映画化において映画作家たちが悩み、迷い、挫けてきた屍の上にようやく発見した光であり、外へとつながる出口だ。
問題は、文化には次の曲がり角で「0番」に差し戻される可能性がつきまとっている、ということだがーー。
〈注釈〉
※1:技術的制約とは別に、そもそもビデオゲームはルールとメカニクスのメディアであり、物語は「ゲームにとってつまらない装飾やギフト包装にすぎず、それを研究することに力を注ぐのは時間とエネルギーの無駄である」(2001,Eskelinen)とするゲーム研究者もいた。
※2:小島秀夫の『P.T.』(2014)という未完成作との近縁性をよく指摘されるけれども、作者本人は『I'm on Observation Duty』とのつながりをより強調している。
※3:ここで言ってるのは知名度のことで、売上との直接的な因果関係はまた別。ちなみに本作については作者の定めた実況配信ガイドラインがあるので、実況したい向きは必ずチェックされたい。
※4:水鈴社公式note『川村元気 小説『8番出口』刊行記念インタビュー』より。
※5:とはいえ、主人公のために用意された物語には川村元気の作家性が強く認められる。つまりは、愛と記憶と選択。それらのある種人工的な運命。
■映画情報
キャスト:二宮和也/河内大和/浅沼成/花瀬琴音/小松菜奈
原作: KOTAKE CREATE「8番出口」
配給: 東宝
監督: 川村元気
脚本: 平瀬謙太朗、川村元気
音楽: Yasutaka Nakata (CAPSULE)、網守将平
脚本協力: 二宮和也
全国東宝系にてロードショー
■関連リンク
映画『8番出口』公式WEBサイト:https://exit8-movie.toho.co.jp/
『8番出口』映画化が示唆する新トレンド 2025年はインディーADVの“メディアミックス元年”に?
2024年12月27日、『8番出口』の映画化が発表された。「インディーゲームのメディアミックス」という観点から、新たに生まれつつ…