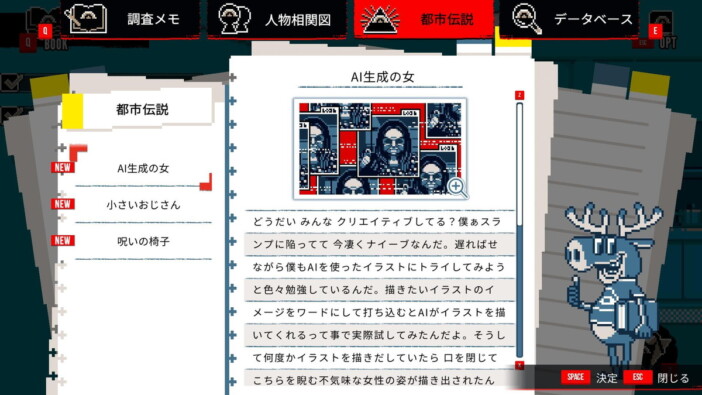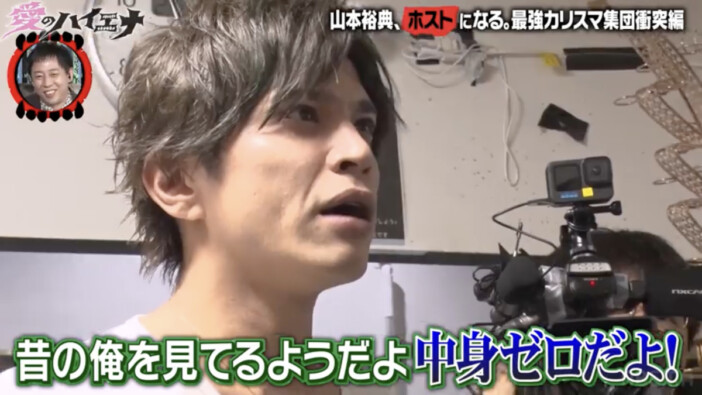王道にして異端なゲーム作り 「サガ」シリーズの生みの親・河津秋敏のクリエイティブを追う

王家に生まれながら術の適性がなかった子ギュスターヴと、両親の死にまつわる“エッグ”という存在を追いかけるウィル・ナイツの物語が交錯していくRPG『サガ フロンティア2』。このたび、26年の時を経てついにリマスター版が発売された。
本作のディレクションを担当したのは「サガ」シリーズの生みの親である河津秋敏氏(以下、敬称略)。スクウェア(現スクウェア・エニックス)の黎明期から国産RPGを作り上げてきた河津は、いまだに最前線でクリエイティブを発揮し続けている。
今回はそんな河津の来歴を追いかけつつ、彼が作り上げてきた名作たちを紹介していきたい。
スクウェア入社~『魔界塔士Sa・Ga』
1962年に熊本県で生まれた河津は、東京工業大学理工学科に進学。Apple IIを購入した友人らとともに海外のボードゲームを遊んでいくうちに、コンピュータゲーム作りに興味を持つこととなった。
https://www.nintendo.co.jp/wii/interview/rfcj/vol1/index.html
1987年、スクウェアにアルバイトから入社し、大学を中退。同年に『ファイナルファンタジー』のゲームデザインを任され、ゲーム開発者としてのキャリアをスタートさせる。

『ファイナルファンタジー』はもはや言わずと知れたRPGシリーズだが、河津のクリエイティブがわかりやすく発揮されたのは翌年に出た『ファイナルファンタジーII』だ。本作で河津はゲームデザインとシナリオを担当している。
『ファイナルファンタジーII』ではレベル制を廃止し、武器や魔法の頻度や、攻撃を受けた回数によってステータスが上昇する仕組みを採用した。これにより、余裕のあるときに味方キャラクター同士で攻撃しあっておく……といった、本作でしか見られないテクニックが大量に存在する。

このレベル制の廃止や、唐突なテキストという味は、彼が初めて全面的にディレクションをしたゲームボーイのRPG『魔界塔士Sa・Ga』(1989年)に受け継がれる。
『魔界塔士Sa・Ga』はゲームボーイで初めて制作されたRPGだ。当時のスクウェアの社長である宮本雅氏が『テトリス』のような落ちものパズルを期待していた一方で、河津は「ユーザーはRPGを望んでいる」と考え、社長の意見を押し切って開発した作品である。
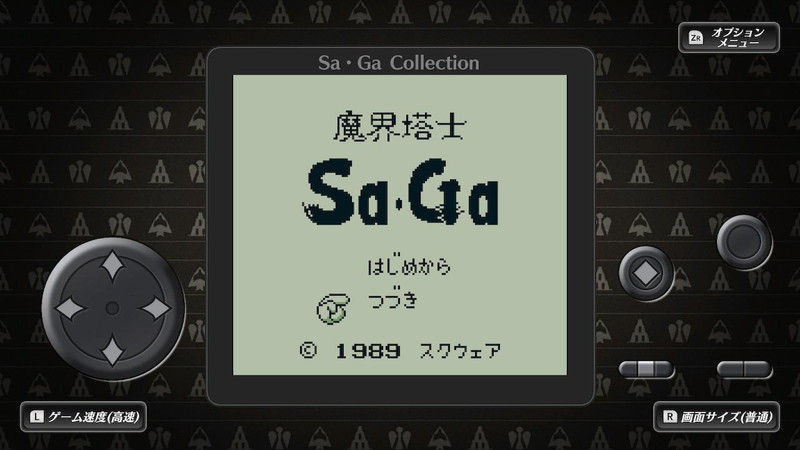
結果としてはスクウェア初のミリオンセラーを記録し、そのゲームとしての完成度からゲームクリエイターである田尻智に影響を与え、かの「ポケットモンスター」シリーズに繋がったとも言われている。しかし、この説は近年になって当人が(半ば謙遜も入っているようだが)否定していた。
時折り、この論を目にします。「魔界塔士」を持ち上げて頂けるのは有り難い事です。しかし、ポケモンは田尻さんという個性が生み出した作品です。先行する様々なタイトルの影響を受けているとは思いますが、何か特定のタイトルが決定的な影響を与えた様な事実は無いと思います。
— 河津秋敏 (@SaGa30kawazu) January 18, 2025
ゲーム自体は『ファイナルファンタジーII』同様にレベル制ではなく(河津が直接関わっていない『時空の覇者 Sa・Ga3』以外、サガシリーズにレベル制は導入されていない)戦闘終了後、種族ごとにステータスが上がったり、わざを覚えたりするといった仕組みになっている。
また、当時から主流だった中世ファンタジーの世界観に比べて、塔のなかにいくつもの世界がまたがっており、それらを行き来するというストーリーもとてもユニークだった。シリーズを象徴する「サガ」という言葉に込められた意味がわかるラストシーンは、ラスボスをチェーンソーで一撃にできるというバグともども必見である。
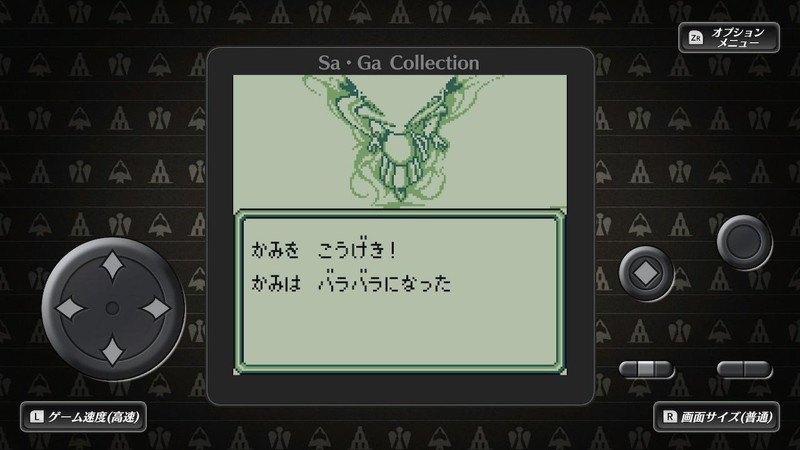
「ロマンシング サガ」シリーズ
『Sa・Ga2 秘宝伝説』を発売したのち、河津はスーパーファミコンでのRPG開発を任される。
生み出されたのは『ロマンシング サ・ガ』(1992年)。ここに来て彼は、自身のクリエイティブのなかでもっとも重要なメカニクスを構築していくこととなる。

ひとつは「フリーシナリオ」という仕組みである。これは読んで字のごとく、プレイヤーが好きなように行き先を決めることができる仕掛けで、どこでどんなイベントを攻略してもよいという作りだ。
このシステムを成り立たせるために裏で動いているのは、戦闘回数によって敵が強くなったり、イベントが勝手に進行したりするというプログラムだ。主人公たちも倒した敵の強さに応じて成長するため、どこに行っても戦いは退屈にならず、ゲーム側で行き先の順番を固定されることもない。
次作『ロマンシング サ・ガ2』では、これらの仕組みに加えて「ひらめき」という仕組みが登場した。

これは戦闘中にランダムでわざを習得し、その場で使用するという仕組みだ。従来のRPGではレベルに応じて固定の技や魔法を覚えていくものがほとんどであり、現在も多くのゲームがそれを採用しているが、ひらめきは(テーブルこそ決まっているものの)どの武器をプレイヤーがどの程度使うかによって習得する順番が左右されるため、同じ冒険でも毎回新鮮な驚きを提供してくれた。
また『ロマンシング サ・ガ2』は七英雄というボスも有名である。本作もまたフリーシナリオであり、どこに向かうかはプレイヤーの自由だが、七英雄もまた自分の都合で特定のロケーションを行き来している。イベントの段階によってボスと会ったり会わなかったりするという仕掛けに、当時のプレイヤーは度肝を抜かれた。
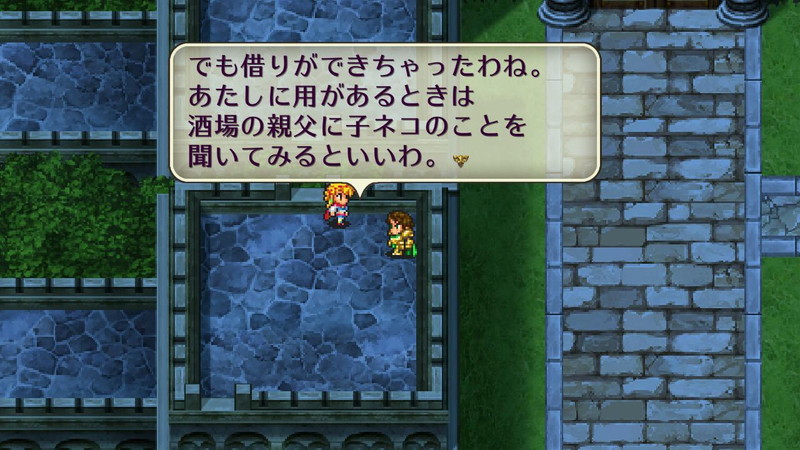
「サガ フロンティア」シリーズ
『ロマンシング サ・ガ3』を発売したのちは、ハードウェアをPlay Stationに移して『サガ フロンティア』(1997年)を制作した。

中世ファンタジー世界をモチーフにした「ロマンシング サ・ガ」シリーズから、『魔界塔士Sa・Ga』のように複数の世界を渡り歩くシステムに戻ったが、フリーシナリオやひらめきといった仕組みは踏襲している。
また今作から「連携」というこれまたシリーズおなじみの要素が登場。連携に対応した技が前後すると、確率でひとつの技になり、大ダメージを与えることができるという新たなランダム要素が生まれた。「グランドインプロ集中巻き幻魔」といった感じで技名がハチャメチャにドッキングするのも笑えるところだ。

本作の続編が、このたびリマスターされた『サガ フロンティア2』(1999年)だ。今までのフリーシナリオを捨て、ヒストリーチョイスという仕組みを採用し、ふたりの主人公の運命がゆっくりと絡み合っていく様を描いた。
河津のクリエイティブのなかでも屈指の泣けるシナリオになっている。普段は突拍子もない展開や独特なセリフ回しで驚かせてくる印象があるが、筆者含め多くのプレイヤーが良い意味で裏切られたことだろう。

『アンリミテッド:サガ』から2000年代前後のクリエイティブ
1999年は『レーシングラグーン』も発売された年だ。ヤンキー文化と言えなくもないような非常に尖ったテキストセンスと、レースゲームとRPGを掛け合わせたユニークなゲームデザインから、いまだにカルト的な人気を誇る作品である。本作で河津はプロデューサーを務めている。

『聖剣伝説 LEGEND OF MANA』『はたらくチョコボ』『ワイルドカード』など立て続けにスクウェア内のゲームに関わったのち、河津は『アンリミテッド:サガ』に着手する。
本作は彼のキャリアのなかでもずば抜けてピーキーなゲームであり、TRPGのお約束とビデオゲームの面白さを独自の手法で合体させた作品だ。リールを回して連携技を叩き込んだり、ステージの最後にキャラクターの成長の判定があったりと、良くも悪くもオンリーワンな出来で、メディア・ユーザーともにかなり評価が分かれたゲームとなった。
2000年代は『ロマンシング サガ -ミンストレルソング-』や『サガ2秘宝伝説 GODDESS OF DESTINY』など、過去作のリメイクが中心となる。名作を現代の基準でリメイクし、多くの改善点を施した点がファンから好評を受けたが、完全新作までしばしの時間を要するのだった。
一方で、GONZO制作のテレビアニメ「FF:U ~ファイナルファンタジー:アンリミテッド~」の原案や「ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル」シリーズや『ラスト レムナント』のプロデュースなど、サガ以外の仕事にも積極的に注力していた。
ブラウザゲームから『サガ スカーレットグレイス』
2010年代はサガシリーズのブラウザゲームが発売した(世間的にもブラウザゲーム及びスマートフォン向けRPGが台頭した時代だった)。
2012年に『エンペラーズ サガ』、2015年に『インペリアル サガ』をリリース(どちらもサービス終了)。2018年にリリースされた『ロマンシング サガ リ・ユニバース』はいまなお配信中である。
https://www.jp.square-enix.com/saga_reuniverse/
また、2014年には『ロマンシング佐賀』と題して、佐賀県とサガシリーズがコラボするという企画が発足。ダジャレからスタートした企画だが、自治体との緊密な連携により実現した多くのアクティビティを体験できるとして、毎年多くの観光客が訪れている。
そして、2016年、久々に家庭用の完全新作としてPS Vitaで『サガ スカーレットグレイス』が発売。ダンジョンと街が存在せず、世界地図とイベントと戦闘だけが存在するというソリッドなデザインや、タイムライン方式によって行動順がはっきりと可視化されたバトルシステムなど、さらなる進化を見せた作品だ。

ふたり以上の味方に挟まれた敵を倒して味方がくっつくと「連撃」という大ダメージを入れることができるシステムは、まるでおはじきかオセロのようだが、これをいかに作り出すかに苦心するという、唯一無二なセンスが光る名作だった。
滅びた帝国という『ロマンシング サ・ガ2』のセルフオマージュとも取れるロケーションもあり、ファンとして胸が熱くなる展開がある一方で、このころからストーリー展開は輪をかけてランダム性が増していき、読解が難しくなっていった。

『サガ エメラルド ビヨンド』『ロマンシング サガ 2 リベンジオブザセブン』
2024年、サガの新作と大型リメイクが同年にリリースされるという信じられない出来事が起きた。
一作目は完全新作『サガ エメラルド ビヨンド』。『サガ スカーレットグレイス』同様にタイムライン方式を採用したバトルシステムだったが、さらに戦略性を増し、もはや誰も真似できない領域に達していた。

基本的には各キャラクターの放つ技ごとに「連携範囲」というものが存在し、これらを触れ合わせることで連携が行えるので、なるべく味方同士をくっつけて行動できるようにしたいのだが、あまりに敵を孤立させすぎると「独壇場」という大技を放ってくるので、敵味方の位置取りが非常に重要なゲームだ。

じっくり考えて戦いたいシステムである一方で、回復手段をなくすという英断により、一回の戦闘がダラダラと長くならないようにする施策が取られている。このRPGの当たり前を見直し、不必要であればバッサリと切り捨てるあたりが、河津の作品が愛される所以だろう。40年近いキャリアを有していながら、こんなにも目新しい仕組みを入れていくことを恐れないクリエイターが他にいるだろうか?
https://news.denfaminicogamer.jp/interview/240527t
同年には『ロマンシング サガ 2 リベンジオブザセブン』も発売された。こちらは『ロマンシング サガ 2』のリメイク作であり、原作のあらゆる点に改善を施している。
グラフィックスタイルやUIの変更だけでなく、タイムライン方式の採用や、ゲージを溜めて連携する「オーバードライブ」の追加など、現代的で派手だが同時にサガらしい戦闘を確立していた。

特に「アビリティ」といういかにも一般的なRPGによくあるシステムを導入したにも関わらず、それが邪魔をせず、むしろ新たなゲーム体験として考える余地がさらに増えたことが感動的だった。

まだサガに触れたことがないというプレイヤーは、ぜひとも本作から入ることをオススメしたい。
以上、河津秋敏のクリエイティブをまとめてみた。
伝説を作り続け、王道を往きながらも、常に異端であり続けた「サガ」。その歴史は挑戦の連続だった。これからも面白く、そして尖ったRPGを期待したい。
バイオパンク日本神話の世界で同化に抗い、文化をつなげ HIPHOP×ハードコアアクション『SONOKUNI』レビュー
『SONOKUNI』はDON YASA CREWという日本のヒップホップユニットが制作した見下ろし型のハードコアアクションゲーム…