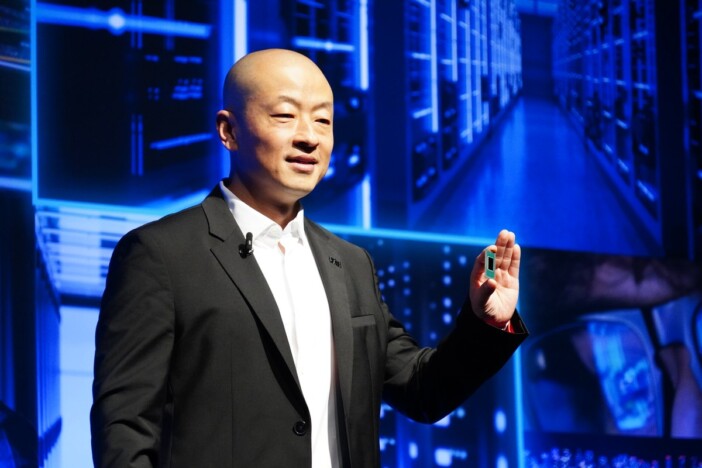「タッチしない」改札に使われているテクノロジーとは? JR東日本の“挑戦”に迫る

ユーザーの位置情報から乗車・降車を検知し、運賃を自動引き落としすることで、「タッチ」動作なしで改札が通過できるというシステム。JR東日本は今後10年で従来のSuicaの仕組みを大幅に進化させていくと表明しているが、そうしたシステムをどのように実現していくのか。モバイル決済ジャーナリスト/ITジャーナリストとして活躍されている鈴木淳也氏に最新動向を解説いただいた。

主に関東首都圏の利用者にはお馴染みのSuica。携帯電話への搭載が2006年1月にスタートしてから、間もなく20年になろうとしている。いわゆる“ガラケー”と呼ばれた時代から、市場はスマートフォンの世界へと変化しているが、この「モバイルSuica」も時代の趨勢に合わせて変化を続けており、JR東日本は近い将来にも「Suicaは首都圏だけのもの」というこれまでの認識を変えようとしている。加えて、「カードやスマホを改札機にタッチする」という従来のスタイルを新技術を導入することで“タッチレス”と変え、例えばスマホをカバンやポケットに入れたまま改札を通過可能な“ウォークスルー改札”を実現しようとしている。
エリア統合でJR東日本のすべての駅をSuicaで利用可能に
まずは従来首都圏など、都市部のみに限られていたSuicaの利用範囲の拡大だ。現在、日本全国で利用されている主要な交通系ICカード(10種類あることから「10カード」と呼ばれる)は相互乗り入れを行っており、例えばSuicaで関西や九州エリアの鉄道をそのまま利用可能だ。一方で、JR東日本が管理している東日本エリアにおいては現在もなおSuicaが利用できない駅が地方を中心に多数存在しており、そうした駅の利用には別途磁気切符を購入するか、現地で運賃の精算が必要になる。
さらに、同じJR東日本の駅であっても“エリア”単位で区切られており、例えば東京から仙台まで新幹線ではなく在来線でSuicaを使って移動しようとしても、両者は異なる“エリア”に属しているため、やはり現地窓口で運賃の精算を行うか、Suicaを使わずに磁気切符で移動する必要がある。こうした不便を解消するため、JR東日本では改札の運賃計算をより複雑な処理が可能なセンターサーバー方式という集中管理方式へと順次変更しており、この移行が完了する2027年春ごろには1枚のSuicaで(JR東日本の営業範囲であれば)どこへでも移動できる“エリア統合”を実現する計画だ。

ここで気付いた方もいるかもしれないが「Suicaで主要都市の間を移動できるようになっても、途中にはSuicaで入出場できない無人駅もあるし、全部の駅は対応できないんじゃないの?」という疑問が当然、沸いてくるはず。以下の写真にあるような簡易改札機がある駅ならいざ知らず、そもそもSuicaがまったく利用できない駅が多く存在するわけで、こうした駅でも問題なくSuicaの仕組みを利用できるようにすべく、JR東日本ではスマホに新たに「Suicaアプリ」を提供することでこの問題を解決しようとしている。それが、ロードマップの「今後10年以内」の部分で予告されている「位置情報等」を活用した入出場システムだ。

JR東日本ではSuicaの残高管理やチャージ、定期券・特急券等の購入に特化した従来のモバイルSuicaアプリをもう一段進化させ、より高度な機能を提供できる「Suicaアプリ」を2028年度にもリリース予定だ。指定駅からの運賃が割り引きになるサブスク型のサービスや各種クーポン配信機能がSuicaアプリで新たに提供されるサービスとして例示されているが、それ以外にも同アプリを通じて「ウォークスルー改札」や「位置情報等」による改札の入出場が将来的に可能になるとみられる。
まだ未提供の機能なため正確な部分は分からないが、「位置情報等」については「Suicaに未対応の駅において、スマホの位置情報を使って入出場が可能になる仕組み」だと考えて問題ないだろう。理由としては、JR東日本が昨年2024年10月1日に提供を開始した「Qチケ」という仕組みで同様の機能がすでに実装されているからだ。「Qチケ」とは「えきねっと」アプリで提供されている、QRコードを活用した電子切符(チケットレス)の仕組みだ。アプリ上で指定区間の切符を購入可能で、従来は新幹線や特急券に限定されていたものが、Qチケの提供により在来線での利用が可能になった。本稿執筆時点ではまだ東北エリアに限られるが、駅の改札機にあるQRコードの読み取り機にスマホに表示させたQチケのコードをかざすことで改札を通過できる。

ここでまた疑問に思われた方がいるかと思うが「(QRコード読み取りができる)改札機のない駅はどうするの?」という問題が当然上がってくる。そこで登場するのが位置情報だ。Qチケで改札機のない駅へとやってくると、チケットの利用終了または利用開始を行うためのボタンが「えきねっと」アプリ上に出現する。これはスマホの現在位置と駅が一致するかをアプリ側でチェックしており、当該の駅に到達した段階でこの操作が可能になる仕組みだ。利用者自らが操作する必要があるが、ここで必要な操作を行っておかないと、例えば改札機のない駅を起点に別の駅に移動したとき、「入場記録がありません」ということで駅の改札機で止められてしまう。
“ついうっかり”が理由でトラブルに発展する可能性があり、仕組みとしてはやや微妙なのだが、今後Suicaアプリが正式に提供され、「位置情報等」による入出場の仕組みが一般化すれば、こうした操作もある程度自動で行ってくれるよう改良される可能性が高く、将来的に「スマホ1台あれば(JR東日本の駅を)どこでも自由に移動できる」ようになるための布石と考えておいていいだろう。