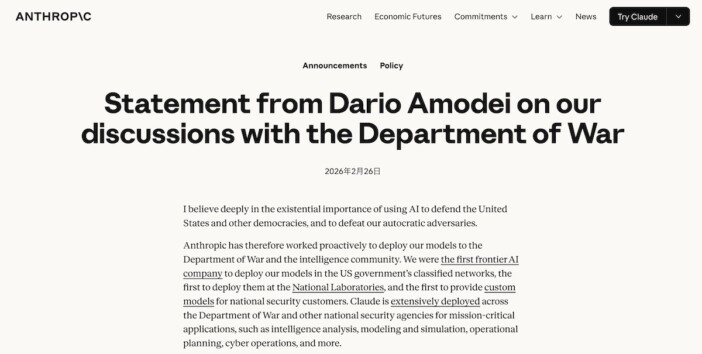『ペーパーマリオ』に潜むメタ構造 『オリガミキング』で崩壊した物語を考える

「ペーパーマリオ」シリーズが誕生してから、もうすぐ20年を迎えようとしている。シリーズ第1作『マリオストーリー』から同シリーズをプレイしている筆者にとっては、非常に感慨深い。紙のようにデフォルメされたペーパーマリオが冒険に出るという設定ではあるが、実は『マリオストーリー』の時点では「ペーパーマリオ」という呼び方は浸透していなかった(恐らく存在すらしていない)。
『マリオストーリー』における“紙っぽい世界観”は、あくまでもマリオたちのいる世界が「絵本の世界」であることを強調するための演出に過ぎなかった。それがシリーズ第2作『ペーパーマリオRPG』において「ペーパーマリオ」という名前が公式に定義され、以降の作品ではマリオが紙飛行機に変身したり、あえて3D視点でペーパーマリオを描写したりするといった、マリオ自身が「紙」であることを活かしたアクションが増えていく。
この「紙」という性質自体を活かす演出は、第4作『ペーパーマリオ スーパーシール』以降でより顕著となり、キャラクターだけでなくゲーム内の土地や建物も、ペーパークラフトのようなもので表されるようになった。
この流れは(メタ的に見れば)マリオたちが自分たち自身、ひいてはその世界さえも、紙で作られた絵本の世界に過ぎないと自覚するようになっていった過程であると解釈できる。シリーズを重ねるにつれて頻出するようになった、自らが「紙」であることを自己言及するブラックジョークにも、そのことが象徴されているだろう。「ペーパーマリオ」はそのゲームシステムが進化していくにつれて、絵本の住人たちがその世界構造を把握していくという(メタ)物語を展開してきたのだ。
このような(メタ)物語を経た最新作『ペーパーマリオ オリガミキング』で描かれたものとは何か。今作で描かれるのは、マリオたち「ペラペラ」な生き物と、「オリガミ」との対立だ。あるきっかけで人格を宿した「オリガミ」の王・オリーは、自らを道具として扱う「ペラペラ」なキノピオたちに怒りを覚え、彼らを消し去るためにピーチ城を襲う。
オリー王の復讐の動機は(過度に)コミカルな演出で描かれるが、これを簡単に見過ごすわけにはいかない。なぜなら(過去シリーズでマリオたちが自覚したように)元々「オリガミ」(=紙)こそが世界を構築しているのであって、マリオやキノピオは紙に生み出された絵本世界の構成要素に過ぎないからだ。そのキノピオに道具扱いされたオリー王が怒りを覚えるのは、ある意味当然と言える。
そんなオリー王の脅威を阻止するため、マリオは世界各地を冒険する。ボム兵やキノピオといったお馴染みの仲間と協力しながら、オリー王の構えるピーチ城に向かう。物語の終盤でオリー王を滅ぼしたマリオは、彼の支配下にある「オリガミ兵」たちから人格を消し去り、「ペラペラ」の世界に平和をもたらすのだった、というのが今作のあらすじだ。
ここで注目したいのは、マリオたち絵本の住人が「オリガミ」(=紙)に勝利したことの意味だ。今作のラスボスが、絵本(紙)の中で用意された敵ではなく、紙自体だったことの意味は何か。
マリオたちが「オリガミ」に勝利したことは、彼ら/彼女らが絵本世界を自由に書き換えられるようになったことを意味する。つまり紙に生み出されたマリオたちは紙に勝利し、その力を支配することで世界そのものをもコントロールできるようになったのだ。ゲームの操作中、プレイヤーが「オリガミ」の破片(=「カミッペラ」)を使って建物を修復したり地面をふさいだりできるように。マリオたちは紙に支配される側から、紙を利用し世界を記述する側へと生まれ変わったのだ。
そう、20年の時を経てマリオたちは絵本の紡ぐ物語(と、それを過度に期待する自称古参ファン)から解き放たれ、自らの生きる世界を自らの手で記述できるようになった。そしてこのような世界観は、ある一点において、将来ありえるかもしれない現実の世界観と共通している。