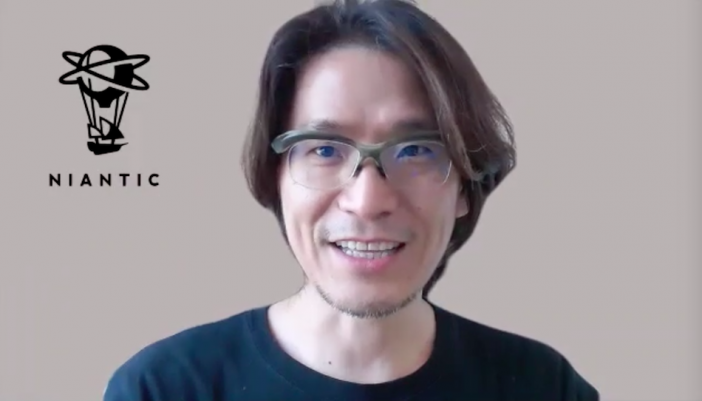【ネタバレあり】『The Last of Us Part 2』は、映画を最も震え上がらせるーー映画評論家・小野寺系が“問題作”の可能性を考える

ラストシーンが示すジョエルたちの勝利
そこで、エリーはジョエルとの、ある会話を思い出し、復讐を断念することになる。なぜ、エリーはここまできて復讐をやめたのか。この場面にフラストレーションを感じたという批判的な声もあるが、前述したように、エリーはすでに正常な判断を失っている状態なのである。そして、ここで復讐を遂げたとしても、彼女の心は救われることがないはずなのだ。それは、ジョエルとの会話シーンで示されている。
世界を救う役割を果たすことを阻止し、生きる意味を剥奪されたと感じていたエリーは、ジョエルに対し長い間怒りを募らせていたが、そのことを赦したいと思っていると、会話のなかで語っていたのだ。しかし、その翌日にジョエルが殺害されたことで、エリーはジョエルに怒りをぶつけたことを謝る機会も、赦す機会も、永遠に奪われてしまった。そう、エリーの心を救うことができるのは復讐の完成ではなく、ただジョエルを赦し、同時に贖罪することだけだったのだ。
いま目の前にいるアビーは、もはや憎むべき悪魔ではなく、ただ大事な人間を守るために必死になっているだけの存在である。それは、まさに昔のジョエルそのものではないのか。エリーは、彼女を赦し、解放することで、この旅が始まってから唯一、他人の幸せのために行動する。それは、エリーの心を救うために必要な、ジョエルを赦す行為そのものであるといえよう。しかも、アビーはファイアフライの活動に戻ろうとしていた矢先でもある。彼女を助けるということは、ジョエルがファイアフライに対して行った罪のささやかな償いになり、アビーの父親への贖罪にもなっていたのである。
その意味で、本作は前作のラストをより正しい結末へと更新したことになるのではないだろうか。エリーは、最後の最後に成長し、善良さを取り戻す。そしてそれは、ジョエルの彼女への深い想いが、ついにエリーの心へと届いた瞬間でもある。この結末は、地獄を通り抜けた先にたどり着いた、エリーの勝利であり、アビーたちの勝利であり、ジョエルの勝利なのである。そのことを感じることができれば、本作をプレイしてきたことに深い達成感が与えられるはずだ。
そして本作は、エリーの犯してきた罪についても、一定の決着をつける。それが、二本の指の代償と、愛する人たちとの別れである。エリーが弦を押さえられず、満足にギターを弾くことができなくなった場面は悲痛だが、その後、ギターを置いて一人で歩き出す描写には希望がある。エリーは多くの代償を払い、多くの罪を背負いながらも、ついにジョエルに庇護されていた少女の頃の自分と決別し、成長した大人として初めて自分の人生を取り戻したのである。
一本道だからこそたどり着いた境地
本作は、少なくとも筆者が知る限り、最も人間や人生を深く描ききったドラマを持つゲーム作品であり、前作と比較しても芸術性が高く、作り手の意志が前面に出た作品といえる。これが問題になるとすれば、ゲームにここまでの作家性が必要なのかという議論だろう。
実際、本作に寄せられた批判のなかには、キャラクターが非道な行動をすることを止められず、強制的に殺しに加担させられることへの不満も多い。キャラクターの決断をプレイヤーにまかせ、複数の結末を用意するマルチエンディングにすべきだったという意見もある。
だが筆者としては、本作の素晴らしいドラマと、考え抜かれた美しいエンディングを理解した後に、いまさらマルチエンディングなどを体験したいとは思わない。レベルの高い多くの文学作品や映画の脚本は、ドラマのあらゆる描写を結末と関連づけて描くものであり、読者や観客の気にいるラストを複数用意し、気に入ったものを選ばせるということは基本的にしないものである。そこには、作り手の意志を尊重する文化と歴史があるからだ。
もちろん、マルチエンディングというシステムそのものが悪だというつもりはない。しかしゲーム作品では、このような意見が出てしまうことからも分かるように、比較的作り手の作家性というものが尊重されてないのは確かであろう。もっといえば、“芸術作品”として扱われていないということだ。
なぜ、このような話をするのかというと、『The Last of Us Part II』というゲームが、娯楽作品としての魅力を持ちながらも、紛れもなく文学や映画に匹敵する、堂々たる芸術作品だと感じるからだ。しかも、本作はプレイヤーに行動を強制することで、キャラクターの決断を追体験させるという、ゲームならではの強みをも発揮しているのである。
これまでも映画は、ゲームの急激な成長に脅かされる場面があった。そのなかで本作は、映画という媒体を最も震え上がらせるものだったと感じるのだ。それは、プレイヤーへのサービス精神よりも、一本道のシナリオを極限まで洗練させ、妥協なく作家性を押し出したからこそ到達し得た境地なのではないのか。
ゲームは、やりようによっては、名作文学や巨匠の映画作品といった古典を超え、人類最大の芸術に到達する可能性のある分野になり得る。予想される批判を覚悟したうえで、そして巨費を投じた制作体制で、このような挑戦的な姿勢を貫き、その可能性を十分に見せた功績は、特筆に値する。今後、ゲームがどのように進化していこうと、本作は革命的な傑作として歴史に残るタイトルになるのではないだろうか。その内容の成功に、そして強い意志に、いまは最大限の賛辞を贈りたい。
付け加えとなるが、本作でのLGBTについての表現に対し、「ポリコレへの配慮のし過ぎ」だという、程度の低い批判も存在する。作り手たちはその反応を事前に予期しており、劇中でエリーとディーナのキスする様子を見て文句をつけ出す保守的な男性を登場させている。その姿が批判者そのものの姿である、という皮肉に気づくべきだろう。
■小野寺系(k.onodera)
映画評論家。映画仙人を目指し、作品に合わせ様々な角度から深く映画を語る。やくざ映画上映館にひとり置き去りにされた幼少時代を持つ。Twitter/映画批評サイト