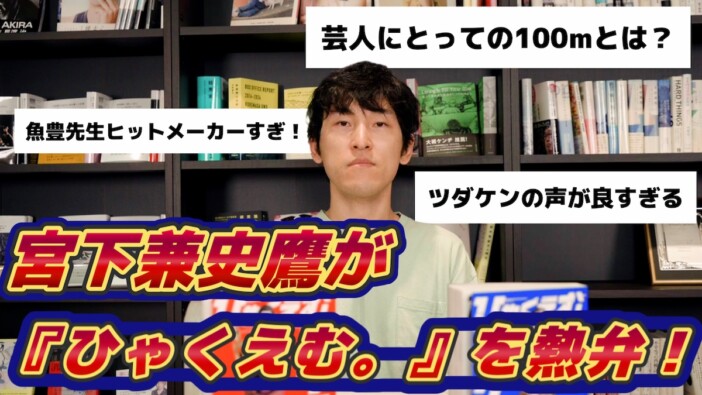『ひゃくえむ。』と『チ。』は“たった一文字”でつながる 追求する者たちの孤独とカタルシス

これだけアニメーションが“文化”として根付いてきたなかでも、「なぜこの物語をアニメーションで描いたのだろうか」と考えてしまうことはしばしばある。原作が漫画であれ、小説であれ、はたまたオリジナルであれ。作り手がアニメの人だからとか、商業的なメリットなども一旦置いておき、もちろん実写とアニメのどちらかに優劣をつけるというわけでもなく、あくまでも一本の作品の表現の選択肢として。
魚豊の同名マンガをアニメ化した『ひゃくえむ。』は、“100m走”に全身全霊をかける者たちを描いた物語であり、その舞台は決して特異な世界でもなく現実に存在しうるものだ。陸上競技を題材にした実写映画もこれまで数えきれないほど存在している以上、実写とアニメどちらの選択肢も存在していたはずだ。だがおそらく、この物語はその“どちらか”だけで描写するのは難しかったはずだ。

己の肉体と精神力をフル稼働させて100mという距離を全力で駆け抜ける人物の躍動。その時点での風向きにかかわらず空気を切り裂いて進むがゆえの風の抵抗。歯を食いしばり、目をひんむいて、誰よりも――それは隣のコースを走る者だけでなく、過去の自分自身も含まれる――速く走ることを渇望する表情。この美しさと醜さを共存させたデフォルメに対して見出されたのが、古くからあるロトスコープ――すなわち実写を基にしてアニメーションを生みだす手法というのは非常に興味深い。
これによって実現した生々しいまでの躍動は、“走ること”という極めてシンプルなアクションだけで幾多のドラマを作りだしていく。生まれつき足が速いトガシと、彼との出会いで速く走ることに目覚める小宮の小学生時代から、離れ離れとなった後に陸上競技者として再会する高校時代、そして苦節を乗り越えて社会人選手となって迎える両者の再戦。登場人物たちの心理的な揺らぎも解放感も、各々の時代をつなぐ役目もすべて“走ること”が担う。ひいては、走らなければこの登場人物たちは誰一人として出会うことがないのである。

ひとつの主題をめぐって複数の登場人物がめぐりあい、時代を超えて共鳴する。その構成は、同じ魚豊の『チ。-地球の運動について-』とまるで一緒である。同作では異端審問館のノヴァクなどごく数名の登場人物が時代をまたぐが、章立てごとに主人公は代わり、地動説を追究する者たちと信仰とのせめぎ合いで一貫性はあるものの、物語の運ばれかたは今作と異なっている。それでもなにかを追求することで味わう不安、周囲との隔絶によってもたらされる孤独感、そしてその先に訪れる、自らの手足によって切り拓くカタルシスは通じているといえよう。