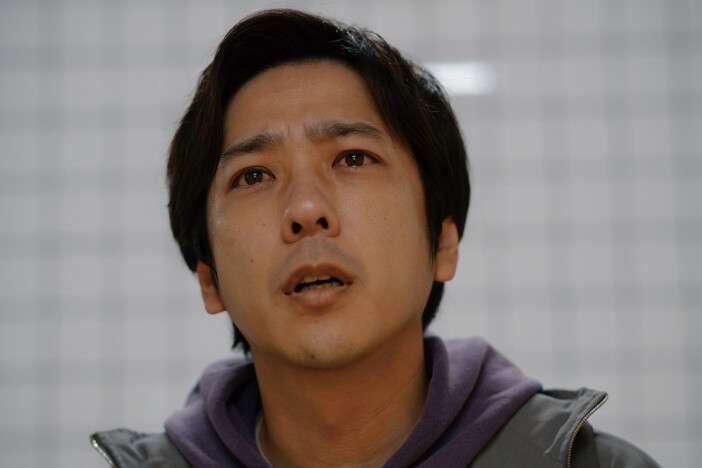『8番出口』は“映画ファン”こそ必見 達人揃いのスタッフ・キャストが作り上げた最適解

「当たるべくして当たった映画」を観ている、そういう清々しさが『8番出口』にはある。
巷で話題を呼んだインディーゲームを原作にした企画段階で、すでにヒットする可能性はある程度は担保されていたのかもしれない。だが、本作の場合、何よりその料理の仕方が非常に優れていた。
映画ならではの脚色を施しつつも、原作ゲームのシンプリシティを尊重し、無駄なことは極力していない。脚色するにしても「原作同様シンプルに」とどめている。これは「何かと付け足しがち」もしくは「見当違いな当たる要素」を持ち込みがちな日本映画では非常に珍しい。

監督の川村元気は、ヒットメイカーとして定評のあるプロデューサーとしての感性と分析眼を、本作でフルに発揮した。つまり、原作の良さはなんだったのか、なぜヒットしたのかという勘所をしっかり理解し、そのうえで自身の主戦場である映画界のヒットの法則も投入。さらに、前述の「見当違い」に陥りかねない要素も、注意深く排除している(たとえば「話題のアーティストによる主題歌」みたいなことだ)。
上映時間95分ということは、映画館では早朝上映からレイトショーまで含め、客出し・清掃・客入れ・予告編の時間を合わせても、1スクリーンだけで1日6~7回は上映できる。もちろんそれは興行収入に直結する大事な要素である。おそらく映画作家としての「何か付け足したい」欲望とも戦いながら、川村は興行のプロとして、エンターテイナーとして、コンセプチュアルなエンタテインメントとしての完成度の高さを実現してみせた。なかなかの偉業だと思う。
それでも、ヒューマンドラマ志向という作家性は滲む。下世話な言い方をすれば「万人の心を打ちたい」「泣かせたい」という欲望も、このヒットメイカーの個性であり素質のひとつであろう。だが、今回はそれを前面には出さず、物語のスパイス程度に抑え、不条理ホラーの容貌をとった現代の寓話としてまとめ上げた。「家庭を持つことの不安から逃れられない」「出口を求めながらも未知の外界に飛び出していくことを恐れる」現代日本人の肖像を、巧みにストーリーの核心に取り入れたシナリオが秀逸だ。

隠し味ではあっても、老若男女すべての観客層にわかりやすいドラマの根幹部分だけを際立たせる語りの巧みさは、同じく東宝配給のメガヒット作『国宝』(2025年)の「わかりやすさの魅力」も思い起こさせる。そのバランス感覚もヒットメイカーならではの手腕といえよう。
ループ構造という独特の展開も、ともすれば「退屈さ」を誘発しそうだが、その轍は、主に映像テクニックの面白さによって巧みに避けられる。特に前半に集中する擬似POV・擬似長回しといった手法は、FPSゲームやモキュメンタリー・ホラーとも通じるもので、ジャンルについての素養や知識の有無にかかわらず、まず生理的に不穏なムードを否応なく盛り上げる。同時に、ゲーム=物語のルール設定も必要最低限の描写で、序盤のわずかな時間で処理しているのも見事だ(この不条理なルールに、主人公が意外にすんなり従ってしまうところも、いまの日本人の悲しさを体現しているようにも見える)。