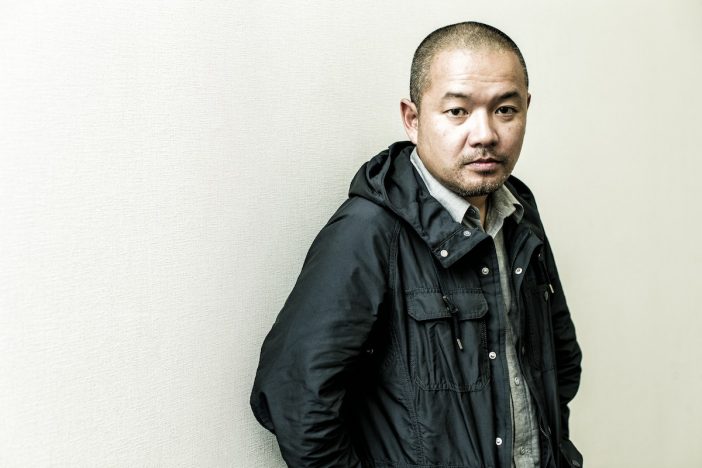『魔女がいっぱい』が子どもにとって恐ろしい内容になった理由 原作やニコラス・ローグ版から分析

あのアン・ハサウェイが凄まじく凶悪な魔女を演じることで話題の映画『魔女がいっぱい』は、児童文学を基にした娯楽大作だ。本作の見どころは、アン・ハサウェイが演じる“大魔女”をはじめとして、とにかく恐い“魔女がいっぱい”登場するところ。子どもを中心に楽しませる映画としては少々恐ろしい内容だが、なぜ本作はそのような内容になっているのだろうか。

原作者は、イギリスで小説やシナリオなど数多くの魅力的かつ斬新な物語を書き上げ、児童文学界の巨匠でもあったロアルド・ダール。二度も映画化された児童文学『チョコレート工場の秘密』をはじめ、『ジャイアント・ピーチ』(1996年)、『ファンタスティックMr.FOX』(2009年)、『BFG:ビッグ・フレンドリー・ジャイアント』(2016年)と、彼の作品を原作とする映画がこんなにも多いことが、その支持の大きさを裏付けている。
そんな映画を手がけたのは、スティーヴン・スピルバーグやティム・バートン、ウェス・アンダーソンなどの大物監督たちだった。日本でも『魔女がいっぱい』の原作が『おジャ魔女どれみ』の創作上のヒントになっていたり、宮崎駿監督が描く魔女のキャラクターにも影響を与えていると見られるなど、後の創作に与えたインパクトは計り知れないものがある。
今回、ロバート・ゼメキス監督によって映画化された、1983年発表の児童文学『魔女がいっぱい』も、そんなロアルド・ダールの作品群の一つであり、『ジム・ヘンソンのウィッチズ/大魔女をやっつけろ!』(1990年)という先行作品も存在する。しかもその監督は、『美しき冒険旅行』(1971年)や『赤い影』(1973年)などの奇才ニコラス・ローグである。この、ロアルド・ダールの原作やニコラス・ローグの映画版を手がかりにすることで、本作『魔女がいっぱい』のやりたかったことが、より詳細に見えてくる。

原作では、イギリスとノルウェーを舞台に、両親を亡くして祖母に育てられることになった少年を主人公としている。今回の映画版の設定上の特徴は、舞台をアメリカのアラバマ州に移し、主人公をアフリカ系アメリカ人の少年に変更したところだ。そのことで、作品には人種差別や、人種問題をベースとした経済格差の問題が含まれることになった。とはいえ、本作は大筋で原作を忠実になぞっているため、そのような要素を深く掘っていくような内容にはなっておらず、あくまで一つの要素になっているだけだ。
だが、最近もBLM(ブラック・ライヴズ・マター)運動が盛り上がりを見せたアメリカにおいて、この設定変更は、様々なものを想起させることになったのは確かだろう。本作で「魔女は貧しい子どもを狙う」と述べられるように、アメリカで比較的弱い存在とされているのが、アフリカ系やアジア系、中南米出身者などの有色人種だ。ならば、子どもを始末しようとする魔女が目をつけるのは、人種的なマイノリティである場合が多くなるはずである。そして、そのような子どもが行方不明になったとしても、世間はさほど興味を持ってくれないかもしれない。そういった意味で、ある場所におけるある種の属性というのは、命のリスクも同時に引き受けることになってしまうのである。
少年を育てることになる祖母を演じているのが、オクタヴィア・スペンサー。この祖母の励ましによって少年が両親の死を乗り越えていく描写は非常にエモーショナルだ。なかでもモータウンのナンバーをレコードでかけながら陽気に踊り、少年に手を伸ばすシーンが感動的である。だがさらに小道具としてフライドチキンやコーンブレッドなどのアフリカ系アメリカ人のソウルフードとされる代表的な食べ物が登場するなど、アフリカ系の文化が記号的に提示されすぎていると感じられる部分もある。

作中の描写でより問題視されたのは、アン・ハサウェイたちが演じた魔女の容貌だった。もともと原作でも、その姿は怪異なものとして表現され、裂けた口と“かぎ爪”が特徴の怪物として描かれていたし、ニコラス・ローグ版でも『セサミストリート』や『ダーククリスタル』(1982年)などで人形やクリーチャーのデザインを担当したジム・ヘンソンによって、世にも恐ろしいものとして表現されていた。だが本作では、両手の指が三本という独自の描き方をしている。これが差別的だと、障害のある俳優やスポーツ選手などから非難されることとなり、演じたアン・ハサウェイが謝罪する流れとなった。
本作がそのような偏見を広めようとしていたとは考えづらいし、このような表現を擁護する声もSNSでは見られるが、見た目の異なる身体の部位を怪物であるかのように描いたと受け止められたり、この表現が差別の原因となる可能性があることは否定できない。その意味で製作者が反省する部分は多いといえる。