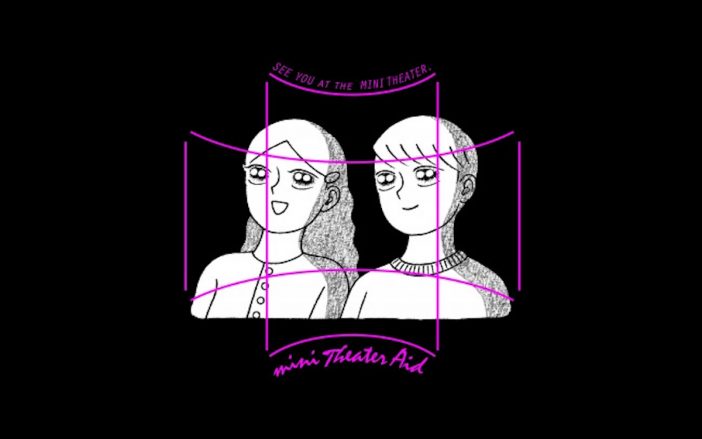大林宣彦監督が映画界や社会に遺したもの その“フィロソフィー”から何を学ぶべきか
大林宣彦監督が、2020年4月10日に肺がんで亡くなった。『HOUSE/ハウス』(1977年)で長編映画デビューを果たして以来、日本でブームを巻き起こした『時をかける少女』(1983年)を含める、故郷を舞台にした「尾道三部作」など、最新作にして遺作となった『海辺の映画館―キネマの玉手箱』まで、継続して多くの話題作や、個性的な映画作品を撮り続け、日本映画界で長く輝きを放った映画監督だ。

しかし、大林監督はなぜそんなに長く時代を生き残ることができたのだろうか。ここでは、印象的な業績と、その作家性を振り返りながら、監督が映画界や社会に遺したもの、そして受け継がれるべきものについて考えていきたい。
子ども時代の大林宣彦は、港町である尾道の家の蔵のなかに、フィルムや映写機があることを発見し、フィルムに絵を描いて遊んだり、切ってつないで編集しているうちに、映画製作を身体で覚えたという稀有な経験を持っている。そして、成城大学に入学した青年期以降は、映画スタジオや映画学校で徒弟的な映画づくりの伝統を覚えるのでなく、代わりに赤瀬川源平やオノ・ヨーコ、そしてドナルド・リチーなど、当時の若い前衛的なアーティストたちと親交を持って映像製作に取り組み、CMディレクターとなって第一の成功を収めている。
劇場長編の第1作となった『HOUSE/ハウス』は、そんな大林監督の前衛的な野心や、子どもの頃の遊び心が最も強く発揮された作品だろう。あらゆる特殊効果を用いたり、しきりにフィルムを逆回転させたりと、とにかく遊びに遊んだ映像で、従来の映画ファンのなかでは不評を買った部分もあったが、当時はこのようなCM、ミュージックビデオのようなポップな表現は斬新なものだった。この作風は、その後の大林作品においても重要なものとなっている。
それは、重厚な“映画らしさ”からは、一見離れているように感じられる。だが、同時に“映画らしさ”とは何なのかという問いも、そこに生まれてしまうのだ。現在の国内外のいろいろな映画作品を観ていると、特殊効果や凝った編集技術はいまや当然のように使用されている。それもまた映画の魅力の一部だったのである。大林監督は、そのような未開拓の分野に切り込んで、当時の日本映画に新しい風を吹き込んだ代表的存在だったのだ。
このような役割は、かつて巨匠・市川崑監督が担っていた。市川監督は大林監督のふた回りほど上の年代で、アニメーション製作と実写映画の両方を手がける、当時としては珍しい監督だった。市川監督が、いかにも職人の監督やスタッフによって占められる、美術や撮影において随一といえる技術を持った大映のスタジオに招かれたとき、当初ベテランのスタッフたちは「漫画屋がきた」と陰で揶揄し、市川監督の指示に難色を示すこともあったという。
だが、市川監督のアニメーションと実写を融合したような斬新なセンスは、新しい個性を大映にもたらし、日本の映画界に次々に新しいアイデアを加えることになった。そして、その後の東宝での活躍を含め、2000年代にもみずみずしい感性を保ち作品を発表し続けた。時代への対応を可能にした理由のひとつは、従来の重厚な映画の魅力と表層的なデザインセンスの2WAYを自在に引き出すことのできる能力である。