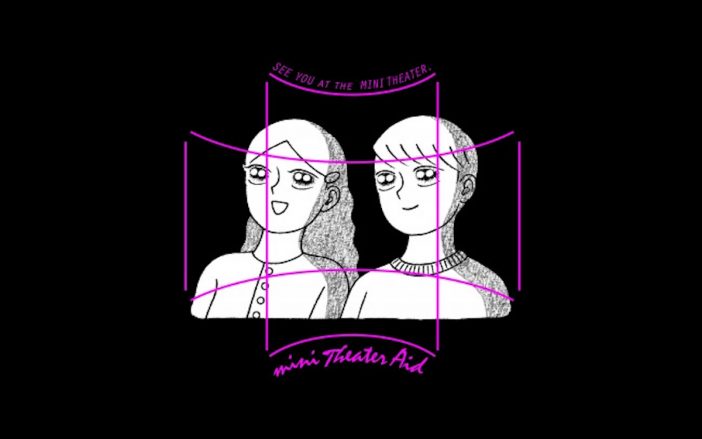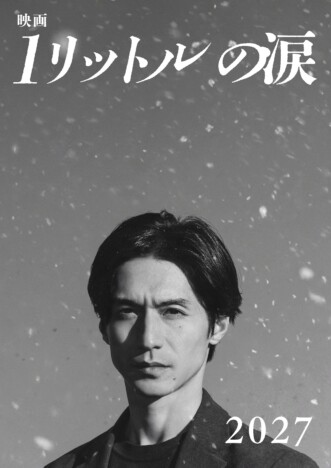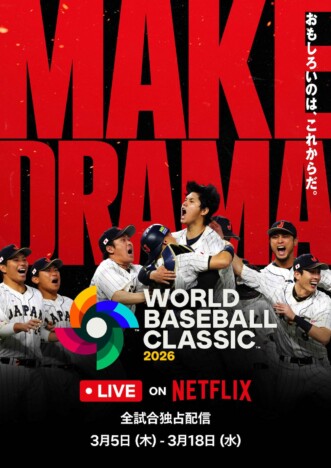大林宣彦監督が映画界や社会に遺したもの その“フィロソフィー”から何を学ぶべきか
大林監督も、そのようなふたつの能力を身につけていく。芸術映画を製作するATGでの作品『廃市』(1983年)では、福岡県柳川の運河を舞台に、これまでのポップな作風ではなく、しっとりとした文芸映画そのものの作品を仕上げたように、繊細な演出で押し切るだけの力があることを見せつけることになる。
『廃市』は高い評価を得ている作品だが、筆者は不満を覚える部分もある。それは、大林監督らしい遊びが見られない点だ。このような作品は、大林監督以外の監督でも手がけることが可能なのではないのか。

一方、『時をかける少女』などの「尾道三部作」は、尾道の古い家並みを印象的に切り取りながら、ポップさと文芸的な雰囲気を重なり合わされている。そして、大林監督ならではの、水と油が分離したまま混在するかのような不思議な魅力と、強烈な個性を放つ作風が出来上がっていったのである。
市川崑監督が、いつまでも時代に対応し続けられた大きな理由は、もうひとつある。それは、目先の流行に左右されず、自分の考えを大事にしたところだ。『子猫物語』(1986年)など、いくつかの映画で市川監督と仕事をした詩人の谷川俊太郎は、市川監督は哲学性を大事にしていたと述べている。映画で谷川の詩を使用するとき、それを採用するかどうかの基準は、耳障りのいい言葉や華麗なレトリックがあることでなく、そこに作品に関連した深い哲学があるかどうかを重要視したというのだ。市川監督は、役者のアドリブを極度に嫌った。それは練り込まれたセリフのなかに、自分の哲学的意図を染み込ませていたからなのだ。
大林監督は、NHK Eテレの番組『最後の講義』のなかで、若い学生たちに向け、もし自分の人生最後の日に伝えたいことがあるなら何かという題に対して、奇しくも「映画はフィロソフィー(哲学)である」と発言している。何より、まずはじめに伝えたい哲学があり、それをどう伝えるのかが技術なのだと。
晩年、大林監督は『この空の花 長岡花火物語』(2012年)や『野のなななのか』(2014年)など、『HOUSE/ハウス』の頃に戻ったような強烈な演出で、ストレートに反戦を訴える作品を手がけ続けることになった。大林監督が何としても観客に伝えたいと思った哲学は、戦争にまつわる、政治性を色濃く反映したものだったのだ。
著書『大林宣彦 戦争などいらない‐未来を紡ぐ映画を』(平凡社)のなかで、大林監督は、日本アニメーション界の巨匠・高畑勲監督との晩年の交流について、このように述べている。
「高畑さんとは旧知の仲でしたが、同志ともいえるほど仲良くなったのは、二〇一四年に、高畑さんは『かぐや姫の物語』、ぼくは『野のなななのか』で日本映画功労賞をいただいた席でご一緒してからです。帰りに久々に食事でもしましょうかねとなって、お互いに何となく「うかつでしたね。うかつでしたね」という言葉が出てきました。「ぼくたちがあまりにもうかつで、この国が戦争をすることはもう二度とないだろうと思っていた。うかつにも高をくくって、意識的ノンポリとして生きてきた。そのことが日本をまた戦争に向かう国にしてしまった。これはぼくたちの責任だね」と話し合いました。それから高畑さんとぼくは離れがたいパートナー意識で共に生きてきたんです」
じつは大林監督は、『HOUSE/ハウス』の時点で太平洋戦争の要素を出していた。その後も商業作品のなかで、原爆のイメージを使うなど、戦争の惨禍を扱ってきたのは確かなのだ。しかしそれは、晩年の大林監督にとっては「うかつ」なことだったらしい。