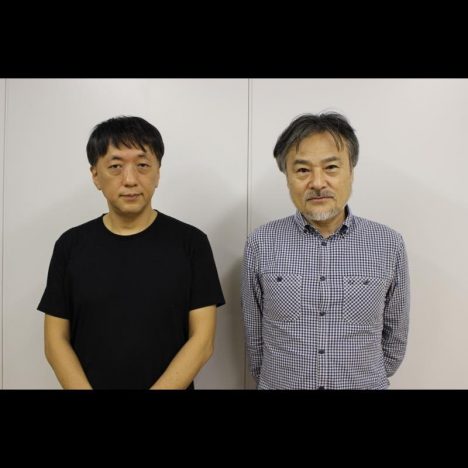宮台真司の月刊映画時評 第10回(前編)
宮台真司の『愛しのアイリーン』評:「愛」ではなく「愛のようなもの」こそが「本当の愛」であるという逆説に傷つく体験

愛のようなものの絶対勝利
「駆り立て連鎖」は、食物連鎖を考えれば思い半ばに過ぎるように、大概は一方向的です。それは一方的な「贈与」や「剥奪」として現象するだけで、双方向的な「交換」はむしろ例外的です。だからこそ、映画のどこかで「贈与」や「剥奪」ならぬ「交換」が描かれれば、観客の身勝手な視座=人間的視座にとっては、大きな救いになるでしょう。
この映画が原作と大きく異なるのはラストシーンです。有名な原作なので御存知でしょうが、原作では、アイリーンを訪れた一方的な「剥奪」(ないし「贈与」のしっ放し)は、子供の誕生という「反対贈与」によって報われます。吉田恵輔監督は恐らくは迷った末、映画からこの反対贈与という交換を、明確には子供を描いていないという意味で除去しています。
かつてのハリウッド映画なら、プロデューサがこの除去を許さないはずです。そうした除去が、カタルシスを抑止することで、仲間や恋人や家族と一緒に訪れた観客たちに「いい映画だったね」といった会話を禁じてしまうからです。この映画がそうした会話を可能にしていたら娯楽映画で終わっていました。
しかし、実際には娯楽映画では終わりませんでした。そのことで、観客の心に回復不能な傷をつけるアートに昇格しました。「贈与」も「剥奪」も報われることがないという存在界の摂理──<社会>という間接化装置に普段は覆い隱された<世界>の実態──に、無理矢理に直面させられる体験。それが回復不能な傷を与えるのです。
それが回復不能になるのは、観客たちが既に存在界の摂理を知っているからです。知っているのに「見て見ぬフリ」をするのは、<社会>を──<社会>によって間接化された<世界>を──安心して生きるためです。でも、「本当の愛」(と敢えて呼べば)は、「交換」を旨とする安心安全な<社会>のなか=法内に、あるのでしょうか。吉田恵輔監督の問いです。
思えば、今日のドラマや映画で「愛」として描かれるものは、所詮は無害な「交換」のロジックの内側にあり、到底「本当の愛」だとは思われません。この映画に描かれた「愛のようなもの」は、意図せず巻き込まれた一方的な「駆り立て連鎖」そのものであり、一方的な「贈与」と「剥奪」に耐えるがゆえに「本当の愛」を導くのです。それは私たちに可能でしょうか。
[この文章は劇場パンフレットに寄せた文章の大幅増補版です]
※吉田恵輔監督の「吉」は土よし
■宮台真司
社会学者。首都大学東京教授。近著に『14歳からの社会学』(世界文化社)、『私たちはどこから来て、どこへ行くのか』(幻冬舎)など。Twitter
■公開情報
『愛しのアイリーン』
全国公開中
出演:安田顕、ナッツ・シトイ、河井青葉、ディオンヌ・モンサント、福士誠治、品川徹、田中要次、伊勢谷友介、木野花
監督・脚本:吉田恵輔
原作:新井英樹『愛しのアイリーン』(太田出版刊)
音楽:ウォン・ウィンツァン
主題歌:奇妙礼太郎「水面の輪舞曲(ロンド)」(WARNER MUSIC JAPAN/HIP LAND MUSIC CORPORATION)
企画・製作:河村光庸
製作:瀬井哲也、宮崎伸夫
エグゼクティヴ・プロデューサー:河村光庸、岡本東郎
プロデューサー:佐藤順子、行実良、飯田雅裕
企画・制作・配給:スターサンズ
製作幹事:VAP
制作協力プロダクション:SS工房
レイティング:R15+
(c)2018「愛しのアイリーン」フィルムパートナーズ(VAP/スターサンズ/朝日新聞社)
公式サイト:http://irene-movie.jp/