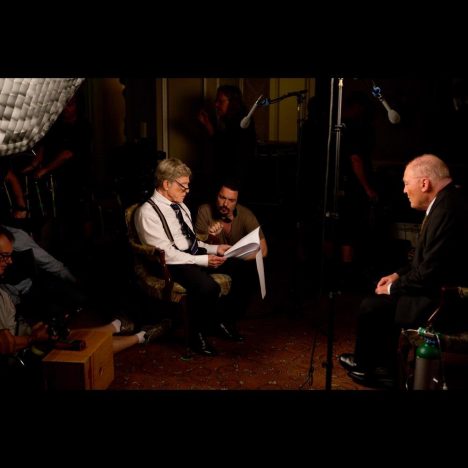宮台真司の月刊映画時評 第8回(後編)
宮台真司の『ニュースの真相』評:よく出来た映画だが、トランプ現象の背景を捉えきれない

<技術による人間解放>の初期的な流れ
ところで、行論の都合上、ベトナム戦開始以降のアノミーの実相に触れねばなりません。このアノミーは先進各国に共通していました。各国で学園闘争が爆発し、リベラルな風が噴きました。反戦平和の反体制、性解放・LSD・爆音ロック・コンピューター音や映像の眩暈が追求されました。
こうした流れの背景に先進国に於ける60年代以降の「二重の挫折」があります。第一の挫折はベティ・フリーダンの『新しい女性の創造』に象徴されます。米国テレビドラマが描く「薔薇色の郊外生活」が実は砂を噛むような地獄。豊かさがもたらした<こんな筈じゃなかった感>です。
第二の挫折は政治的オルタナティブを巡る<こんな筈じゃなかった感>。当初<ここではないどこか>として中共や北朝鮮やキューバが憧憬されたのが、夢から程遠い現実が知られ、<ここではないどこか>は現実ではなく観念に探されるようになります。<政治からアングラ文化への逃避>です。
後のアップルコンピュータに象徴される70年代シリコンバレーも、そうした流れの上にあります。二重の挫折を経て、<ここではないどこか>の眩暈は、バックパッカーに象徴される<自分探し>やコンピュータ音楽や映像に象徴される<環境いじり>(村上春樹的なもの)へと縮退していきます。
でも、今紹介した流れの中に、<技術による人間解放>の初期的な流れがあります。そこでは既に述べたように、歴史的経緯を背景に、反戦・反体制と結合した形で<ここではないどこか>の眩暈が主題化されていたので(ティモシー・リアリー的なもの)、シリコンバレーはリベラルな香りでした。
マルクーゼ:子宮回帰から多型倒錯へ
回り道から戻ります。言葉の自動運動の帰結として、初発的感覚から遠く離れた制度を、阿呆のように受け入れさせられる全体主義的事態に反発する、シリコンバレー系新反動主義者の思考が、言語的自動機械化を嫌うフロイト的伝統に連なるフランクフルターに似ることをお話ししました。
ところが、似るのはその点だけじゃありません。フランクフルターの中に技術と人間の関係を考え抜いたマルクーゼがいます。映画批評で小説家のJ・G・バラードに触れる際などに繰り返してきた通り、僕はマルクーゼ主義者ですが、新反動主義者の思考はマルクーゼのそれに酷似します。
『エロスと文明』『1次元的人間』で知られるマルクーゼは、技術が人間を解放する──1次元的(フラットな)人間をエロスへと解放する──と考えました。学園闘争当時の彼は米国流の技術礼賛だと誤解されました。彼の言う解放は、技術による<安心・安全・便利・快適>化ではありません。
彼は、技術による負担免除が、ヒトがヒトである必要を免除すると述べたのです。そのことを理解した者の多くは、彼の言う「エロスへの解放」のエロスを、子宮回帰──庵野秀明監督『エヴァンゲリオン』シリーズの「人類補完計画」的なもの──として理解しました。でも間違いでした。
彼が言う「1次元的人間のエロスへの解放」のエロスとは、子宮回帰ではなく、多型倒錯です。全体への癒合ではなく、錯乱の眩暈です。子宮回帰が動物化だとすると、多型倒錯化はハイパー人間化です。本能の壊れ(欲動化)を補完する言語プログラムを、技術が免除して、壊れに戻るのです。
マルクーゼ思想を小説化したバラード
マルクーゼのエロスに対する、子宮回帰的理解を表現するのが、SF作家バラートの初期作品、特に「破滅三部作」で、多型倒錯的な理解を表現するのが、バラードの中期以降の作品。映画化作品としてはD・クローネンバーグ監督『クラッシュ』(1997)とB・ウィートリー監督『ハイ・ライズ』(2016)があります。
しかし、未来のリゾートを描いた最も初期の短編『ヴァーミリオン・サンズ』シリーズには、既に中期以降的理解が見られ、かつ技術が何を可能にするかが描かれています。ヒトよりも遙かに優れたコンピュータが産業やインフラの管理を行うので、ヒトは自由気儘な芸術的生活を送ります。
宝石を埋め込まれた昆虫たちが歩き翔び、至る所に不思議なノイズ(音楽?)を奏でる音響彫刻が立ち並び、部屋はヒトの感情に従って色どころか形を変え、或る者は飛行機械に乗って雲の彫刻をし、或る者は実在するか否か分からない女を追い求めて徘徊する──むしろ多型倒錯的です。
そこには、技術が未熟な段階では、ヒトは言語を用いてちゃんと考えて社会を運営したり人生を運営しなければいけないが、技術が高度に発達した段階では、もはや<安心・安全・便利・快適>を意図する必要さえ免除され、他人様に迷惑をかけずに<渾沌と眩暈>を満喫できるというビジョン。
このマルクーゼ=バラード的なビジョン──僕が長らく推奨してきたもの──と、シリコンバレー系テクノロジストが主張する新反動主義のビジョンは、形式が同じだと感じます。彼らはマルクーゼを反復する形で、特異点問題=2045年問題以降の社会を、先取りしていると僕は感じます。
テクノロジスト版オルタナ右翼とマルクーゼ
現地では用語が混乱していますが、ここでは「オルタナ右翼」という言葉で米国版ネトウヨを指し、「新反動主義」をテクノロジスト版オルタナ右翼、と考えます。僕が注目(共感?)しているのは、頭の悪い人間が多いネトウヨ一般ではなく、こうした連中をむしろ見下す新反動主義者の発想です。
オルタナ右翼ないしネトウヨの大半は、国を問わず「周辺化された人々の、不安の埋合せ的な権威主義化」で説明できます。謂わば動物化=自動機械化した存在ですが、そうした連中の出現を必然と捉え、かかる動物化とハイパー人間化(錯乱化)を、同時に擁護する新反動主義者があり得ます。
ここでは先に挙げたような個別の新反動主義者ではなく、僕が考える理念型的な新反動主義者を想定してみます。彼は、所詮は下らない思想や哲学に基づく制度の押しつけに反動しますが、しかしリバータリアンと違い、社会概念を否定するのでなく、技術による社会変革をこそ志向します。
制度による社会変革ではない、技術による社会変革。これを明確に対照させて後者に軍配を上げたのが、見田宗介『現代社会の理論』です。彼は、資源の限界・環境の限界・市場の限界を克服する方途として、資本主義の制度的否定ならぬ、延長線上にある情報化消費化社会に夢を託します。
1996年のこの著作を朝日新聞の論壇時評で批判しました。大食らいのペットを買うより、たまごっちで遊ぶ方が、資源にも環境にも負荷をかけず、簡単な意匠変更で市場の飽和を避けられるのは確かでしょうが、そこで働くヒトの感情がより人間的で豊かになるとの見立てはナンセンス。
むしろ、映画『ファイトクラブ』的な意味で「何でもあり」になる筈です。そうした予想を1968年の時点で打ち出したのがスタニスワフ・レム『泰平ヨンの未来学会議』で、それを見事に映画化したものが、アリ・フォルマン監督『コングレス未来学会議』(2013)です。少し説明します。