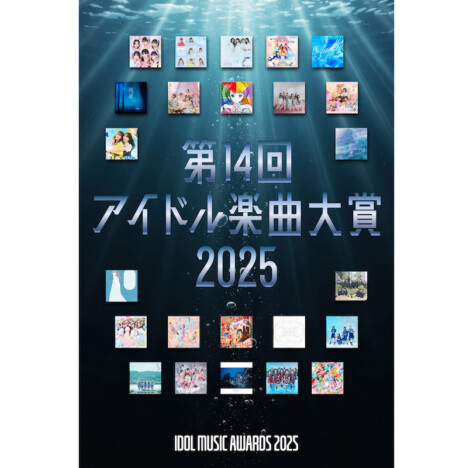Spotifyのビジネス的成長が音楽業界にもたらすもの 印税分配新ルールの狙いも聞く

オーディオストリーミングサービス・Spotifyが、音楽業界に対する支払いや還元についてまとめた年次レポート「Loud & Clear」の2023年版を発表した。今回より初めて国別のデータも公開されている(※1)。日本の国内アーティストがSpotifyで生み出した印税は、2023年だけで200億円以上。さらに約6割がインディーズアーティストであるという。「アーティストとファンをつなぐことによってアーティストが生活できるように還元する」ことをミッションとして掲げる同社のビジネス的な成長や、ストリーミングサービスの市場拡大がアーティストや音楽業界に与える影響について、スポティファイジャパン株式会社 代表取締役 トニー・エリソン氏に話を聞いた。また、インタビュー後半では、今年の4月より施行され、一部で議論を呼んだ印税分配の新方針についても話を聞くことができた。(編集部)
インディーズ活況、海外リスナー拡大…2023年のレポートから見えるもの

ーーSpotifyは音楽業界に対する支払いや還元についてまとめた年次レポート「Loud & Clear」を2021年より毎年発表しています。2023年のグローバルレポートも先ごろ発表されましたが、どのようなアップデートがあったでしょうか?
トニー・エリソン(以下、トニー):おかげさまでこの1年間、Spotifyはビジネスとして非常に大きな伸びがありました。Spotifyは大勢のアーティストやクリエイターが作品への対価が得られるようにすることをミッションに掲げており、ビジネスが成長するということはアーティストやクリエイターへの還元も大きくなるということです。2023年にSpotifyのグローバルでの音楽業界に対する支払額は、90億米ドル(約1兆4000億円)に達し、その伸び率は6年間で3倍という結果になりました。そして、その内訳として印象的なのがインディーズの割合です。全体の約5割を占めていて、支払金額は45億米ドルでした。
ーーインディーズのアーティストやレーベルが半数を占めているというのは、リスナーやユーザーとしてはあまり実感していない部分かと思うのですが、サービス側としてはいかがですか。
トニー:ストリーミングの広がりをはじめとする昨今の音楽業界全体の動きが反映された結果であるように思います。インディーズの比率が大きくなっているというのは、そのシーンやコミュニティに勢いがある、元気があると捉えることができるかと思います。アーティストにとってはさまざまな活動の可能性や選択肢が広がっているとも言えるかもしれません。
ーーまた今回の「Loud & Clear」では、初めて国別のデータも発表されました。日本についてはどのような結果が出ていますか?
トニー:国内アーティストが昨年Spotifyで生み出した印税は、200億円を超えました。これはSpotifyが日本でサービスを開始した翌年の2017年と比較すると1,800%以上の増加となります。日本の音楽業界の市場規模が3000億円とされているので、7年間でここまでの数字に到達できたのは、我々自身としてもある程度評価できるのではないかと思います。もちろんここからまだまだ大きくしていきたいと考えています。ここで特に興味深いのは、昨年国内アーティストが生み出した印税のほぼ半分は、海外リスナーによるものだったということです。国内需要をさらにいっそう大きくしていくことには引き続き注力していますが、海外からの増収に取り組んでいくのは、Spotifyというサービスが日本国内にある意味、Spotify Japanの存在理由でもあると感じています。「邦楽の輸出時代はこれからだ」という話を最近よく耳にするようになりましたが、Spotifyにおいてはすでにこれが始まっているというのは非常に嬉しいことです。
さらに国内アーティストが生み出した印税の内訳を見ていくと、その約6割がインディーズのアーティストやレーベルによるものでした。ストリーミングが活性化すれば、さまざまなアーティストに作品を届けファンを増やす機会が広がり、アーティストが多様な形で活躍できる環境を整えていくことができるのです。インディーズで活動するアーティストが将来的にメジャーレーベルと契約する可能性もあるでしょうし、日本のアーティストエコシステムは非常に活気があると言えるのではないでしょうか。
日本はストリーミングの普及がまだ海外のレベルに至っていないと言われることもあります。しかし、逆を言えば今後まだまだ伸びしろがあるということですし、ここからが楽しみです。

ストリーミング独自のレコメンドやデータがもたらした変化
ーーストリーミングをきっかけにしたアーティストとリスナーの新たな出会いが、アーティストのその後の活動に影響を与えることも増えています。日本国内のアーティストがストリーミングで初めてリスナーに発見・再生された回数が27億回以上という驚きの数字も発表されています。
トニー:先日、アメリカ・カリフォルニアに行った際、ヒスパニック系の方が竹内まりやさんなどのシティポップの楽曲を流しているところに遭遇したんです。誰が選曲しているのかと聞くと「Spotifyのマイプレイリストだぜ!」と言っていました。とても嬉しい出来事でしたが、そういうことって今はもう珍しくないんですよね。先ほど、多くのリスナーは自分が聴いている音楽がインディーズなのかメジャーなのかということをあまり意識していないのではというお話もありましたが、プレイリストやパーソナライゼーションによって、楽曲がリリースされた時代や、国や言語すらも関係なく、世界中のリスナーがそれぞれ気に入った音楽を自然に楽しむ時代がやってきたように感じますね。
ーーSpotifyが日本でサービスを開始してから7年半が経ちました。ここまでお話しいただいたような傾向を含め、ストリーミングの普及が国内の音楽シーンにもたらした変化についてはどうお考えですか。
トニー:この7年間であらゆることが本当に変わりました。Spotifyは日本でも音楽ストリーミングにおいてようやくトップサービスになることができましたが、2016年秋のサービス開始当初からしばらくは主要なカタログが揃わない時期が続いていましたし、日本ではストリーミングは根付かないのではないかと思われていた時代もあったかと思います。しかし、今となってはストリーミングで音楽を聴くことが主流になり、CDやLPのようなフィジカルと共存できるメディアであるという認識も広がりました。ストリーミングは音楽業界にとって次の進化を生み出すもの、うまく活用すればCDが主流だった時代以上の可能性があるとポジティブに捉えられるようになったと感じます。また、世界展開を考えるアーティストが増えているというのも大きな変化だと思います。ストリーミングによってリスナーの聴取行動が可視化されるようになったことで、リスニングデータやインサイトをもとに海外ツアーなどの計画も組みやすくなっているのではないでしょうか。
先ほどもあったように、ストリーミングが得意とするのはアーティストとリスナーの出会いの機会を創出することです。アーティストがリスナーとつながるチャンスを広げ、熱心なオーディエンスやファンを作り、さらにビジネスを広げられるような場を提供することが、Spotifyが日本のアーティストに対して用意できる大きな付加価値だと考えています。

ーーここ数年、音楽シーンの多様化が進んでいるため、アーティストやレコード会社からしても、自分たちの音楽をいかに求めている人たちにリーチさせることができるかという点は、今後ますます重視していくポイントだと思います。そういう意味でもSpotifyをはじめとしたストリーミングサービスが果たす役割は大きいのではないかと。
トニー:今のお話にあった「求めている人にリーチする」というところにストリーミングならではの価値や面白さがあると思っています。リスナーと楽曲のマッチングは、パーソナライゼーションやアルゴリズム、サービス側のプレイリストの編成などを通して、リスナーに対して「あなたの音楽テイストやいまの気分に合うのはこういう曲です」とサジェストしていくことで生まれるものですが、ユーザー自身が求めていることを自覚していない、あるいはこれまでは求めていなかったものの好きになりそうな曲ともマッチングするということが大事であり、醍醐味なんですよね。ユーザーが求めているものと意識していないけれどマッチングしそうなもの、双方をレコメンデーションするというのが、ストリーミングならではなのかなと。
ーー確かにストリーミングで新しく音楽の趣味が広がる経験をしたことがある人は少なくないと思います。
トニー:自分が求めているという自覚はないけれど、耳にした途端「これだ!」っていうのがありますよね。レコメンデーション、パーソナライゼーション、プレイリストなどに加えて、Spotifyには複数で一緒に音楽を楽しめるBlendやJamといった機能もあります。そういった多様な形で音楽との出会いが生まれることについては、日本でもリスナーの皆様にもアーティストの皆様にも喜んでいただいているように思いますね。