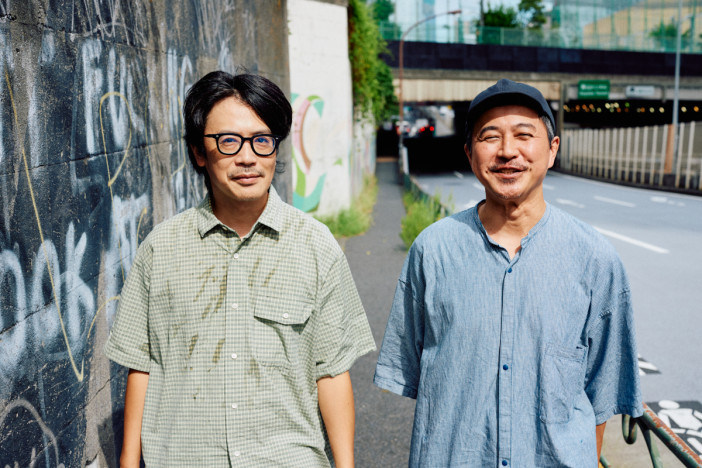『京都音楽博覧会』、3年ぶりに有観客開催された充実の1日 槇原敬之、SHISHAMO……各アクトから垣間見えた“くるりの特別さ”

そして、ファンもファン以外も、『京都音博』の常連もそうじゃない人も含めて、今ここにいる全員を最も強くひとつにまとめ上げたアクト。それが槇原敬之だったのではないかと思う。僕は普段、フェスやライブで一体感なんて生まれなくてもいいと思っている方なのだが、そんな自分でも撃ち抜かれてしまった。
「遠く遠く」「どんなときも。」で始まり、「鉄道博物館があるということなので、鉄道にちなんだ歌を歌いたいなと思います」と披露された「LOVE LETTER」や、「僕が一番欲しかったもの」「世界に一つだけの花」などを経て、「宜候」と「四つ葉のクローバー」で終わる全9曲。「くるりの岸田くんからお声をかけていただきまして、今日この場所に立って、こうやってコンサートできるのを本当に幸せに思っております」と語った、そんな何気ない言葉にも「本当にそうなんだろうな」と思わせる実感がこもっている。ましてや歌の実感たるや。本当に特別な時間だった。

トリのくるりの前に、又吉直樹(ピース)が登場。初めて「東京」を聴いた18歳の時から現在まで、自分のそばに常にくるりの音楽があったことをしたためた朗読に続いて、くるりのライブが始まる。

1曲目は「真夏日」。『京都音楽博覧会2022』の開催記念シングルとして、この会場から販売スタートされ、同じくこの日から配信も始まった新曲である。9分弱に及ぶ、壮大で美しくて、そこはかとなくサイケデリックなこの曲に続いて、あの「東京」のギターリフが響いた。
さらに「ハイウェイ」「潮風のアリア」「琥珀色の街、上海蟹の朝」と、新旧の代表曲を惜しみなくプレイしていく。「琥珀色の街、上海蟹の朝」では岸田はギターを置いてハンドマイクで歌うのが恒例だが、この日はギターを持ったままだったのがちょっと新鮮だった。


岸田、佐藤、松本大樹(Gt)、野崎泰弘(Key)、石若駿(Dr)といういつもの5人に鍵盤のハタヤテツヤが加わった6人編成なのも、音に新鮮さを与えている。くるりのライブを観るのは今年何度目だろう(あとで数えたら5回目だった)と考えつつ、何度観ても、バンドサウンドというものが途方もない可能性を秘めていることを思い知らされるなと、音を浴びていると思う。


その後も、「ばらの花」「everybody feels the same」「太陽のブルース」「ブレーメン」まで、MCを挟まずにやり通す。そして岸田が「大変な状況ではありますが、3年ぶりに梅小路に帰って来ることができました。みなさんがいないと帰って来れなかったと思います、ありがとうございます」と改めて観客にお礼を言い、出演者たちにも感謝を伝える。


そして、「終わりの時間が近づいております。なんか……ちょっと気持ちがいっぱいみたいなので、この辺でしゃべるのやめよかなと思います」と言って、バンドメンバーを紹介。本編ラストの「奇跡」では、止まない雨の中、アコースティックギター、ピアノ、岸田の歌によって美しいアンサンブルが描かれる。
『京都音博』のアンコールはいつもこの曲で終わるーー今年はマンドリンやアコーディオンも加わっての「宿はなし」。そうか、前回(2019年)はまだファンファンがいて、最後に3人でこの曲をやったんだよな、それが恒例だったんだよな、と思い出して、ちょっとしみじみする。
終演後、京都タワーは“オンパクカラー”の緑色に輝いた。
くるりより若いキャリアのアクトが出る、言わば“後輩枠”。主にアメリカとイギリス以外の国からアーティストを招聘する“海外枠”、これまで小田和正や石川さゆり、布施明などが出演してきた、いわゆる“レジェンド枠”。
くるりと同じくらいのキャリアのバンドが出演する“同期枠”的な存在は今年はいなかったが、それ以外の各枠がしっかりと存在した2022年の『京都音博』。その中にあって、特に印象に残ったのは“後輩枠”だった気がした。例えば、SHISHAMOの宮崎は次のように語っていた。
「呼んでいただけたことにびっくりしました。来月CDデビュー10周年イヤーに突入するんです。ずっと音楽だけやってきまして、たった10年なんですけど、その中でもいろんなことがあって、まじめに音楽をやっているのが馬鹿馬鹿しくなるような瞬間もたくさんあったんですよね。でも、こうやって、こんな素敵なステージに呼んでいただけて、間違ってなかったんじゃないかなと思いました」
くるりがリスペクトされているのは十分知っているつもりだが、SHISHAMOが『京都音博』の出演オファーを“10年頑張ってきたご褒美”と解釈するほどなのか……と少し驚いたが、きっと“それほどのもの”なのだ。
それは、マカロニえんぴつとVaundyからも感じられたし、(先輩だが)槇原敬之の歌と言動にとても実感がこもっていた要因でもあると思う。そんな意味でも、くるりという存在の得難さを改めて実感させられた、2022年の『京都音博』だった。

くるり 岸田繁×氣志團 綾小路翔、フェス主催アーティスト赤裸々対談 コロナ禍による中止から2022年の開催まで
海外アーティストの来日や現地での開催など、コロナの影響を受けた2020年以来、最大の盛り上がりを見せる2022年のフェス。リアル…
くるり、25周年を経て再提示された“ロックバンド”としての力強さ 現在進行形の姿刻んだツアーファイナル
8月5日、くるりが『くるりライブツアー2022』のファイナルとなる東京公演をZepp Hanedaで開催した。1月に大阪で、2月…