小説『モンパルナス1934~キャンティ前史~』エピソード11 東京-山中湖 村井邦彦・吉田俊宏 作

東京-山中湖 #2
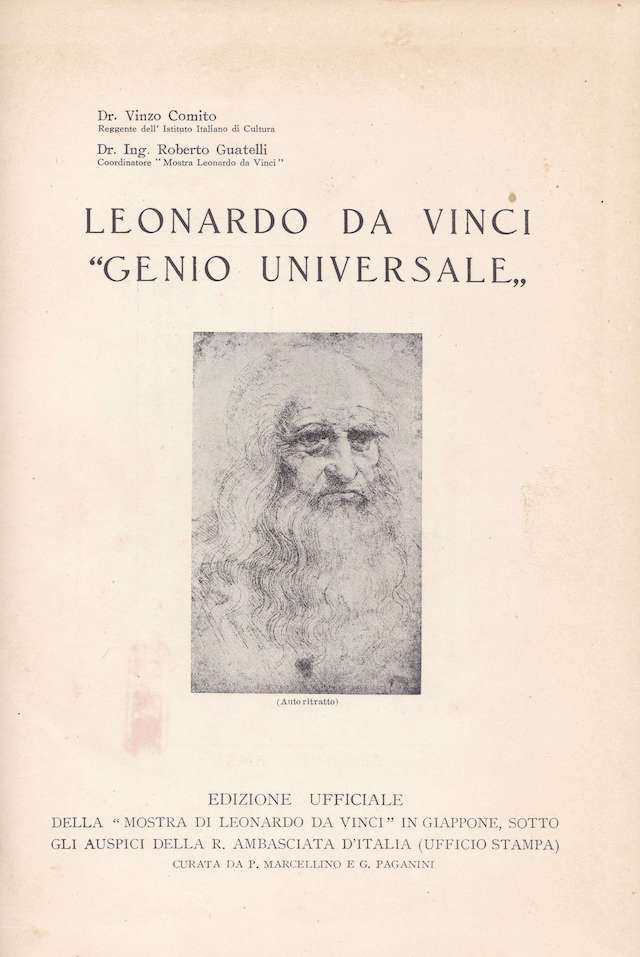
レオナルド・ダ・ヴィンチ展の話を持ってきたのは紫郎だった。
まだ真珠湾攻撃が始まる前の1941年秋、駐日イタリア大使館の友人、オッタビオ・ロンバルディから呼び出され、紫郎は久々に三田の大使館を訪れた。
「シロー、紹介するよ。こちらはミルコ・アルデマーニ情報官だ」
「はじめまして、シローさん。お噂はかねがねうかがっています」
情報官によれば、イタリアのミラノで1939年に「レオナルド・ダ・ヴィンチ展」が開催された。評判を呼んだ同展は翌年、ニューヨークの万国博覧会に出展され、万博終了後も1年かけて全米各都市を巡回したという。
「先日、大盛況のうちに閉幕しました。展示品はこのままイタリアに送り返される予定ですが、もし日本にダ・ヴィンチ展を開催するご意志があるようなら、日本経由で送り返すこともできます。シローさん、いかがでしょうか」
アルデマーニは紫郎の目を見て言った。
紫郎はすぐさま仲小路、小島、坂倉に相談した。アメリカと戦争が始まってしまえばダ・ヴィンチの名品を太平洋航路で運ぶのは難しくなる。
真っ先に賛意を示したのは仲小路だった。
「レオナルドは優れた画家でした。『モナリザ』は素晴らしい。それは誰でも知っています。しかし彼は画家や彫刻家であると同時に、傑出した科学者であり、哲学者でもあり、建築家、解剖学者、植物学者、様々な機械の発明家でもありました。いわば総力戦的な天才です。アメリカとの決戦が避けられぬ状況になってきた今、レオナルドの顕彰は極めて意義のあることといえます。紫郎さん、急いで大使館に受諾の返事をしてください。国家的な大事業にしましょう」
仲小路の発案を受けてすぐに小島が動き、あっと言う間に情報局、陸軍省、海軍省の後援を取りつけてきた。
レオナルド・ダ・ヴィンチ展準備委員会の名誉会長は駐日イタリア大使マリオ・インデルリにお願いし、会長は末次信正海軍大将(スメラ学塾塾頭)、副会長は三井高陽男爵、委員長は奥村喜和男情報局次長が務めることになった。
その下の準備委員にはアルデマーニ情報官のほか、文部省国民精神文化研究所長、外務省欧亜局長、陸軍省報道部長、海軍省報道部長が名を連ねた。仲小路の目論見通り、どんなイベントにも見劣りのしない国家的事業の体裁が整ったのである。実質的に運営に当たる常任委員は小島と坂倉が務めることになった。
「アジア復興 レオナルド・ダ・ヴィンチ展」は当初予定から2カ月遅れの1942年7月11日、上野池之端の産業館で開幕した。
展覧会のパンフレットから名前を抹消された小島は6月3日以降、巣鴨の東京拘置所に移されていた。ノミやシラミに悩まされた警視庁の留置場から一転、待遇は劇的に改善された。義兄の左近司政三海軍中将、兄弟のように親しかった司法省の正木亮行政局長らの計らいだった。かつて左翼活動で捕まった紫郎を救ってくれたのも正木である。
小島の容疑は「軍機漏洩」だった。彼は和歌山県の教育会で講演した際にこう述べた。
「マレー沖海戦でイギリスの大戦艦プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦レパルスが日本海軍航空隊に撃沈させられた。あれが時代の転機であった。もはや大艦巨砲主義は時代錯誤であり、大戦艦など造っても意味がない。飛行機を造るべきであろう」
折しも基準排水量6万4000トンの巨大戦艦大和が呉で完成し、同6万5000トンの2号艦武蔵が長崎で完成しつつあった。特高は小島の取り調べで「日本が7万トンの戦艦を造っている」と話したのではないかとしつこく追及した。
「貴様、何万トンと言った? 正直に言え。おい、7万トンと言ったんだな?」
「7万トンだろうが10万トンだろうが、そんな数字はどうでもいい。巨大戦艦など造っても意味がない、飛行機を造れとは言ったよ。それが僕の信念だからね」
尋問ではそんなやり取りが繰り返されたという。
小島はまだ知らなかったが、日本海軍は1942年6月初旬、ハワイの北西に位置するミッドウェー島付近の海戦でアメリカ軍に大敗していた。日本軍は空母4隻、艦載機約290機を喪失。戦艦大和は初陣を飾れず、くしくも小島の唱えた「大戦艦など造っても意味がない」が実証された結果になった。
ダ・ヴィンチ展の会場計画は坂倉が担当した。場所は上野池之端の産業館。コンクリートブロックの通路とスロープを通って場内を回遊する設計は、1937年のパリ万博で坂倉がグランプリを受賞した日本館をほうふつさせる。紫郎は坂倉の案内で会場を見学した。
「サカ、あの日本館以上だよ、この会場は」
「ありがとう。今回は絵画や彫刻だけじゃなくて、レオナルドが発明した大きな機械類もたくさん出展されている。こうしてスロープをのぼって高い位置から眺めると、ほら、下から見るのとは違った迫力があるだろう?」
坂倉が少々得意げに言った。眼下にはダ・ヴィンチのデッサンに基づいて復元された機械が整然と並んでいる。ミラノで開かれた際にはまだ作られていなかった機械、ニューヨーク万博では会場が狭くて展示されなかった大型機械なども網羅し、世界最大級の展示になっている。
「こいつはすごいね」
紫郎は高さ15メートルの大揚水機を見てため息をついた。会場に水路を設置し、モーターで急流を生み出し、実際に運転して高所まで水をくみ上げてみせるという圧巻の展示だった。
「水路までつくるなんて、カネと手間がかかりすぎるって、反対意見もあったんだけどね。実際に動かしてみせなきゃ、この機械のすごさは分からないだろう? これを500年も前の男が考えたんだぜ。しかも『モナリザ』を描いた男と同一人物なんだからなあ。そうそう、あそこの刻印機も見逃しちゃいけないよ」
坂倉が重量ハンマーをロープで巻き上げている巨大な機械を指さした。
「コクインキ? ああ、貨幣の刻印のことか」
スロープを降りてきた紫郎の目の前でハンマーがガシャンと打ち下ろされ、円盤状の金属が一瞬にしてコインになった。
「これを500年前に考えたってわけか。日本はまだ室町時代だよな。ルネサンスの万能の天才を紹介すれば、日本文化の高揚につながるって仲小路先生が言っていたけど、いやはや、圧倒されっぱなしだな」
1943年に入ると戦況は目に見えて悪化した。まず2月1日に日本軍がガダルカナル島からの撤退を開始したが、これは太平洋の主導権が米軍に渡ったことを意味した。翌2月2日にはスターリングラード攻防戦でドイツ軍が降伏し、これを機に独ソ戦におけるドイツ軍の後退が始まった。
さらに12月には英米中の首脳が「カイロ宣言」を発表する。これは対日戦争の戦後処理案であり、日本の無条件降伏を前提として、満州や台湾などの中国への返還、朝鮮の独立などを求める内容だった。
「ついに終戦を考えるべきときが来たようです」
1944年2月、自邸の応接で仲小路が静かに言った。紫郎、坂倉、井上がソファーに腰かけてうつむいている。小島は釈放されたが執行猶予中で、スメラ学塾などの活動は自粛していた。
「日本の戦争の目的は欧米に植民地化されたアジアの解放でした。戦況は悪くとも、その目的は達成されました。いや、まだ道半ばかもしれませんが、道筋はついたといえるでしょう。これからは、いかに戦争を終わらせるか、最善の策を探っていかねばなりません。しかし、当局はますます言論統制の手綱を締めてくるでしょう」
仲小路はそこまでよどみなく話し、集まった3人の顔を順番に見た。
「先生、まさかスメラ学塾の活動をいったん停止するおつもりでは」
井上が口を開いた。
「スメラ学塾は解散します」
仲小路は1枚のわら半紙をテーブルに置いた。塾員、塾生に宛てた「スメラ学塾解散」を知らせる手紙の下書きだった。
「か、解散か…」
坂倉が絶句した。
無精ひげをはやした書生が「失礼します」と紫郎たちに一礼し、仲小路に耳打ちをした。
「よろしい。お通ししなさい」
2人の若い男がうつむきながら入ってきて、仲小路の前で直立不動の姿勢をとった。色白の優男と浅黒い柔道家風の男で、絵に描いたような好対照のコンビだと紫郎は思った。柔道家の方はスメラ学塾で見かけたことがあった。
「赤紙が届いたそうですね」
「はい。先生、最後のお別れに参りました」
柔道家が言った。
「最後のお別れ…ですか?」
仲小路の声の調子が変わった。紫郎はさっと姿勢を正した。
「はい、お別れに参りました」
今度は色白が声を詰まらせながら言った。
「そんな心構えではいけません。生きなければなりません。『神州不滅』とは生き抜くことではありませんか。必ず生きて帰ってきてください。生きている限り、希望はあります。いいですね?」
「せ、先生!」
柔道家が声を上げて泣き、優男は声を押し殺して、やはり泣いていた。
1944年春の某日、紫郎は仲小路から直々に「食事をしませんか」と誘われ、東京駅の精養軒に急いでいた。仲小路と差し向かいで食事なんて珍しい。いや、初めてのことだ。何事だろうか。冷たい雨に打たれ、満開だった皇居の桜がはらはらと散っている。
「先生、お待たせいたしました」
仲小路は奥の席に座っていた。
「急にお呼びたてして申し訳ありません。さあ、何でもお好きなものを」
「は、はい。あ、あの、宮城の桜が散っておりました」
用件は何ですかとは訊けず、紫郎はとんちんかんなことを口走った。
「実は知人を通じて、赤松さんから依頼を受けましてね」
仲小路は紅茶をすすりながら言った。
「赤松貞雄さんですか。首相秘書官の」
紫郎は身を乗り出した。赤松が仕える総理は、日米開戦前から長期政権を続けている東條英機だ。首相のほか陸軍大臣と参謀総長を兼務している。
「首相と私の会見を実現させたいとお考えのようです」
「東條との会見ですか。東條内閣の決戦非常措置はひどいものですよ。これでは国民は何もできない。いくら戦時下とはいえ、自由のじの字も……」
紫郎が思わず声を上げると、仲小路が目で制した。他の客から遠く離れた隅の席ではあるが、誰が聴き耳を立てているか分からない。1944年2月に閣議決定された「決戦非常措置要綱」は学徒動員や女子挺身隊の強化、旅行の制限、高級享楽の停止など、国民生活にいっそうの窮迫を強いる政策だった。高級享楽の停止によって、待合、カフェー、遊郭、劇場は軒並み休業を余儀なくされ、芸妓らは女子挺身隊として各地の作業所に振り分けられた。
「この期に及んで、東條は先生に何を相談したいのでしょうか」
「会ってみないと分かりません。いや、そもそも会うべきか、否か。そこが問題です」
仲小路は腕を組んで目をつむった。外出嫌いの先生がこうして昼間から出てくるのは極めて珍しい。それに面会の要請は山ほどあるが、ほとんど即座に断っているのを紫郎は知っていた。即断即決の異才がこれほど悩む姿は見たことがない。仲小路にとっても東條との会見は特別の案件なのだ。
沈思黙考する歴史哲学者の前で、紫郎は淡々と食事を済ませ、一人で紅茶を飲んだ。昼食に訪れていた他の客はすべていなくなったが、先生は全く動かない。眠ってしまったのだろうか。そろそろ声をかけるべきかと紫郎が気をもみ始めたころ、仲小路の目が急に開いた。
「やめましょう」
「はあ…。東條との会見は断ると?」
「はい。会見はしません」
「理由をうかがってもよろしいでしょうか」
紫郎はティーカップをテーブルに戻し、仲小路の答えを待った。
「首相が私の意見を全面的に受け入れるのであれば、何の心配もありません。しかし、そうでない場合、私たち同志は一網打尽に逮捕されるでしょう」
仲小路は給仕が何度か取りかえた紅茶を飲み干し、安堵の表情を浮かべた。小島をはじめ、多くの知識人が弾圧されている状況を考えれば賢明な判断だった。それにしても、なぜ自分が呼ばれたのか、自分はいてもいなくても同じではなかったかと紫郎は思ったが、ともかく結論が出て良かったと素直に喜ぶことにした。





















