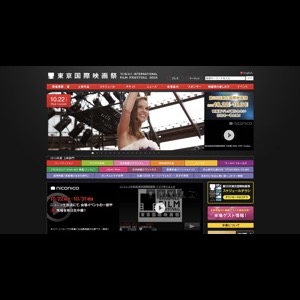『さようなら』公開記念インタビュー
深田晃司監督が明かす、『さようなら』で描いた“メメント・モリ”と独自の映画論

劇作家・平田オリザの戯曲を原作に、死にゆく人間と死を知らぬアンドロイドの交流を描いた『さようなら』が11月21日に公開となる。監督を務めたのは、前作『ほとりの朔子』でナント三大陸映画祭グランプリ&ヤング審査員賞をW受賞した深田晃司。リアルサウンド映画部では、深田監督にインタビューを行い、本作の製作背景や映画に対する思いなどを語ってもらった。
「メメント・モリ(死を想え)の芸術を映画で表現したかった」

ーー本作は平田オリザさんのアンドロイド演劇が原作です。なぜ映画化しようと思ったのでしょうか。
深田:「フェスティバル/トーキョー」という国際舞台芸術祭が毎年池袋で開催されていて、2010年に舞台で初めて同作を観たときに、すぐ映画化したいと思ったんです。それで、オリザさんに「映画化していいですか?」と聞いたら、「ああ、いいよ」っていう一言だけで、あっさりと映画化権の許可をもらって動き始めた感じです。
ーー条件とか、こうしてほしいみたいな要望もなく?
深田:全くないですね、フリーハンドです(笑)。自由にやってくれと。
ーーなるほど(笑)。平田さんは実際に完成した映画をご覧になって、どんなリアクションだったんですか?
深田:一言「面白かったよ」って言ってくださいました。原作の戯曲自体は、15分ぐらいの短い演劇で、何もない真っ暗な舞台に椅子を並べて、そこでアンドロイドと女性が2人で対話する。観客にとっては、その女性が何者なのか全くわからないし、その場所がどこかもよくわからない。そういったシチュエーションで観客の想像力を最大限に引き出して、“死”というものをイメージさせる、極めて演劇的なアプローチでした。今回の映画では、より映像寄りの手法で、二人の周辺をもっと具体的に描き込んで、死体そのものも物質的に見せていきました。なので、演劇的な手法から映画的な手法への拡大、翻訳みたいなところを楽しんでもらえたと思っています。

ーー具体的にオリザさんの原作戯曲のどのような部分に惹きつけられたのでしょうか?
深田:1番惹きつけられたのは、死んでいく女性と死ぬことのないアンドロイドの対話を通して、強烈に“死”というものをイメージさせる、いわばメメント・モリ(死を想え)の芸術だというところですね。生き物はみんな死んでいきますが、概念としての死を認識できるのは人間だけだと言われています。だからこそ、“死”という逃げようのない巨大なインパクトからもがくように、古今東西の芸術家はいろいろな“死”を題材にした文学だったり絵画だったり音楽だったり、そういったものを作ってきた。そのようなメメント・モリの表現の最先端となるものが、アンドロイド演劇の『さようなら』だと思ったんですね。それはもともと僕の関心の高い分野だったので、これをスクリーンに持っていきたいと思ったんです。

ーーもともとアンドロイドに興味があったんですか?
深田:特にそういうわけではなくて、最初に描きたいと思ったのはその“死”の部分で、その“死”を描くのに、アンドロイドはちょうどいいなと思って。ただ撮ってみてやっぱり面白いなと思ったのは、今の科学技術の成果でもあり限界も一緒に併せ持ったアンドロイドと人間を共演させることによって、強烈に「人間とは何か」「アンドロイドとは何か」ということに想いを巡らせざるを得なくなってしまう。そこへの関心は確かに昔からあったんですね。アンドロイドと人間はすごく差があるようだけど、結局人間なんてものすごい複雑なアンドロイドに過ぎないのではないかという想いですね。