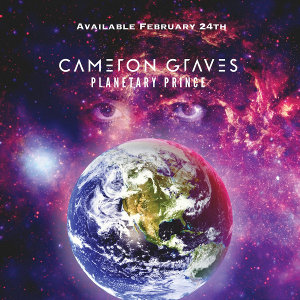柳樂光隆の新譜キュレーション 第2回
柳樂光隆が選ぶ、「生演奏とプロダクション」の2項対立を超えたジャズ新譜5枚
例えば、Thundercatの『Drunk』や、そこに多大な貢献をしていたルイス・コールのユニットのKnowerなどを挙げるまでもなく、「生演奏かプロダクションか」みたいな2択で考えるのが、心の底から馬鹿らしく思える状況が生まれている。ハッキリ言って、「クリエイティブだったらどっちでもいいじゃん」としか思えなくなっている。そして、その2項対立で考えるのが無効になるような作品が次々に生まれている。演奏家が自由になっているのだったら、僕らの耳ももっと自由になればいい。
ジャマイア・ウィリアムス『///// EFFECTUAL』
ジャズの世界でも高い評価を受けながら、ERIMAJというグループでJディラをカバーしたり、インディーロックを意識したりしていたドラマーのジャマイア・ウィリアムスの自身の名前を冠した初のソロ・アルバムはあまりに痛快だった。気付いたらVulfpeckの『The Beautiful Game』にもクレジットされていて、いつの間にかNYからLAに移住していたジャマイアが作ったのはLAらしい自由な雰囲気のアルバムだった。カマシ・ワシントンやデ・ラ・ソウル、カルロス・ニーニョ、シャフィック・フセインやビラルなどに関わっていた複数のエンジニアを使い、複数のスタジオで、それぞれ全く違うセッティングのドラムセットで録音し、全てがほぼドラムソロにもかかわらず、全く違うサウンドと全く違う質感の楽曲が入り混じっている。それぞれのスタジオで、ドラムパットやドラムトリガーを使ったエフェクティブなセッティングから、ヴィンテージのドラムを使った美しすぎる音色などを使い分け、時にカルロス・ニーニョがオーバーダビングを施すことで、まるでビートミュージックのようなサウンドに仕上がっている。
それぞれのエンジニアはドラマー出身でドラムに詳しく、彼らがドラムテックを兼ねることで、徹底的にドラムの音と、録音にこだわり、それが特別な質感を生み出している。フランク・オーシャン『Endless』にも起用された鬼才鍵盤奏者シャソールも参加しているが、それもその中の1曲として溶け込んでいる。過度な編集などを施さなくても、テクニカル且つクリエイティブなドラムプレイと、それをどう録音するかの工夫で、まるでポストプロダクションを施したかのように聴かせることを示したという意味でこのアルバムは特別な意味を持っている。Seihoやディアントニ・パークス、マシュー・デイヴィッドなどをリリースする<LEAVING RECORDS>がリリースしたのも納得。ちなみに以前、マーク・ド・クライブロウと話した時に「今、ジャマイアがエクスペリメンタルなアルバムを作っている。あれはすげーよ」と言ってたのはどうやらこれだったようだ。
Christian Scott aTunde Adjuah『Ruler Rebel』
その一方でプロダクションに一気に比重を傾けたのが、トランぺッターのクリスチャン・スコット。前作の時点でドラムセットに西アフリカのパーカッションやドラムパットを組み込み、徹底的に音像にこだわったクリスチャンだが、新作ではほぼドラムパットで打ち込みかと思うくらいのトラックになっていて、鍵盤もほとんどウワモノっぽく響かせて、もはやバンド感は全く感じられなくなっていた。一つのディスプレイの中にいくつものウィンドウが開いていて、そこで個々のメンバーが演奏している音が同時に一つのヘッドフォンで鳴っているといった雰囲気と言ってもいいくらいのサウンドは、びっくりするくらい完全に振り切れていた。前作のインタビューの時点で「トラップとか現行のR&Bをすごく聴いていて、それを消化したいと思っている」というようなことを言っていたが、正にそんなサウンドが鳴っていて、アトランタ発のヒップホップのようなビート感や酩酊感もあり、曲中でフレーズにいきなりエフェクトがかかって別のテクスチャーになったり、突然歪んでいく感じは正に今のトラップ的な特徴をジャズに取り入れたような感覚がある。という意味では、やはりバンドではなく、トラックであるし、リミックスしたような音楽ともいえるかもしれない。
その中でも特徴的なのがクリチャン・スコットのトランペットが明らかに浮いていることだ。近年は管楽器の音さえも全体のサウンドに溶け込ませようとするミュージシャンも増えたが、クリスチャンはフィルターをかけたり、エフェクトはかけても自分のフレーズを自分の音色で吹くのみ。明らかにそこだけ浮いているが、そこは主役のラッパー=ボーカリスト気分なのか。その敢えて溶け込ませずに浮き上がらせた、異物感や孤立感が不思議な魅力を放っている。浮いているのではなく、狙って浮かせているからこそ「アリ」になる。
ニタイ・ハーシュコビッツ『I Asked You a Question』
バランス感で言えば、イスラエル出身の鍵盤奏者ニタイ・ハーシュコビッツのソロ作が抜群だ。もともとはイスラエルジャズの重鎮アヴィシャイ・コーエンのバンドでシャイ・マエストロの後釜に抜擢され、圧倒的なテクニックとクラシック要素の強いピアノで瞬く間に注目を集める存在になった彼だが、ソロ作をリリースしたのはジャズとビートミュージックやネオソウルなどが入り混じったサウンドをリリースするイスラエルの個性派レーベル<Raw Tapes Records>から。内容ももちろんジャズ寄りでも、クラシック寄りでもなく、イスラエル独特のエキゾチックなメロディーや変拍子などを取り入れつつ、自身で作ったビートに生演奏を組み合わせ、編集しまくったサウンド。時にテイラー・マクファーリンやThundercat的なブレインフィーダー経由のジャズ×ビートミュージックの要素があったり、時にそのイスラエルの独特のメロディーを活かしてFKA Twigs的な雰囲気があったりと、これまでのジャズ作品での超絶技巧プレイからは全く見えなかったセンスのいいエレピ使いなど、底知れない才能に驚愕。何故か、カート・ローゼンウィンケルも参加していたり、謎だらけなのも最高だが、そのあたりにジャズミュージシャンとしての生演奏へのこだわりが薄ら覗くのもこの作品の魅力だろう。