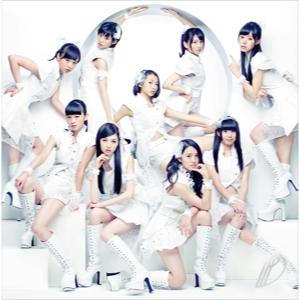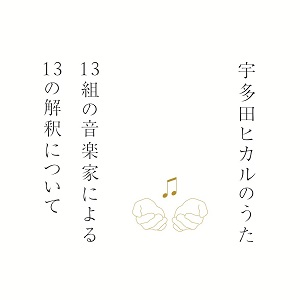カバーブーム立役者の軌跡(後編)
徳永英明、ついに『VOCALIST』シリーズに終止符? 10年間の”カバー術”を検証する

徳永英明が女性アーティストのバラード系名曲を次々とカバーした『VOCALIST』シリーズは累計600万枚を超える好セールスを記録し、大病をかかえ、一度はシンガーとしての再起が危ぶまれた彼を見事に復活させた。前編【「大病で引退寸前」から「カバーブームの牽引者」へ 徳永英明の波瀾に満ちたキャリアとは?】では、そんな徳永が同シリーズに巡り会うまでの波乱のシンガー人生を振り返った。後編では、同シリーズの変遷とその音楽的功績を追うとともに、最新作『VOCALIST 6』をもって、徳永が本シリーズに区切りを付けようとしている理由を推察したい。
『VOCALIST』はそもそも、“大ヒット”を目論んでスタートした企画ではなかった。徳永が2004年にレコード会社の社長と食事をした際、社長に「カバーアルバムを作ろうかな」と話したところ、「それいいじゃない」と後押しされ、復活プロジェクトとしてアルバムを制作することになったという。当時のレコード会社スタッフの述懐によれば、ヒットよりもまず、2001年の「もやもや病」発症以降に停滞していた徳永のキャリアをもう一度盛り上げよう、という思いが強かったようだ。
ただし、徳永自身の意気込みは大きかった。シリーズの1作目を出す時点ですでに40~50曲を選曲し、映画の3部作のように、3作目までの構想を練っていたという。自身のキーに合う女性アーティストに限定し、“知る人が知る名曲”ではなく、誰もが一度は耳にしたことがあるような“時代の名曲”を集めた。
たとえば2005年に発表した1作目の『VOCALIST』には、中島みゆきの「時代」、竹内まりやの「駅」、荒井由実の「卒業写真」などが収録されている。どの曲も女性の繊細な心情ーーとくに失恋や離別の悲しみ、叶わぬ思いなどを歌った名曲で、多くの人々の心に残っている歌だろう。徳永はそれらの歌を我流でカバーするのではなく、譜割りひとつ取っても、できる限りオリジナルに忠実に、丁寧に歌っている。楽曲自体はアコースティック楽器を中心としたアレンジで柔らかなサウンドに仕立ててあるが、それも決して奇をてらったものではなく、オーソドックスな解釈といえる。
徳永のカバーの特徴とは、主人公の女性に完全に感情移入するというわけではなく、どこか淡々と、一定の距離感を持って歌っている点であろう。原曲にそっと寄り添うようなスタンスであり、そこには過剰な装飾や誇張した表現がない。だからこそリスナーは、原曲が本来持っているメロディの豊かさや温かな感情に改めて気付かされる。また、原曲を長く聴き続けてきたリスナーは、一つひとつのメロディや言葉を慈しむように歌う徳永の姿に、自身の原曲への思いを重ねる面もあるのではないだろうか。