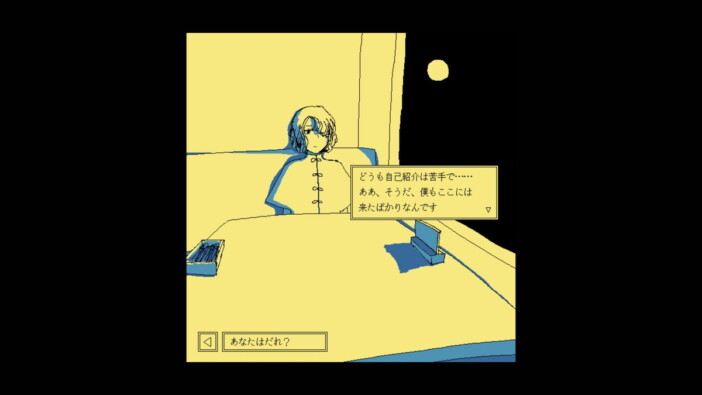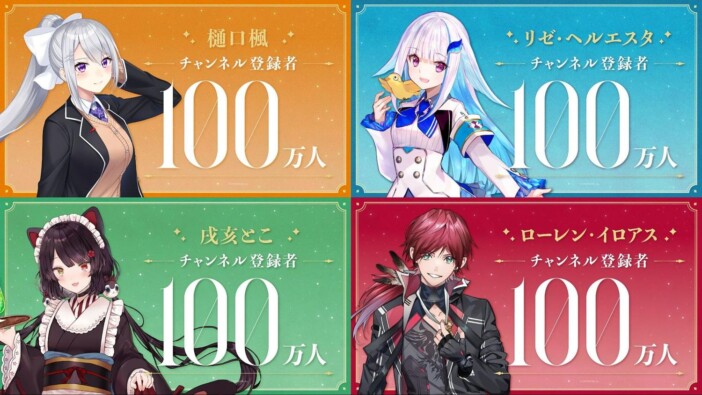ゲームの元ネタを巡る旅 第17回
『ゴースト・オブ・ツシマ』から学ぶ元寇――2度にわたる元軍の侵攻と“神風伝説”

多種多様な販売形態の登場により、構造や文脈が複雑化し、より多くのユーザーを楽しませるようになってきたデジタルゲーム。本連載では、そんなゲームの下地になった作品・伝承・神話・出来事などを追いかけ、多角的な視点からゲームを掘り下げようという企画だ。
企画の性質上、ゲームのストーリーや設定に関するネタバレが登場する可能性があるので、その点はご了承願いたい。
第17回は『ゴースト・オブ・ツシマ』を題材に、元寇について特集する。
『ゴースト・オブ・ツシマ』は、1274年の元寇・文永の役を題材にしたオープンワールドのアクションアドベンチャーゲームだ。開発をSucker Punch Productions、販売をソニー・インタラクティブエンタテインメントが行っている。対馬の武士である境井仁が、武士として戦うべきか、卑怯な戦い方をしてでも民を守るべきかについて葛藤しながら、元軍に立ち向かう物語が描かれている。

元寇とは何か?
そもそも元寇(蒙古襲来)とは何なのか。一般的な説をベースに、簡単な解説から入ろう。
元寇とは、鎌倉時代にモンゴル帝国(元)が日本に対して二度に渡って行った侵攻を指す。一度目は文永の役(1274年)、二度目は弘安の役(1281年)であり、フビライ=ハーンの命により行われた。
文永の役では元軍および高麗軍が約3万人の軍勢で、対馬や壱岐を襲撃し、九州・博多にも上陸。日本側は御家人を中心に迎え撃つが、元軍の集団戦法や火薬兵器(てつはう)に苦戦する。しかし、夜間に暴風が発生し、元軍は撤退した。

なお『ゴースト・オブ・ツシマ』では、このとき最初に進行された対馬の小茂田の浜がゲーム冒頭で描かれ、物語の起点となっている。

続く弘安の役では、元軍は14万から15万人を動員。しかし、日本側は博多湾に石塁を築くなどして、元軍の上陸を妨げる。長期戦となるが、再び暴風雨が発生して、元軍は大打撃を受けて撤退した。以降、元軍が攻めてくることはなかった。
これにより、日本では「神風(かみかぜ)」という伝説が生まれ、のちの太平洋戦争においても軍事思想として用いられることとなる。

元寇に至る流れ
ここからは元寇を時系列に沿って追っていきたい。
まず元と日本の関係性を語る前に、現在の朝鮮半島に存在していた高麗(こうらい)について語っておかねばならない。918年に始まった高麗王国は、1259年、モンゴルからの六度の侵攻や内部でのクーデーターにより、モンゴル帝国に降伏する。以降、高麗は元寇において、日本を侵略したがるフビライ・ハーンに対しての窓口として機能し、また苦労することとなる。

1266年、フビライ・ハーンは日本への侵略を開始するため、高麗に使者と命令書を送る。そこには「波風が強い海を渡ってまで侵攻したくないなどとは言うな」と言い訳を先回りする文面もあったようだが、高麗はその通りの返答をして一旦は使者を送り返した。
その後、フビライ・ハーンは8年もかけて5回もの使者を出し、日本へ侵略する旨を伝えたという。もちろん、この使者や詔書は大宰府にも伝わることとなるが、日本側(北条家)は一度も返書を送らず、着々と防衛戦争の準備をした。

この件について、東洋史家の宮脇淳子氏は『世界史のなかの蒙古襲来』(扶桑社・2019年)のなかで、こう推察している。曰く、モンゴルとの通好が始まれば、それは征服を始められてしまうことと等しく、また断りの返事をすれば、それはそれで開戦事由を与えてしまうことになるのだ。なので、一切の返事をしないということがベストだったのではないかということである。
元寇の始まり――文永の役
さて、ついに元の侵攻が始まる。1274年10月3日、元軍・高麗軍の混成部隊は朝鮮半島の南端である合浦を出港した。
ここでゲームを遊んだ人がやや勘違いをしてしまっているかもしれないポイントをさらっておくと、元寇において日本を攻めてきた軍隊は、モンゴル人ばかりではないということだ。このときの内訳は、元の軍隊が15000人、高麗軍が8000人、船の操縦に関わる人間が7000人ということだったようだ。※1

また『ゴースト・オブ・ツシマ』に登場する人物は(会話中に登場するフビライ・ハーンなどを除けば)すべて架空の人物であり、ラスボスであるコトゥン・ハーンも実在しない。ただし、このときの元側の総司令官はヒンドゥという人物であり、彼についてはモンゴル側の資料にもほとんど詳細が伝わっていないため、制作陣が元ネタにした可能性はある。
文永の役で元軍が退いた理由が台風であるという話についてだが、京都の公家が書いた『勘仲記』の一文によるものであり、いささか根拠とするには乏しい。実際に台風は発生したようだが、『高麗史』には「帰国を後押しした」「絶好の大義名分」とあり、台風で全滅したと受け取るには弱い。『元史』にも「官軍整わず」「矢尽きる」とあるので、必ずしも台風がすべてというわけではなかったのかもしれない。

そもそも大陸では騎馬戦において最強を誇っていた元軍の主力部隊が、此度の海戦にどの程度参加していたのかも怪しく、加えて元や高麗からの補給線も伸びている状態では長期戦は難しい。それらの状況も加味し、ただ台風がすべてをどうにかしてくれたと取るのは無理なのではないか、というのが現代においては濃厚な説のひとつだ。
弘安の役
それから7年後、二度目の侵攻が行われる。
日本は文永の役ののち、博多湾沿岸に石塁を作り、異国からの侵略に備えた。そんな折、高麗では内輪揉めが発生したり、元では征東行省という日本攻略のための役所が作られたりしていた。

1281年、合浦と中国大陸の寧波の沖にそれぞれ部隊が配置され、日本侵攻が開始される。
今回の役においても、8月23日から翌24日にかけて、台風が起きている。これに関して『高麗史』では「大風に遭い、蛮子軍は皆溺死した」とか、『元史』では「10万人の兵のうち生還できたのは3人だけだった」という記述があるが、誤りではないかと推測されている。というのも、台風を免れて生き残った指揮官だけで何人も存在したからだ。
また、今回の役に間に合わせるために900隻の船を新造するつもりが、間に合わず、文永の役で用いた船も混ざっており、それらが主に沈没したのではないか、などといった説も提唱されている。たしかに台風によって大きな被害は出たようだが、それだけが日本の勝因だったと考えるのは今回も難しいようだ。

以上『ゴースト・オブ・ツシマ』を元にして元寇を調べてみた。『ゴースト・オブ・ツシマ』が史実よりもエンタメ性を重視して作られた作品であることは一見してわかることだが、こうして歴史を紐解く良いきっかけをくれるゲームであるのは間違いない。次回作『ゴースト・オブ・ヨウテイ』がますます楽しみになってきた。
※1 宮脇淳子著『世界史のなかの蒙古襲来』(扶桑社・2019)より
参考文献:
山田邦明監修『地図でスッと頭に入る鎌倉・室町時代』(昭文社・2022)
光と闇の対立――「FF」や「ダークソウル」の下地になった啓示宗教・ゾロアスター教を学ぶ
ゲームの下地になった作品・伝承・神話・出来事などを追いかけ、多角的な視点からゲームを掘り下げようという企画「ゲームの元ネタを巡る…