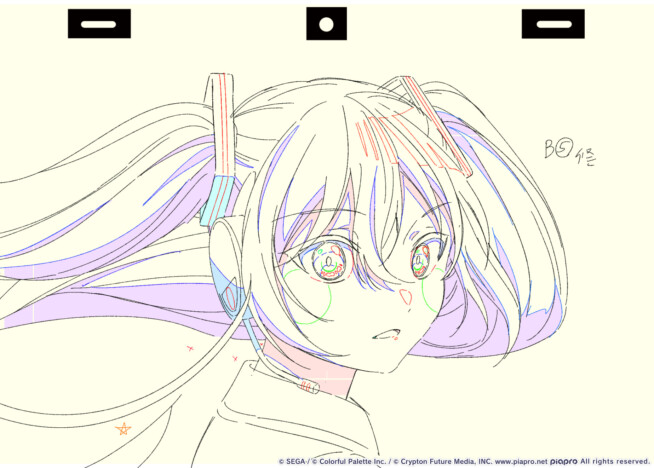2024年、なぜ「SV重音テト」曲のヒットが多発したのか サツキ×大漠波新×吉田夜世が語る“激動のボカロシーン”
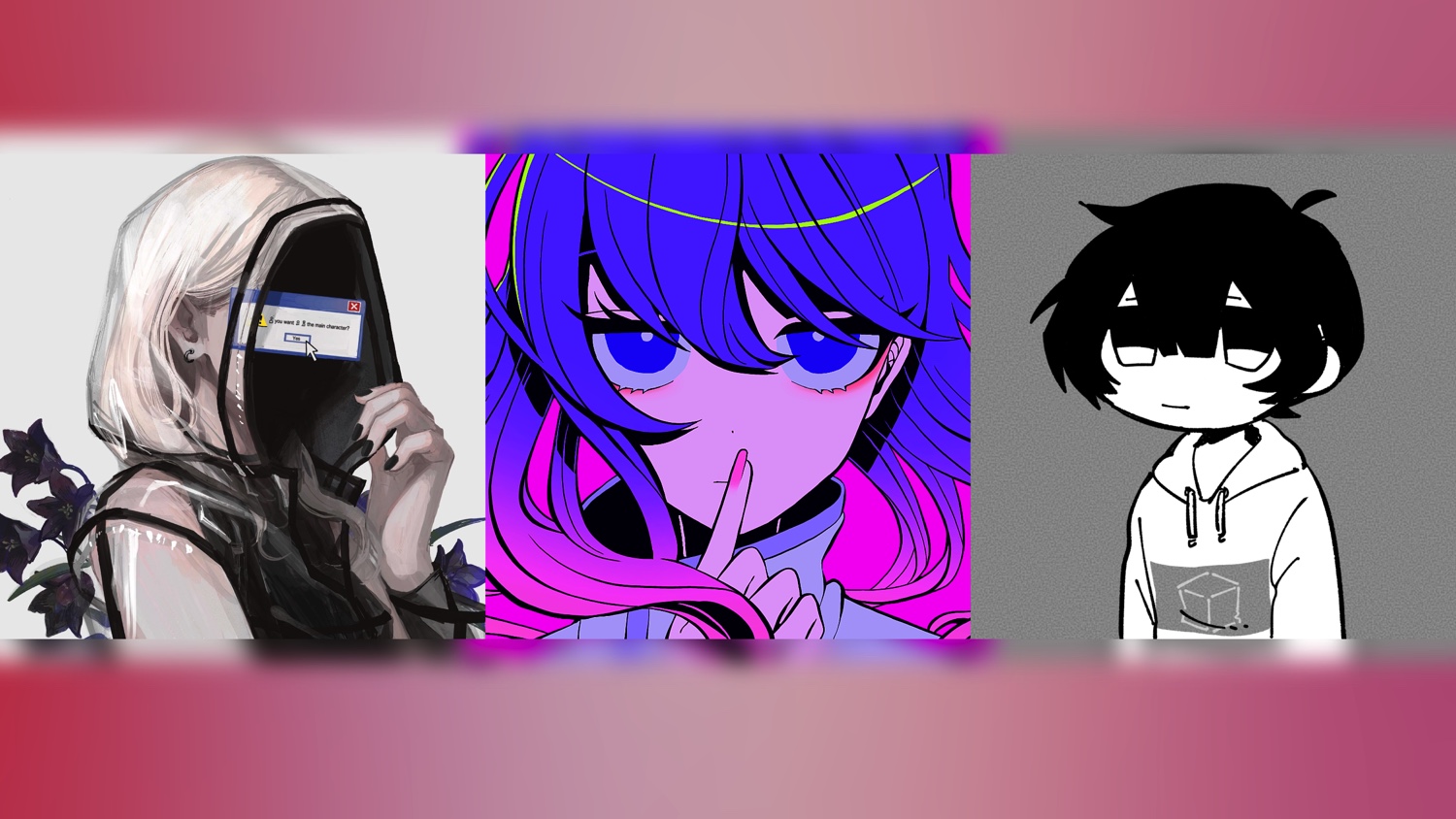
重音テトが“一過性のブーム”で終わらない可能性も見据えている(吉田)
──そんな皆さんの共通項には、SV(Synthesizer V)重音テトの存在も大きいです。ここからはそれぞれ、みなさんに「重音テト」というキャラクターの印象なども聞けたらと。
大漠波新:自分は元々、テトのことをUTAU時代から知っていました。「おちゃめ機能」なんかは、当時ボカロの枠を超えてニコニコ全体ですごく人気でしたし。SVが出た時もデモを聴いて、単純に歌声がめちゃくちゃいいなと思ったんです。これまでにもいろんな音声合成ソフトがバージョンアップしましたけど、テトほど「従来の面影を残しつつちゃんと進化している」子は珍しかったというか。ただ、「重音テト」というキャラクターって、味が濃すぎるとも思っていて。自分の曲で使うなら、ある程度テトを使う理由や「なぜテトなのか」を掘り下げないと扱うのが難しそう、とは考えていたんです。
──それはやはり、テトの特殊な出自が理由で?
大漠波新:それもありますね。なのでSV重音テトは、入りの印象こそ歌声の良さでしたけど、いざ自分の曲を歌ってもらう際は「テトが歌う意義」や「テトだからこそ」という部分をかなり重要視しました。キャラクター性をしっかり掘り下げれば、その文脈自体はいくらでも見つけられるんですが。俺はそういう個性的な子がすごく好きですけど、そういう意味ではめっちゃ個性的なソフトだと思います。
──扱いが難しい一方で、上手い使い所を見つければ強烈な魅力になる、と。
大漠波新:でもそれこそが、ボーカロイド“プロデューサー”の醍醐味ですよね。ちょうど「あいのうた」制作時が、自分も「ボカロPをやろう。」という風に決意を改めた頃だったので。そんなマインドとテトの起用タイミングが重なったのもあったと思います。
──ありがとうございます。続いて、吉田さんにもお話をうかがっていいですか。
吉田夜世:自分は、SynthesizerV版のテトが発表される前の時点ではUTAU版を使ったことがなかったんですが、昔から人気曲の数々は知っていて。重音テトの大御所である亜沙さんやはるふりさんの曲は、大漠と同じく2010年代から聴いてましたね。当初は初音ミクほかクリプトンの子たちと同じような存在だと思っていたんですが、調べたらどんどん濃い設定が出てきて「なんだこれ!?」って驚くという。でも確かに、その分他のソフトに比べてある種の強烈な印象はありました。
自分が作り手になってからも、手持ちの子を使うことに手一杯でなかなかUTAUまで手が出せなかったんですが、SV版の発売で「おっ」となって。当時、すでに同じSVの小春六花を時々使ってて、性能の良さでいずれSVは天下を取るだろうと思っていました。
個人的には、「テトが電気屋に並ぶ」こともかなり感慨深く感じたんです。当初「テトが電気屋に並ぶ」というのは、2ちゃんねる(現:5ちゃんねる)の“釣り”として書かれてた話だった。それが、とうとう本当に電気屋に並ぶ日が来たことにすごく嬉しさを感じて。なのでSV版はぜひバリバリ使いたいと思った中、じゃあ最初にどうやって使おうかと模索した末に生まれたのが「サイマル的な、」だったんです。
──あの曲は発売日当日に投稿された曲なので、ボーカルデータ以外は事前にすでに準備済だったってことですよね?
吉田夜世:そうです。曲を発売日当日に出すために、テトを電気屋で買うことはできずダウンロード版で買ったんですけど……(笑)。実はあの曲、SV版だけでなくUTAU版も作ってるんですよ。そっちはボカ学のアルバムに収録したり、配信にも出してます。楽曲は最初ボーカルをUTAUで入れて、SV購入後すぐUTAUのメロディーをなぞるように打ち込んで公開まで漕ぎ着けた形です。映像もすべて事前に準備してました。
──吉田さんはなぜ、そこまでするほどの情熱・愛情をテトに持っていたんでしょう。
吉田夜世:やっぱり、キャラクター性に惹かれた部分はかなりありますね。「サイマル的な、」はそんなキャラクター性を前面に押し出して、UTAUとSV二人の重音テトが揃った世界線上でテトが自身の歴史や未来のことを歌う、大漠の言葉を借りるなら「テトである意義」のある曲にしたかったんです。
ただ、少し時が経った今、それこそ初音ミクが出た時もそうでしたけど、当初は「ミクである理由」が強い曲が多かった中で、より普遍的な曲へ広がった歴史があるじゃないですか。テトも同じ道を辿るだろうと思っていたので、「オーバーライド」は「サイマル的な、」に比べるとより普遍的な要素の曲になっています。テトの声に合う音域で作ったり、「サイマル的な、」の文脈を辿った部分もありますけど、それはあくまで自分の中でのメタ的な視点で。いわば他のソフトが歌っても問題ない曲として作った面もありますね。
──興味深い考察でした。最後に、サツキさんはいかがですか?
サツキ:僕は2010年頃からボカロを聴き始めたんですが、当時は年1回ぐらいのペースでテトのヒット曲が出ていた印象です。はるふりさんや青谷さん、個人的にはいちたさんの曲もずっと好きで。その頃からいい意味でミクたちと変わらないソフトだと感じてた一方、出自や背景を調べると企業を介していないような、それこそインターネット全体で作り上げたムーブメントのひとつだと思ったりもしたんです。
今回のSV化も、ずっとUTAU版を愛用するボカロPさんや長年テトを愛し続けるリスナーさんの後押しがあって実現したことで。SVからテトを使い始めた後進の僕たちはまずそんな先人の皆さんや運営のツインドリルさんの皆さんに、ちゃんと感謝の気持ちや敬意を持たないといけない、と。
──15年という長い年月越しのリブートは、まさにそんな方々の愛の積み重ねが実を結んだ結果ですもんね。
サツキ:UTAUはフリーソフトで敷居が低い反面、調声やミックス、操作性の難しさに若干ハードルの高さを感じて、結局自分で使うには至らなくて。ただ以前からテト自体は好きなキャラだったし、SVの操作性の良さも知っていたので、今回のSV化で絶対使おうと思ってたんです。
しかもちょうどSV発売のニュースを知ったのが、自分の就職先の研修1日目で、4月はずっと「テトにどんな曲を歌わせたら映えるかな」とか、そんなことばっかり考えて仕事していました。月末の仕事帰りに、出たばかりの初任給を使ってちゃんと電気屋でテトを買いましたよ、僕は(笑)。
ただ当時制作中の曲はすでにボーカルが埋まってたので、実際に使ってあげられたのは購入後半年ほど経ってからで。「メズマライザー」に関しては、channel先生が以前エイプリルフールで重音テトの投稿をしたんですが、動画かと思いきや読み込みがずっと続いて永遠に始まらないというネタ動画で。「channel先生の描く、動く重音テトが見たい」と思ってボーカルに加えた経緯がありました。「オブソミート」も対「メズマライザー」という位置づけが元々あったので、そうなるとミク・テトのコンビが必然的かな、と。
──そんな中で、サツキさんは特にどこにテトの魅力を感じていますか。
サツキ: AI系のシンガーの中だとかなりパワフルな歌い方ですし、高音を張っても芯のある声をしてますよね。自分の曲は歌の音域が広かったりオケに音圧があったり、いわゆる“ボカロらしい”曲が多いので、それにもすごく馴染むので、その点をかなり気に入ってます。
──みなさんのお話を聞くと、やはりテトのキャラクター性は大きな魅力だと思っていて。ただ大漠さんも言われていたように、その存在感ゆえにまだ使い所を探っているボカロPさんもいれば、吉田さんの言葉通り、直近は徐々にキャラとして普遍化してきた面もあって。改めてお三方に伺いますが、なぜ2024年はあんなにも“重音テトイヤー”になったのだと思いますか?
大漠波新:シーン自体を遡っても、GUMIやIA、v flowerや可不など、そのときどきでトレンドの子はいつの時代もいて。要はそこにテトも組み込まれたっていう話なんですけど、一方でそれは単純に良い物に対してみんなが「良い!」ってなった結果だとも思うんです。
ただ、「じゃあ今v flowerは?」「IAは?」っていう風に思う所もあって。もちろんトレンドは常に移り変わっていくものだし、VOCALOIDの文化自体にもメインストリームとカウンターカルチャーがあるし。何なら従来のボカロ文化ってカウンター性の方が強いから、どんどん形は変わっていくと思います。
これはテトに限らずですが、その中でどんな状況だろうと「こんなにいいソフトがいるんだぜ」って自分の趣味嗜好を発信するのがボカロPの役目だと僕は思っているので、そこからまた新たな流れが生まれるはずです。なので、自分は今のテト人気とあわせて「じゃあ5年後、10年後、20年後のシーンはどうなってる?」という未来の事も含めて、長い目で考えていきたいですね。
吉田夜世:加えて言うなら、初音ミクってずっと文化のスタンダードですけど、あれも理由を分析するとキャラクター性と使いやすさの奇跡的なバランスが要因だと自分は感じていて。今までのトレンドの子たちって、そのバランスでいうとキャラクター性の方が強かったと思うんです。
ただ、今回のSV重音テトはそのバランス感がかなり初音ミクに近いというか。なので僕は、このテトブームが一過性で終わらない可能性も見据えてます。このまま初音ミクに次ぐスタンダードになってもおかしくない、と。UTAU時代から一定の人気の下地がずっと敷かれていることもありますので、僕らボカロPの頑張り次第になるかもしれませんが、テトを次のスタンダードへ導けると信じています。
──確かに昨年はテトのヒット曲が多かった反面、やはり全体曲数の多さは初音ミク一強でした。そういった点に、吉田さんの仮説がすでに表れているのかもしれません。
サツキ:さっき話したUTAUの操作性の難しさがハードルになってる人は、自分以外にも結構いるのかな、とうっすら感じてて。キャラは好きだけど、ソフトとして使うのは難しい、という潜在層がかなり多かったんじゃないかと思います。それがSV化で掘り起こされて、現在の人気に繋がったのかな、と。
重ねて近年はAI系のソフトが発達しすぎてて、最近ボカロPを始めた人にはもしかしたら、「VOCALOIDすら操作が難しい」って人もいるんじゃないかな。SVはその点ベタ打ちでも充分歌ってくれるので、初心者にもすごく優しい存在なんだと思います。聴き手の中にも機械音声の違和感ある響きが苦手な人は一定数いるし、そういう人にとってもSVの自然な発声は受け入れやすいでしょうね。
──作り手と聴き手どちらの需要にもハマった、という点は納得感がありますね。
サツキ:あと、テトって出自にネタ的要素もあるせいか、「シリアスすぎない」曲も多い気がしてて。2020年代前半って、シーン全体としてシリアスでダーク、闇・病み要素の多い曲が流行った体感なんですが、それこそさっき大漠が言ったように、そんなトレンドのカウンター性とテトの性質が合致したというか。その結果、ネタ的・ミーム的なふざけ要素が入った最近の曲の流行に傾いてる気もします。
──そのお話を受けて、今後もしかしたら「UTAUのテトを知らない」新しいボカロリスナーも出てくるかもな、とふと思いました。
サツキ:原口沙輔さんやフロクロさんを始めとして、UTAUのテトを使用している人もたくさんいますけどね。SVの方が今はやっぱり世間の認知としては上なのかな。
大漠:でもUTAUにはUTAUの良さがありますよ、やっぱり。
──ボカロ文化自体にすでに途方もない多様性がある中で、そういったテトの二面性も今後シーンをさらに深化させる要素になるかもですね。