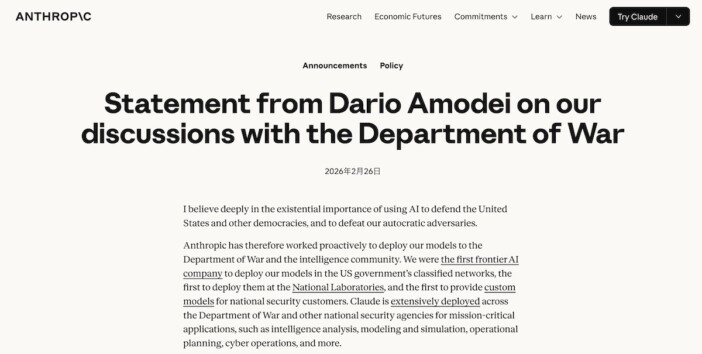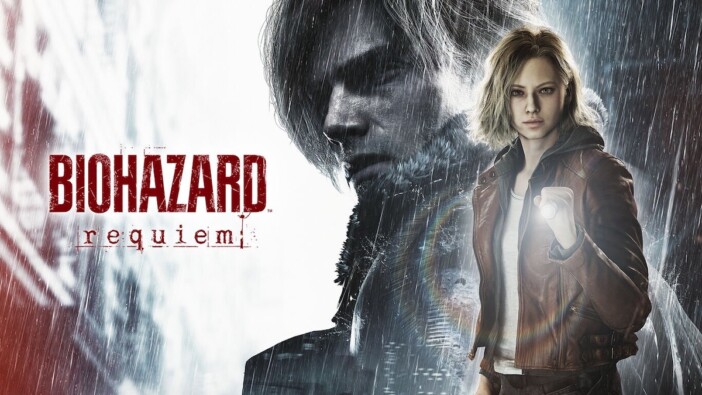任天堂がgamescom不参加か 逆風続く「ゲームの見本市」、生存戦略のカギは体験価値向上にあり

「世界三大ゲームショウ」のひとつとして知られる見本市「gamescom」の2024年開催に任天堂が参加しない方針であることを、ドイツのゲームメディア・Games Wirtschaftが伝えている。
なぜ世界三大ゲームショウにも数えられる著名な見本市に、ゲーム業界のキープレーヤーが参加しない決断をするのだろうか。明るくない話題が続く見本市の業界。存続のために求められる変化を考える。
ドイツ・ケルンで開催されるヨーロッパ最大級の見本市・gamescom
gamescomは、例年8月にドイツ・ケルンで開催されるゲームの見本市だ。日本の東京ゲームショウ(以下、TGS)、アメリカのElectronic Entertainment Expo(以下、E3)とあわせ、世界三大ゲームショウに数えられているイベントで、2009年の第1回以降、オンライン開催となった2020年、2021年を含め、毎年欠かさず開かれてきた。例年の動員人数は30万人前後にも及ぶ。この数字は三大ゲームショウのなかでも最大のものだ。2024年は8月21~25日の日程での開催を予定している。歴史の長さ、規模の大きさを考えても、ゲーム市場、ゲームカルチャーに小さくない意味を持つイベントである。
今回、gamescom 2024への任天堂の不参加を伝えたのは、現地メディアのGames Wirtschaft。報道によると、任天堂は「gamescomを重要なイベントである」と前置きしつつも、「慎重に検討した結果、(2024年開催への参加を)見送ることにした」のだという。
gamescomは任天堂と距離の近いイベントとしても知られている。同社は日本で開催されるTGSには基本的に不参加の方針を貫く一方で、gamescomには何度も出展を重ねてきた。ここには、前者の主催団体であるコンピュータエンターテインメント協会の設立経緯や、同イベントへの入場が有料であることなどが影響していると言われている。2023年には、E3への参加を見送ったのに対し、gamescomには出展を行った経緯もある。もちろん過去を振り返れば、gamescomに出展しなかったケースもあったが、現在となっては、三大ゲームショウのなかで唯一、任天堂が参加することを期待しやすい見本市がgamescomであるのだ。だからこそ、今回の報道は業界にインパクトをもたらしている。一部では、Nintendo Switch後継機のローンチ時期の延期が、任天堂の動向に影響したのではないかという憶測も囁かれているようだ。
なぜ任天堂はgamescom2024への不参加を決めたのか
三大ゲームショウをめぐっては2023年12月、四半世紀以上にわたって一角を担ってきたE3の消滅も発表されている。同イベントは2022年にオンライン/オフラインを通じて初めての完全中止となると、復活を期した2023年の開催も、主要プラットフォーマーの不参加などから中止を余儀なくされていた。当初は「将来について再評価をおこなう」と前向きなニュアンスも含めての声明を発表していたが、残念ながらその数か月後には消滅という判断へと至った形だ。
背景には、動画プラットフォームの台頭により、プラットフォーマー/メーカーがユーザーと直接の接点を持ちやすくなったことがある。オフラインイベントに逆風が吹き荒れたコロナ禍を経て、見本市の役割が彼らの発信する新作情報番組などに奪われつつある現状がある。
また、ゲーム業界では、未発表情報のリーク問題が取り沙汰される機会も多い。第三者に情報を共有しなくてはならない見本市への出展の仕組みが敬遠されている実情もあるのだろう。動画プラットフォームを通じた新作情報番組の配信であれば、社内で完結しやすいため、リークの心配が少ない。この点もまた、見本市への出展が軽視される理由となっているのではないか。
おそらくgamescom2024における任天堂の動向にも、少なからずこうした影響があるものと思われる。実際に同社は今回の不参加によって失われるユーザーの試遊機会に関し、「ドイツ国内で開催されるほかのイベントで埋め合わせる」という旨の発言を行っている。その言葉の裏には、「それ以外の見本市の価値は別の場所で補える」との考えも見え隠れする。三大ゲームショウが創設されたころに比べると、相対的にその価値が低まっているのは否定できない現実であると言える。
ゲームの見本市に求められる変化とは
これまでの四半世紀と同様に、見本市がゲーム市場、ゲームカルチャーに影響力を持っていくためには、どのような変化が必要なのだろうか。少なくとも従来のような運営では、今後も先細りとなっていくことがまず間違いない。その観点に立ったとき、重要なテーマとなるのが「コストに見合った対価を提供できるか」だ。
言わずもがなだが、見本市の運営は慈善事業ではないため、出展社や来場者がその場に参加するための費用を支払っている。つまるところ、プラットフォーマー/メーカーの不参加が増えているのは、こうしたコストを含むデメリットがメリットよりも大きいと判断されているからにほかならない。
先にも述べたとおり、見本市の持つ「情報を発信する場としての役割」は、動画プラットフォーム上で配信される情報番組に取って代わられている。この点で見本市がコストに見合った価値を提供することはまず難しいと言えるだろう。であるならば、「オフラインだからこそ実現できること」に目を向けていかなければならないのではないか。
たとえば、昨年開催されたTGS2023では、セガ/アトラスが自社のブース内に巨大なステージを構え、ピックアップタイトルに関連する大規模なショーを定期的に行っていた。開演時刻になると、ステージ前には一際大きな人だかりができ、そのただならぬ光景に当初は興味を持っていなかった人も足を止めるという現象も起きている。このような接点は、出展社/来場者の双方にとって、その場にいなければ持てないものであると言えるだろう。まして、本来はアプローチできなかったであろう層にも影響が飛び火しているのだからなおさらだ。こうした注目の広がり方は、オンラインでは実現しづらいものである。
昨今、マーケティングの領域では、体験価値に大きな視線が注がれている。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは4月19日、新エリア「ドンキーコング・カントリー」の開業延期について、「これまでにない体験価値をさらに引き出し完成度をより高めるため」とコメントした。今年3月には、東京・お台場に“完全没入体験”をうたう新たなテーマパーク「イマーシブ・フォート東京」もオープンしている。食の分野では4月3日、東京・恵比寿にサッポロビールによるヱビスブランドの体験拠点「YEBISU BREWERY TOKYO」も開業した。
これらと同様に、ゲームの見本市も体験価値の創出に目を向けていかなければならないのではないか。上述のセガ/アトラスのステージの例は、出展社の工夫によって生まれているであろうものだ。今後、「ゲームショウ」という場が継続していくためには、運営として類似する価値の提供を模索していかなければならないのかもしれない。そうした取り組みによって動員数や注目度が増せば、結果的にプラットフォーマー/メーカーも出展のメリットを得やすくなる。この点こそが、ゲームの見本市に求められる変化、ひとつの生存戦略と言えるのではないか。
コロナ禍を経て、見本市の運営は苦境に立たされている。存続のためには、体験価値へとフォーカスした抜本的な改革が必要なのかもしれない。
画像=Unsplashより
ニンテンドー3DS&Wii Uソフトのオンラインサービスが終了 今後も「すれちがい通信」は利用可能
任天堂は4月9日午前9時をもって、ニンテンドー3DSソフトおよびWii Uソフトにおけるオンラインプレイなど、インターネット通信…