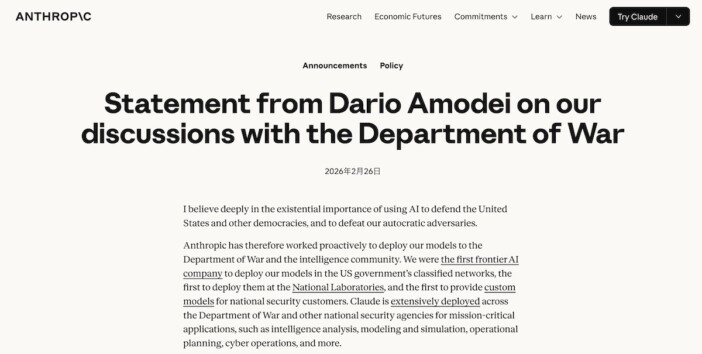日本独自のエンタメを活かすために必要なクリエイター支援の理想像 『SIW SHIBUYA 2022』セッションレポート(前編)

日本最大級のソーシャルデザインをテーマとした都市フェス「SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 2022」(以下、SIW)は、今年で5回目を迎える。今回は「アイデアと触れ合う、渋谷の 6 日間。」と題し、会期中にはさまざまなプログラムやパネルディスカッションが行われた。
去る2022年11月11日には、5GやXRなどの先端技術開発におけるコンテンツの企画・開発を手がけるクリエイティブカンパニー「stu」が、SIWを主催する渋谷未来デザインとパートナーを組んだ「SPECIAL SESSION」を開催。日本のエンタメコンテンツ制作やクリエイターの底上げに必要なことについて、各方面の有識者らによる議論がなされた。
本稿では前編と後編の2回に分けて、トークセッションのレポートをお届けしていく。
登壇者:
里村 明洋氏(アドビ株式会社 常務執行役員 兼 CMO)
ローレン・ローズ・コーカー氏(株式会社 stu COO)
長田新子氏(一般社団法人渋谷未来デザイン理事・事務局長)
柿本ケンサク氏(映像作家、演出家)モデレーター:
黒田 貴泰氏(株式会社 stu CEO)
過去2年間で世界のクリエイター人口が3億人まで増えた
セッション冒頭では「渋谷クリエーター制度」構想の立ち上げ背景について、黒田氏から説明がなされた。特にまだ具体的な中身は定まっていないものの、「各業界で活躍するクリエイターが集まるようなコミュニティスペースやエコシステムのようなものが作れないか」といった雑談レベルのものが切っ掛けとなって取り組みが始まったという。
渋谷はカルチャーの発信地として知られ、多くのクリエイターが集う場所であるが、「クリエイター支援」の具体的な取り組みについては、行政側がすぐに動き出せるわけではない。
そこで、クリエイティブカンパニーとして事業展開するstuが、いわばプラットフォームとしてstuの持つ技術やノウハウ、知見を共有し、どういう形でクリエイターをバックアップしていくか。このような考えが今回の構想の裏側にあると黒田氏は述べた。
行政、クリエイター、民間企業がどう関わり合いながら、どのようにして構想を具現化していくのかがテーマになるわけだが、里村氏は「創作活動の最前線にいるクリエイターを対象とした調査『Future of Creativity』をもとに、各国のクリエイター事情を考察していきたい」とAdobeの観点から見たクリエイター支援について話した。
同調査は世界のうち、米国、英国、スペイン、フランス、ドイツ、オーストラリア、日本、韓国、ブラジルの9カ国をピックアップし、デザイナーやフォトグラファー、イラストレーターなどオリジナルコンテンツを生み出しているクリエイターの動向について調べたものになっている。
そんななか、日本国内では「一億総クリエイター時代」と言われて久しいが、グローバルで見ても同様にクリエイターが増加しているという。
「コロナ前はおよそ1.5億人ほどのクリエイターが活躍していましたが、過去2年間で2倍となる3億人以上のクリエイターが誕生したという調査結果が出たんです。とりわけブラジルは7,300万人と飛躍的に数が伸び、お隣の韓国でも1,100 万人の新たなクリエイターが生まれているような状況です」
ブラジルやスペインのようなラテン系の国では、ポジティブマインドを持っている人が多く、「自分自身を『クリエイティブ』である」と自負している割合が他国と比較しても抜きん出ているそうだ。さらに、コロナ禍でデジタル化が進んだことで、ポジティブマインドを持った人の表現する場や活躍できる場が増えたのが、クリエイター増加の要因になっている。
他方、韓国や日本はクリエイター自身の前向きな認識が低く、SNSでプレゼンスを高めるための投稿や共有する機会もラテン系の国と比べて少ないとのこと。
ではなぜ、韓国では新規のクリエイターが多く誕生したのだろうか。それは「クリエイティブをビジネスと結びつけ、事業の発展やセルフブランディングに活用していきたいと思う人が多く、それが背景にある」と里村氏は説明する。
「韓国はクリエイティブに対する感度が高く、ビジネスとの親和性を意識している一方、日本はクリエイターやインフルエンサーのそもそもの時給が他国と比べて低いのが現状と言えます。ビジネスとしてクリエイティブ活動に取り組む人の数が少ないのもそうですが、今のままではビジネスとしても成り立ちにくい。このような課題をどう解決していくかが、日本のクリエイターを取り巻く環境整備および支援を考える上で肝になってくると考えています」
韓国は国を挙げてクリエイターの支援を行っており、日本でもクリエイターの底上げをしていくためには、行政や国も巻き込みながらアクションを起こしていくことが求められてくるだろう。柿本氏は世界と日本でクリエイターとして活躍してきた経験から、次のように意見を述べた。
「私はコロナ前までは世界を中心にクリエイティブ活動を行っていました。年間の半分くらいは海外で撮影したり仕事したりすることが多かったんです。海外志向を持って活動していた矢先、コロナ禍になってしまったのを機に180度方向転換し、今は日本にフォーカスして活動しているような状況です。世界での経験を生かし、日本のクリエイティブにどう還元していくか考えることがすごく面白くて、映像編集室を渋谷に構えたんです」
しかし、当時は日本と海外とでは広告やMVの作り方が大きく異なり、温度差を感じたこともあったという。
「海外の場合はディレクターに制作プロダクションが付いている一方、日本の場合はクリエイティブエージェンシーが、制作会社と一緒に企画を作って、クライアントに通し、そのあとに企画をやってくれる監督を選ぶ流れになっています。これは海外と全く逆のことをやっているわけで、僕ら監督としての立場で見ると『受け手の仕事』になってしまい、自ら挙手して『あのクライアントと仕事したい』と言えないような縦割り社会になっていると思っていました。映像編集室やマネジメントの会社を作ったその当時は、業界から異端の目で見られたというか、圧力を感じた部分もありましたね」