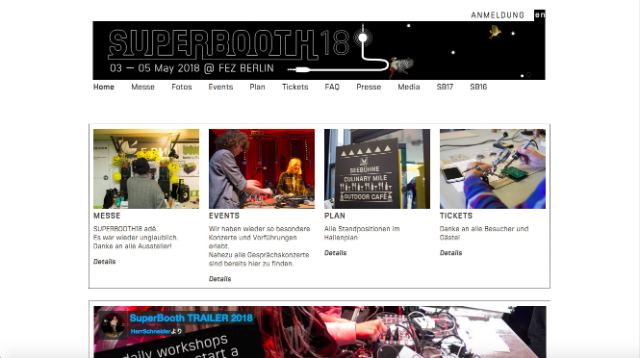連載:音楽機材とテクノロジー(第一回)横山克
横山克が語る、機材で『テクスチャーを作る』ことの重要性 日本のレコーディングスタジオへの提言も

テクノロジーの進化とともに機材の数や種類が増えている現在、音楽制作者の人口もDAWの普及によってさらに増加の一途を辿っている。今回よりスタートする連載「音楽機材とテクノロジー」では、音楽家の経歴やターニングポイントなどを使用機材や制作した楽曲とともに振り返る。
第一回では、ももいろクローバーZやイヤホンズへの楽曲提供者でもあり、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』、『わろてんか』、『ちはやふる』、『クローズアップ現代』、『リバース』、『Fate/Apocrypha』、『天狼-Sirius the Jaeger-』など数々の作品で劇伴を担当する横山克にインタビュー。機材を使ううえで心がけていることや、トラディショナルと最先端の共存、ライブラリを作る制作手法が生まれた経緯、さらには日本のレコーディングスタジオが抱える問題点についての言及もあった。(編集部)
「レコーディングよりも前の段階に着目」
ーー前回の取材( https://realsound.jp/2017/04/post-11910.html )では、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』の劇伴を中心に、横山さんの楽曲制作について伺いました。その後も『わろてんか』『ちはやふる』『クローズアップ現代』『リバース』『Fate/Apocrypha』と大活躍ですし、今期の『天狼-Sirius the Jaeger-』もすごく面白い試みをしてらっしゃるという印象を受けました。
横山:ベルリンテクノですね(笑)。
――そうです(笑)。前回のインタビューでは「『ガンダム』を機に、劇伴における仕掛けの重要性に気付いた」という話してもらいましたが、そのなかでも面白かったのは“ライブラリを自分で作る”というお話で。あれ以降、いろんな作品でオリジナルのライブラリを作る、という方法論を取ってきたのでしょうか?
横山:そうですね。ただ、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』はそれだけじゃなくて、僕の音楽作家人生においても、たくさんの新たな刺激があったんです。初めて海外でオーケストラを録ったのもこの作品でした。ドイツを始め、ブダペスト、ニューヨーク、そしてもちろん東京。リモートレコーディングも含めて、沢山の場所でレコーディングをしました。

ーー確か、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』劇伴の録音では、New York Gypsy All StarsのIsmail Lumanovskiをはじめとした、個性的なプレイヤーと出会ったんですよね。
横山:オーケストラはもちろん素晴らしい編成です。ですが、得られるサウンドは当然「オーケストラ」であり、その良し悪しこそありますが、耳にとって斬新であるかといわれると、「オーケストラ」ではあります。ですので、その作品に合った独自の編成を探す面白さを求めました。『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』で言えばバルカンブラスを探す旅がありましたが、その後の作品でもこの経験は活かされています。
例えば、『Fate/Apocrypha』はルーマニアが舞台ということもあり、ルーマニアやハンガリーの楽器でもあるツィンバロンやジプシーバイオリンを使っています。そこでも良い出会いがあって、ハンガリー人の素敵なツィンバロン奏者の方と知り合えたんです。最初、ブッキングしたものの、その方が楽譜をどのくらい読めるのか、全く情報がなかったんです。でも、そこで出会えたMiklós Lukácsは、元々ジャズピアニストでもあり、楽譜を読めるどころか、コードやスケールを理解した上でインプロビゼーションまでできるという『Fate/Apocrypha』の印象的な支えを作ってもらいました。あまりに印象的な出会いでしたので、その方を主役にした音楽を作りたいという思いを持ち、その後に作った『わろてんか』ではかなりの頻度でツィンバロンを使いました。
ーー横山さんにとって、ツィンバロンという楽器が果たす役割はどんなものだと思いますか?
横山:ハンガリーにおいて、ツィンバロンという楽器は、ハンガリーにおけるフォークソングのような楽曲で用いられることの多いものなんです。つまり、日常に近い音として使われているということですね。街やカフェでは沢山演奏している場面に出会えます。『わろてんか』は日常を描く物語なので、そういった意味でも合うと思いました。音楽のスタイルとしては、主人公である藤岡てんの生きた時代は、スコット・ジョップリンの「ジ・エンターテイナー」、つまりラグタイム(シンコペーションを多用する右手のメロディと、マーチで進行する左手の伴奏を主体とした音楽ジャンル)がめちゃくちゃ流行っていたタイミングだったんです。なので、ツィンバロンでラグタイムな音楽を、あの作品では一番最初に書きました。
ーーそのお話だけでも『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』~『Fate/Apocrypha』~『わろてんか』が接続されましたね。面白い。
横山:そして、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』~『Fate/Apocrypha』の間にもう一つ、面白い作品もありました。『22年目の告白』という映画の劇伴は、ほぼノイズだけで作り上げたんです。
ーー『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』直後くらいのタイミングでしたね。先のお話と違い、楽器というよりはノイズというジャンルに焦点を当てた劇伴でした。
横山:楽器をフィーチャーするのではなく、何かしらのサウンドをジェネレートする、という方向に特化した作品ですね。メロディは一音もありませんでした(笑)。『Max』という、今は『Ableton Live』と一体化もしましたが、プログラミングで音を作るソフトを主に使っています。もちろん僕は『Max』を技術的に完璧に使いこなせるわけではありませんが、元々使っていた時期もあり、再度勉強しなおして作りました。テレビ局が制作するような商業映画の世界で、大きな映画館で思いっきり実験音楽をやってみたかったんです。日本中で沢山の人がノイズミュージックを聴いてくださった事実に興奮しました。ほとんど個人的な理由ですね(笑)。
ーーそれらの作品は、横山さんが『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』以降に取り掛かってきたやり方の応用編だといえますよね。その期間を経て、新たに気づいたことはありますか?
横山:海外のミュージシャンやプロデューサーとも一緒に仕事をする中で、日本の作家って色んなものをミックスするのが得意なんだ、と気付きました。たとえば、デトロイトテクノの要素を劇伴に入れようとしたとき、市販のサンプル(ライブラリ)を買うことが多いんですが、日本人はそのサンプルの取り入れ方がどの国の音楽家よりも上手いなと思うことがあります。レゲエのサンプルを使ってレゲエそのものを作るのではなく、レゲエの要素を含んだ何かの音楽を作る。もちろん当たり前に行われていることですが、複雑なことをしっかり組み合わせて形にする、そのやり方がうまいと思うんです。
――なるほど。『天狼-Sirius the Jaeger-』においても、そのような手法を使ったんですか?
横山:いえ、話は『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』劇伴のレコーディング時まで遡るんですが、当時、ベルリンから1時間くらいで行くことのできるフランクフルトオーダーで録音をしていたんです。僕はテクノが大好きなので、ベルリンにはベルグハインという最高のクラブがあるということも知っていたんですが、その時に行くことができなくて。時間や体力的な問題があったのですが、それにしても悔しくって。いつか行きたいなとずっと思い続けていた…という事が一つ。もう一つは、自分が多くの曲を書いているなかで、鍵盤から作ることに危機感…つまり、もっと自分の作曲を広げたいと思っているタイミングが来ていて、『MASCHINE』(NATIVE INSTRUMENTS社製)を使って曲を作っていた時期があったことも大きいです。そんななかで『天狼-Sirius the Jaeger-』のお話をいただいて、「暗く、映画的な世界観の劇伴が欲しい」と言われたので、「ベルリンテクノというジャンルがありまして……」と提案させていただきました。

――自分の中でずっと温めていたものを出したと(笑)。
横山:はい(笑)。このタイミングで話したのには、他にも理由はあるんです。『KONTAKT』のライブラリは、ハンス・ジマーをはじめ色んな人が作っているんですが、「『MASCHINE』のライブラリを作っている音楽家っているのだろうか?」と思ったんです。NATIVE INSTRUMENTS社(以下、NI)はベルリンが本社ですし、アーティストが社員に多いという事は知っていました。また、日本法人が数年前にできたこともあり、相談に行ってみたら「NIでサウンドデザイナーをやっていたJulian Laping(Polly Powder)という人がいる」と紹介されて、楽曲を聴いたらまさに自分の作りたい音に近くて。彼が『MASCHINE』のエクスパンションパック(CAVERN FLOOR)を作っていたということもあり、これはオファーするしかない、と即座に連絡先を教えてもらって、2017年のクリスマスにドイツへ行くことになりました。
ーーその時点で、Julianとの共同作業が『天狼-Sirius the Jaeger-』の大きなテーマになっていたわけですか。
横山:これまでは「いかにレコーディングを面白くするか」というところに着目していたんですが、今回は、作曲よりも前の「一緒に音素材を作る」という、レコーディングよりも前の段階を他のクリエイターとやることで、新たな刺激になればいいなという思いもありました。
ーー横山さん自身、これまで劇伴の共作曲はなかったわけですよね。
横山:作家2人で作品の音楽を担当したことはありますが、共同作曲という事はありません。歌ものでも、作曲した曲はほとんど自分で編曲までしています。今回も、例えばアレンジャーとしてベルリンテクノが得意な人を入れることもできたと思うんですけど、日本の劇伴独特の「展開」や「スタイル」を理解してもらう事は難しい部分もあります。なにせ、ベルリンテクノは踊りながら10分かけてハイハットがひとつ増えて狂喜乱舞するようなジャンルですから(笑)。大好きなんですけどね、流石にそいういうことを劇伴でやるわけにはいきません。ストレスなくコラボレーションするためにも、作曲の前の、音を作るところをやりたいと思っていました。さらに……彼はベルグハインのアーティストでもあったという!
ーーそんな伏線回収が!
横山:ベルグハインってバウンサーがいて、地元のドイツ人ですら「お前、今日は入っちゃダメだ」と弾かれたりするんですよ。でも、Julianのおかげて簡単に入ることもできました(笑)。
――(笑)。紆余曲折あってのベルリンとなりましたが、Julianとはどんな風に作品のイメージや、横山さんが考えていたことを共有したんですか?
横山:目的としては、とにかく一緒に作るということがしたかったんです。ハリウッドでは、コンポーザーが「テクスチャーを作る」ことにすごく注力しているんですよ。例えば、ヨハン・ヨハンソンは『メッセージ』の劇伴でテープに多重に人の声を重ねるのを、繰り返して…これって、2回や3回どころの話ではないんですよ。そうやって個性的なサウンドを作って、作品全体のトーンを作ったり。
僕の目的としていたコンポジションも、素材を作ることでオリジナルの質感を出すという「テクスチャーを作る」行為に近かったので、そこを目指した、といえばわかりやすいかもしれません。ディレクター、プロデューサーや視聴者にとって、レコーディングでどれだけこだわっても、それが新しいかどうかは伝わりにくい部分があることは残念ながら事実です。パッと聴いてわかる何かを作りたい、という思いもありました。
ーーコンポジションの更に前の部分を共同作業することで、新しいコンポーズのやり方が生まれた、というのは面白いです。
横山:それをベルリンテクノというフォーマットで実現したのが『天狼-Sirius the Jaeger-』でした。最近は同じやり方を別の方法でやろうとしていて。ちょうど今、アシスタントさんに特殊な楽器を片っ端からサンプリングしてもらっているんです。たとえば「プリペアド・ピアノ(コインや消しゴムを挟んでノイズの混ざったピアノ)とか。『KONTAKT』にあるような、きれいなライブラリを作るのではなく、ひたすらにフレーズのサンプリングです。『ガンダム』のときにトライして、『天狼-Sirius the Jaeger-』で手応えを掴んだ「ライブラリを作る」ということを、さらに自分たち向けにカスタマイズして、強化しようかと。今は一万音色くらいのフレーズをオリジナルのライブラリとして、使うことができています。