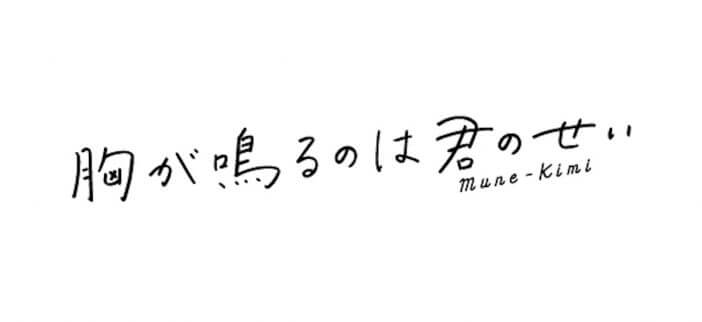“キラキラ映画”をアップデート 『モエカレはオレンジ色』に詰まった映画的ダイナミズム

“キラキラ映画”はどのようにマンネリ化から脱却し、“少女漫画”という歴史ある文化に不可欠な筋道を保ちながらアップデートを図っていくべきか。2010年代のピーク期を過ぎて著しい低迷期に突入し、恋愛要素はかろうじて「難病もの」に、高校生の青春要素は「ラノベ・Web小説原作」に、日本映画のトレンドとしては「テレビドラマの劇場版化」に取って代わられるようになった2020年代。ジャンル存続をかけた試行錯誤にもそろそろ答えが出されなくてはならない頃合いだ。
昨年の初夏に公開された『胸が鳴るのは君のせい』の際に筆者は、相手への恋愛感情を一寸たりともブレさせないヒロインの描写と、すでに「告白」からの「恋愛成就」がビッグイベントでなくなった現代における最もふさわしい着地点の設置。そして従来の少女漫画で多く見られた「恋愛を通して成長」する役割を、ヒロインである女性から相手役である男性にも背負わせることなどを挙げた。(※1)ちょうどその直後に公開された『ハニーレモンソーダ』にもその傾向は確かに見受けられたわけだが、そうしたあからさまな試行錯誤が、かつてこのジャンルに存在したプログラムピクチャー的な奔放さという魅力を幾分か削いでしまっていたことは否定できない。
結果的にこうした少女漫画を原作とした純正の“キラキラ映画”は、2021年の夏から2022年初夏にかけてほぼ1年もの間公開されることなく、もはや完全に消滅する一歩手前にまでたどり着いてしまった。あらゆる面において「時代の流れ」と言ってしまえばそれまでなのだが、これは長い目でみれば損失ともなりかねない。以前から言ってきたように、取り立ててサプライズもない決まりきった枠組みのなかで設定とキャストを微妙に入れ替えて量産させるシンプルさは、監督や脚本家といったスタッフはもちろん若手俳優の技量を測る上でも必要不可欠なものだ。

「同じような」作品ばかりというのは多様な時代の鑑賞者からすればどうしたって辟易とする材料だ。とはいえ時代劇といい『男はつらいよ』といい、「同じような」ものが生みだすある種の安心感こそが日本映画の礎となってきた。そこにプラスアルファを足し算していく、あるいは時代遅れの要素を引き算していく。完全にジャンル全体を淘汰するよりもその方が選択肢は増えることは間違いなく、相対的な傑作が時間の経過とともに絶対的な名作へと昇華する様は少なからず繰り返されてきたのである。
さて、こうした“キラキラ映画”約1年の休眠期間を経て公開されたのが、講談社『デザート』に連載中の玉島ノンの少女漫画を原作とした『モエカレはオレンジ色』だ。先に言っておけば、ここには確実に“キラキラ映画”というジャンルの試行錯誤の結果と進化の過程が刻みつけられている。驚異的に感情の揺らぎがないヒロインに、いつの間にか成就している恋愛。恋愛が単なる“きっかけ”に過ぎない成長譚と、作劇的にもコンプライアンス的にも正しいかたちの着地点。既存の王道を踏襲しながら、足りていなかったものを見事に注ぎ込む。これは2022年における“キラキラ映画”の模範解答ではないだろうか。
生見愛瑠演じるヒロインの萌衣は、父親を亡くしたショックで塞ぎ込むようになり、新しい高校へと転校するもひとりぼっちで過ごしていた。そんなある時、学校の消防訓練で消防士の蛯原(岩本照)と出会う。彼の信念に触れて心が動き、近所のスーパーで偶然再会したことで急接近。蛯原の言葉に突き動かされて友人を作ることにも成功した萌衣は、その喜びを報告しようと消防署に向かう途中で放火現場を目撃。放火犯に捕まり燃える建物の中に閉じ込められてしまう。そして助けにやってきた蛯原に、一気に恋焦がれるようになるのである。