若手とベテラン双方の活躍光る豊作の年 2021年を振り返るアニメ評論家座談会【前編】

「2021年は作家の時代」

藤津:2021年は作家の時代だと言ってもいいくらい、いろんな作家の個性の作品が出揃ったと思います。例えば『映画大好きポンポさん』の平尾隆之監督はスタイルが明確ですし、『サイダーのように言葉が湧き上がる』のイシグロキョウヘイ監督も今回すごく明確なルックを持ってきたし、作家的な振る舞いだと思いますね。
杉本:『アイの歌声を聴かせて』の吉浦康裕監督も前から活躍はされていましたが、改めていい作品を作りました。個人的に僕はとりわけ『ポンポさん』が楽しかったですね。映画制作が題材の映画って実写映画にも数多くありますが、主に取り上げられるのって撮影現場じゃないですか。あるいはプリプロダクション(撮影前の準備)。映画の制作工程の3段階のうちポストプロダクションってなかなかフィクションの物語でとりあげられることが少なかったですが、『ポンポさん』はそのポストプロダクション=編集を真正面から描いているのは本当に面白かったですね。実写の監督から見ると、編集作業って地味だから絵にならないと思ってしまうのかも。そこはアニメの監督さんだからこそ掘り下げられたのかな。僕は昔、映画学校に通っていたんですけど、編集作業はすごく刺激的でしたからその時の感覚をすごく思い出しましたね。
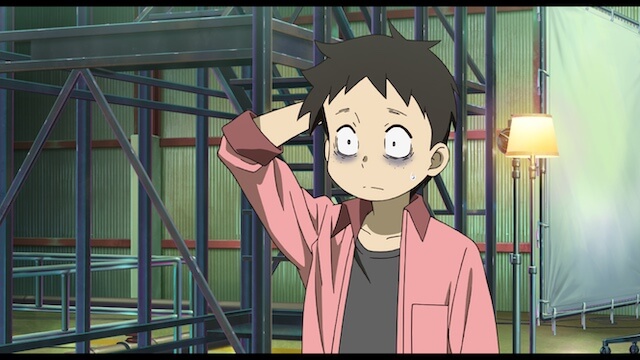
藤津:補助線を引くなら実写映画『バクマン。』の漫画を描くシーンにも近い見せ方ですよね。実は原作は編集のくだりがあまりないんですよ。アニメで平尾監督が足したところなんですよね。だから、平尾監督の主張が明確に込められている。しかも編集しながらこれを自分の作品にしていくにはどうしたらいいのかという葛藤がクライマックスになっていていいですよね。編集によってどういう効果が生じるかをチュートリアル的に見せるシーンもあったり。
藤津:ちなみに『明るい映画、暗い映画』で、写真家の大山顕さんの言葉で、新海誠監督が『君の名は。』でタイムラプスを使っているという話が書かれていましたが、その前年に平尾監督がテレビアニメ『GOD EATER』でタイムラプスをやっているんですよ。なので平尾監督は面白い絵をアニメに取り込むことにアンテナを張っている人なんだと思いますね。

渡邉:僕が観た中では、名前が出ているイシグロキョウヘイ監督の『サイダーのように言葉が湧き上がる』がすごく面白くて。一目見てわかるような鮮やかな特徴的な絵柄が印象的でした。これまで「アニメ定点観測」で杉本さんとお話ししたと思うのですが、仮に2010年代が新海誠と京都アニメーションに代表されるようなフォトリアルな実写感だとすれば、2021年はそのアニメらしさが変わってきているんじゃないかと。イシグロさんは川瀬巴水の新版画を意識しているんでしたっけ? 版画的というか、すごくグラフィカルな画ですよね。
藤津:川瀬巴水、吉田博、鈴木英人さんなどをレファレンスに挙げていますね。

渡邉:これは、藤津さんが近著の『アニメと輪郭』で書かれている「アニメにとってリアルとは」というテーマにも関わってくると思うんですが、結局アニメって絵だし記号だから、そこで大々的なファンタジーをやってもリアルじゃなくなってしまう。だから、2010年代はある意味でアニメが実写にすごく近づいていた。それが新海監督なら『天気の子』、京都アニメーションなら『リズと青い鳥』以降で、そのスタンスが絵柄とともに変わっているように思えたんです。その流れが今年極端に表れていたのが、イシグロ監督の新版画的、わたせせいぞうさんのイラスト的とも言える画なんじゃないかと。一方であの作品は俳句も大好きですよね。土居伸彰さんが著書『個人的なハーモニー』の中で触れていたことなんですが、ロシアのユーリ・ノルシュテインという世界的なアニメ作家が、アニメーションは実写映画より、むしろ演劇・俳句に似ていると言っていました。演劇も舞台、俳句も「5・7・5」という形式=記号で出来ていて、アニメも類似するところがあると。僕は『サイダーのように言葉が湧き上がる』はアニメという表現が持っている形式の本質を突き詰めたことで、新海誠、京都アニメーション的なフォトリアルな表現から変わっていく転換期を示しているんじゃないかと思います。この変化は2021年、いろんなところで見られたんじゃないかなという気はしています。

藤津:おっしゃる通りで、これまで、アニメ業界のクオリティ感の証明として、画面の中に情報量の多さ、それを活かした「綺麗さ」みたいなのがあったと思います。でも、綺麗は綺麗でも、いろいろな「綺麗さ」の形があると。それを今模索している段階なのかもしれません。先ほどの『閃光のハサウェイ』はその意味ではどちらかというと情報量の多さで写実的表現を目指したものではありますが、一方で『サイダーのように言葉が湧き上がる』や『Sonny Boy -サニーボーイ-』は、絵であることへの意識が明確です。『Sonny Boy -サニーボーイ-』は背景も筆で描いてあることがわかるぐらいタッチが残っているし、登場人物も引きになると背景と同じタッチで描かれたりしているという独自の絵柄になっている。みんながそういうふうに作品独自の絵柄を探していることは間違いないと思います。
杉本:アニメはあくまで絵であって、リアルだけを目指すわけでなく、いろいろな表現があっていいはずですし。
藤津:本当は新海監督も「写真のように」ではなく、「写真のように見せている」綺麗な絵というところがミソなんですけれどね。同じ場所に行って、いくら凝って写真で撮ってもこういうふうにはならないという独自の絵を描いているんですが、そのツイストは一般の観客にはなかなか伝わりづらい。ただ「情報量を少なくしたらどうなるだろう」というのは、たぶん作家のみなさんは考えているんじゃないかなと思います。
杉本:本当にいろんな作家さんが多かったんだなと思いますが、一方で、これまでアニメ業界を支えてきた作家さんたちも2021年はたくさん活躍していました。やはり、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が100億円を超える結果になったということについては触れないといけません。
藤津:堂々たる完結でしたね。僕は、1番最初の『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』を観たときも、テレビシリーズで振っていた謎や散りばめられた伏線を、漏らさず回収していると思ったんですが、今回はそれ以上の意気込みを感じました。
杉本:おっしゃる通りだと思います。もともと『エヴァンゲリオン』は第1話で少年と父の対立を提示していたけれど、『Air/まごころを、君に』はそれに決着をつけずに終わっていた。今回の劇場版はそこに明確にケリをつける物語だったというのがよかったと思います。
藤津:父子の関係に決着をつけるためにはなにが必要かということを再検証して、ゲンドウがどういう人物だったらいいのかもう1度やり直したという感じはすごくしました。かつてない長台詞をゲンドウがしゃべるという(笑)。
杉本:後半はゲンドウが主役にすら感じましたよね。
渡邉:『シン・エヴァ』に関しては僕も『エヴァンゲリオン』世代なので思うところはいろいろありました。僕や杉本さんの世代の中では映画はアンチ派も割と多かったような気がするんですが、僕は非常にいい着地点だったなと。やっぱり旧エヴァと新エヴァの間に『シン・ゴジラ』を作っていたというのがすごく大きかったと思います。「旧劇」以来のシンジくんとゲンドウの関係やトラウマ的な旧エヴァから続いてきた主題というのを、庵野秀明監督にとっても、旧エヴァ時代から観てきた僕たちにとっても納得できる形で完結させましたね。何度も触れられている象徴的なシーンですが、ラストでは庵野監督の故郷の山口県宇部市の実写風景の中にアニメのキャラクターたちがいるという。あの感覚はなんなんでしょう。
藤津:実写とアニメの境界線を揺らがすような感じですよね。
渡邉:私たち3人の問題意識にも繋がってくると思うんですが、アニメと実写のレイヤーを衝突させるのでもなく、離れさせるのでもなく、うまく共存させているというのが非常に2010年代的だと感じました。庵野監督も大変だったと思うんです。90年代から続いてきた功績を締めくくりつつ、一方で今にも対応させなきゃいけない新たな作品を手がけるというすごい綱渡りをやりましたよね。今年は『進撃の巨人』も完結しましたし、大作が完結するという年もありました。
藤津:実写との境界線という点で、作り方もキャラクターの配置を実際のカメラで決めたり、あるいはセットを作ってカメラアングルを決めたりしていて。『ポンポさん』の話の延長線上じゃないですが、絵コンテ的な映像の流れをフィックスするまでのトライアル・アンド・エラーを、模型やCG、プリビズなどを使って試行錯誤した上でアニメを作る作業に入るという。つまり、編集をアニメを作る作業の前に行っている。実写的な作り方は誰もができる方法ではないですが、アニメが持っている「最初に絵コンテで設計をしなければいけない」というルールを突破したという意味でも面白い作品でしたよね。
杉本:その経験は実写映画『シン・ゴジラ』のときのプリビズ制作からきているんですよね。僕はあのラストカットが本当に好きなんです。庵野監督がこれまでやってきたことがあのワンカットにすごく詰め込まれていると思いました。アニメでリアリズムを追求する一方で、実写映画を作るときは逆にフィクショナルな方向に振るという。ご本人も実写のときは生々しさを削ってしまうという話をされていますが、アニメと実写の間に何があるのかというのをずっと考えられていた方なんですよね。だからその考えの1つの具体的なイメージがあのラストシーンに結実したように思えます。だから、『シン・エヴァ』で「庵野監督ってこういう作家」という答えが明確に出た気がしますし、これからの庵野監督の作品は本当に楽しみです。『シン・ウルトラマン』と『シン・仮面ライダー』の2本の特撮を今用意していますが、やはり感性の故郷はそこにあるんだなと。改めて特撮というのが何をやってきたのか、どんなリアリティを追求してきたのか、改めて模索していく段階なんだと思います。特撮は、一般的な実写映画とも、アニメとも違うリアリティを作ってきたはずなんですよね。その3つ目のリアリティライン自体を、うまい具合に作品に生かしていくと1つ面白いものになると『シン・エヴァ』を観て改めて感じました。
渡邉:2021年は国立新美術館で大規模な回顧展が開かれたり、「庵野イヤー」みたいになったわけですけど、今後も『シン・ウルトラマン』『シン・仮面ライダー』と続いていて、私の今度の本でも庵野監督はかなり重要なプレイヤーと位置づけていて。今後、庵野監督はこれから映画史においても黒澤明に並ぶ重要なポジションに行くんじゃないかと私は思っています。これまではかなり映画史の中でブレがあったじゃないですか。
藤津:20年くらい前からCGが出てきて、CGを用いて実写のようにアニメが作れないかと押井守監督がいち早くいろんなアプローチをしてきたんですが、若干早くてPCの性能が追いついていなかったのと、押井監督の関心がエンタメ性にないということもあって、それが一般の人に分かるように示されたかと言うと、なかなかそうではなかった。ただ、『シンエヴァ』は実写のようにアニメを作り、できたものはアニメの快感もちゃんとあるといううまい落着点になっていて。ここ20年の業界全体の功績をまとめて、時代をうまく1ページ進めた感じがありますね。




















