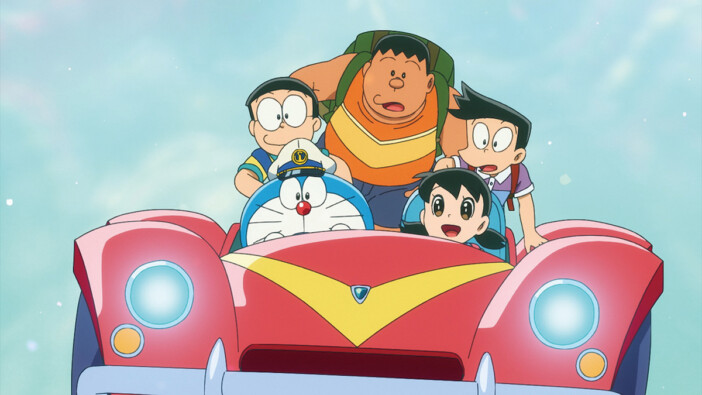豊田利晃監督の本当の意味での“復帰作”に 『泣き虫しょったんの奇跡』で再び放たれた輝き


豊田監督から失われた輝きとは
そもそも、豊田作品から本来の圧倒感が失われていた本当の原因とは何だったのか。こういう場合、「感性の衰え」などと安易に表現する向きもあるだろうが、ここで影響を及ぼしたのは作家性の後退というよりも、むしろ監督の内面的な成長だったのではないだろうか。
かつて豊田監督が撮ってきたのは、『青い春』に代表されるように、出口のない絶望に満ちた世界であり、そこで生まれる、破滅へと向かう登場人物たちが放つ一瞬の輝きだった。その光の源泉とは、損得勘定で動く大人の世界の入り口に立った、まだ純粋な子どもの感性を宿す若者による、どうにもならない現実社会へ、ささやかな反抗を試みようとする魂である。豊田監督は、その若者と感性を同化させることで力を最大限に発揮し得たといえる。
しかし破滅へと向かった後も、そこで命が絶たれない限り人生は続いていく。脚本と演出両方の仕事を行う豊田監督は、遅かれ早かれ、これまで描いてきた“絶望の先”の世界を描くという、作家として不可避の課題に挑戦せざるを得なかったように思える。
閻魔大王のはからいによって現世に復活したという小栗判官の説話に、作家・魯迅の奇妙な短編『剣を鍛える話(鋳剣)』の描写を組み合わせた、『蘇りの血』(2009年)だったり、また、雪深い山荘で暮らしながら爆弾を製造するテロリストの孤独な精神世界に宮沢賢治の詩が引用される『モンスターズクラブ』(2012年)がそうであるように、豊田監督は続くこれらの作品で、いままでより深く高度な領域に足を踏み入れることを望んだのだと思われる。
だが同時に、表現したいものが複雑になればなるほど、ここで追い求めようとする知的な“大人の世界”と、以前からの持ち味であった社会への反抗心は衝突を起こし、これまでの単純で直線的な作品に存在したドライブ感は失われ、主人公に監督がうまく同化できなくなっているように感じられた。
現実の厳しさを痛感する「将棋残酷物語」

本作『泣き虫しょったんの奇跡』の脚本は、大きく分けて3幕に分けられる。すなわち、「〈1〉将棋との出会いを描く学生編」、「〈2〉プロ試験に挫折する養成期間編」、「〈3〉再びプロを目指す社会人編」という流れだ。子役たちと松田龍平によって演じられる主人公「しょったん」が、〈1〉によって将来を嘱望された将棋の才能の持ち主であることが示されながら、〈2〉によって日本将棋連盟のプロ棋士養成機関である「奨励会」に入会した後、年齢制限が設けられているプロ昇段試験において足踏みを繰り返し、まさに文字通りズブズブと泥沼に入っていくような恐怖が、おそろしいリアリティで描かれていくのである。
将棋のプロといえば、明晰な頭脳を使って、将棋の勝負を繰り返すことで生計を立てるという、まさに全国将棋ファンの夢を具現化した存在だ。だからこそ、プロになれるかなれないか、当落線上に置かれたプロ予備軍の戦いである「三段リーグ戦」は熾烈を極める。

このリーグを戦う者たちは、上位に食い込むために連勝しなければならない。妻夫木聡が演じる、年齢制限によって脱落していく青年は、三段リーグの残酷さを嘆く。必勝を期すためには、勝ちを確信してもなおトドメを刺すリスクを避け、対戦者を苦しめ続ける戦い方が強いられてゆくのだという。真剣を持った侍の斬り合いに例えるなら、手傷を負わせ有利に立った側が、踏み込んで勝負を決することなく、卑怯にも遠くから細かな攻撃を繰り返すことによって、じわじわと相手をなぶり殺していく、血だらけの凄惨な戦い方ということになるだろう。
そんな非情さを要求される環境に置かれた者たちが集う、窮屈なリーグ戦会場は、静かながら殺伐とした雰囲気に満ちている。だが劇中で描かれる背景を知れば、それも無理はないと分かる。プロになれれば雲上人、なれずに年齢制限で落とされれば、つぶしの利かないただの趣味人として社会に放り出されることになる。その落差が、挫折する者の悲壮さを倍化させる。そして、崖っぷちに立たされ自殺すら考える者も出てくるのである。その意味で、ここでの年齢制限は、プロ棋士を目指す若者にとって、まさに「死刑宣告」を意味するのだ。