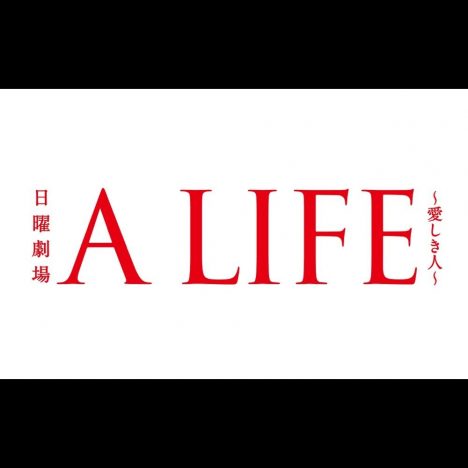ティム・バートンの作風に変化アリ? 『ミス・ペレグリン』に自ら登場した背景

我々はよく「ティム・バートン的」という言葉を用いて、そのダークな世界観と、職人的な絵作り、ブラックユーモア、“人とは違う”主人公の痛みや悲しみについて集約しようとする。確かにバートン映画には、彼自身が少年時代に感じた疎外感や孤独といったものが顕著に現れているのはファンならずとも多くが知るところだ。
「子供の時に感じた自分は人とは違うんだという気持ちは決してなくならないもの。それは一生付いて回る。私は“変わっている”というレッテルを貼られた。なぜなら子供なのに、モンスター映画が大好きだったせいだ。人は子供の頃、時にはもう少し後になってから、そういう経験をするものだ。同じように感じている人はたくさんいる」
最新作においてもその方向性は変わらない。そこには多くの“人とは違う”こどもたちや、主人公がたどる“自分らしさを見つける旅路”が映し出される。まさにバートン印。だが、実際に映画に触れてみると実に興味深い感触を覚えた。「ティム・バートンは徐々に変わってきているのではないか?」という思いが頭をよぎったのである。
もちろん、近年になってジョニー・デップやヘレナ・ボナム=カーターとのコラボレーションが影を潜めていることも大きいが、それ以上に、一つの個性や作家性を傑出させるのではなく、むしろ様々な才能を結集させて、チームプレーでゴールを目指そうとする印象が強くなってきているように感じられたのだ(ちなみに今回は作曲家ダニー・エルフマンの音楽もなし)。
その姿がこれまでのトレードマークとなっていた衣を次々と脱ぎ去り、新たな可能性を模索しているようにも感じられ、そのせいだろうか、私は本作を見ながら「ああ、確かにティム・バートン作品だな」と思いながらも同時に心底「新鮮で、たのしい!」と感じてしまった。そこには陽光がきらめき、様々な可能性が胸に差し込んでくるような明るさがある。決して内向きではなく、窓を開け放って外に飛び出すような開放感がある。
個々の才能が絶妙なチームプレーを生み出した娯楽作

それは一人の青年の冒険の物語。最愛の祖父(テレンス・スタンプ)が謎の死を遂げ、孫のジェイク(エイサ・バターフィールド)はその時に黒い巨大な影を目撃する。あれは一体何だったのか。大人たちに相談すると精神科医の診療を受けさせられ、よっぽど祖父の死がショックだったんですね、ということになる。
生前の祖父は語っていた。ある島に暮らす子どもたちのこと。大きな屋敷の中にたくさんの“奇妙な”こどもたちが暮らしており、ミス・ペレグリンが面倒を見ているという。そして他でもない祖父もまた、そこで幼少期を過ごしたのだとか……。「是非そこに行ってみたい」そう主張するジェイクに精神科医も「精神的にも良い効果が得られるかも」と了承し、保護者同伴で旅立つことを勧める。そうやって辿り着いたのは、イギリスはウェールズ地方にあるケルン島。島を探索する中でいつしか異世界への入り口を見つけた彼は、その驚くべき世界へと足を踏み入れーー。
「最愛の人が聞かせてくれた物語」。それが嘘か誠かという面では『ビッグ・フィッシュ』を想起する人も多いだろう。あの作品も非常にカラフルで、登場キャラたちは非常にユニーク。そのテーマ性も「物語のほとばしるところ、創造性の原点」に寄り添い、非常に前向きな気持ちにさせてくれる優しさがあった。
本作は、前半に「きっとおじいちゃんの作り話」「おじいちゃんは認知症だったし」という前提を挟み込む。が、そこを抜けると真実or妄想という境界線には主眼をおかず、『アリス・イン・ワンダーランド』のように思い切り異世界へと飛び込み、その世界で『ダーク・シャドウ』のようにそれぞれが奇妙な個性や能力を持った者たちと出会うといった格好だ。
脚本を手がけたジェーン・ゴールドマンは、マシュー・ヴォーン監督の執筆パートナーとしても知られる。『X-MEN:ファースト・ジェネレーション』や『キック・アス』、『キングスマン』などヒット作が目白押しだが、彼女の練り上げる言葉はキャラの肉付けがうまく、個々の卓越した能力を一つひとつ際立たせる力を持つ。交わされるセリフも粋でストンと胸に飛び込んでくるストレートさも併せ持っている。
そんな彼女が紡ぐキャラの中でもミス・ペレグリン役のエヴァ・グリーンは格別だ。ティム・バートンは「怖いメリー・ポピンズ」と形容しているそうだが、彼女がこどもたちを守ろうとする時の鋼鉄の意志やその表情は、まるで死を恐れぬ戦士のよう。他にもクリス・オダウド、ルパート・エヴェレット、ジュディ・デンチといった名優が顔を揃える同時に、祖父役のテレンス・スタンプの、狂気か正気かわからぬ役柄も実に素敵だ。そうそう、忘れてはいけない、サミュエル・L・ジャクソンは、相変わらずのサミュエル・L・ジャクソンぶり。それ以下でも、それ以上でもない。
さらに『アリス・イン・ワンダーランド』のようなCG満載の世界観に振り切れることなく、今回はベルギーのアントワープ近郊に実在する城を使用し、コーンウォールやブラックプールでロケを行うなど実景を取り入れた空間作りが美しく、その下地がしっかりしているので要所要所のVFX効果が鮮やかに際立つという好循環が生まれている。