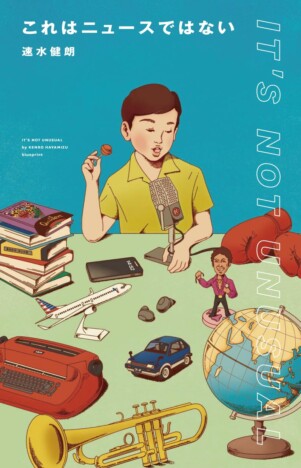森直人の『レヴェナント:蘇えりし者』評:イニャリトゥ監督による、ハリウッド大作への真っ向勝負

お話はシンプルな復讐劇だ。仕掛けも簡素。しかし熱量はメガトン級で、ボリュームたっぷりの映画体験を提供してくれる。19世紀の雪に覆われたアメリカ西部を舞台に、実在のハンターがモデルとなった主人公ヒュー・グラス(レオナルド・ディカプリオ)が残虐な隊員仲間(トム・ハーディ)への復讐を決意。極寒の未開地で、怒りと執念に憑かれた男の魂が煮えたぎり、作品全体から凶暴で凄まじいエネルギーが放射される。
監督はアレハンドロ・G・イニャリトゥ。メキシコ出身の彼はデビュー作の『アモーレス・ペロス』(00年)から『21グラム』(03年)『バベル』(06年)『BIUTIFUL』(10年)までは、市井の人々の皮肉な運命を見据えた重厚なヒューマンドラマのスタイルを取っていた。
しかしアカデミー賞作品賞・監督賞などに輝いた第5作『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』(14年)で作風を一変させる。SF映画『ゼロ・グラビティ』(13年/監督:アルフォンソ・キュアロン)で見事な宇宙空間を創出した撮影監督、エマニュエル・ルベツキ(やはりメキシコ出身)とタッグを組み、ブロードウェイの舞台裏を臨場感あふれるリアルタイム進行で、シュールな幻想性を交えながら手品か魔法のような全編ワンカットで見せた。要は「語り」から「体感」への転換を図ったのである。

なぜ「体感」に旋回したのかは『バードマン』が自己言及的に語っている。あの作品の核心的な主題は「小さな映画」の危機感だ。映画業界のメインストリームから弾かれた落ち目の中年俳優(マイケル・キートン)の狂気じみた姿を通し、アメコミ原作のヒーロー物など、安易な商業主義に傾きがちなハリウッドの大作傾向を風刺した。一方でミニマムなドラマ=「語り」が、インターネットのコンパクトな視聴に移行している現状への焦りも随所に垣間見える。
その認識を踏まえて大きくジャンプしたのが、今回の『レヴェナント:蘇えりし者』だろう。本作もロケーションが主体という点では本質的に「小さな映画」だ。しかしカナダやアルゼンチンの危険な高地に繰り出し、神秘的な原野が広がる中で肉弾戦のスペクタクルを展開。野蛮かつ崇高な大自然に包まれて刺激的な「体感」を実現した。つまり『バードマン』がカウンター的視座からの批評だとすると、『レヴェナント』はハリウッド大作への真っ向勝負だと言える。

ルベツキは軽量なデジタルカメラの機動力を驚異的な技術で駆使し、知恵と本能で必死に生き抜こうとする主人公を躍動的に捉える。人工的な照明を使わず、自然光のみで撮影された映像はクリアで美しい。この「自然光のみで撮影」というスタイルは『ニュー・ワールド』(05年)以降、ルベツキが継続的に組んでいるテレンス・マリック監督の流儀でもある。イニャリトゥは貪欲にもマリックの手法を移植・吸収し、そのスピリチュアルな詩的世界を大切にしつつも、自らはアート・シネマ然とした形ではなく豪快なアクションへと振り切っている。