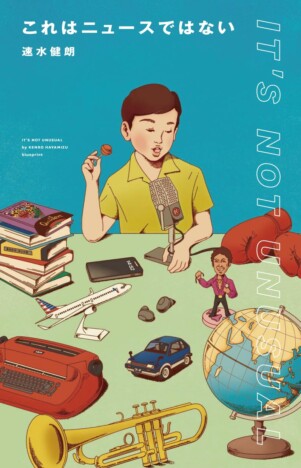森直人の『レヴェナント:蘇えりし者』評:イニャリトゥ監督による、ハリウッド大作への真っ向勝負

結果、『レヴェナント』で強烈に印象づけられるのは人間の原初的な活力だ。筆者が連想したのは、ドキュメンタリー映画の父とも呼ばれるロバート・フラハティ(1884~1951)の世界。特にカナダのイヌイット族の暮らしを記録した『極北の怪異(極北のナヌーク)』(22年)には近いものを感じる。

実は「記録」と言いつつ、フラハティは生活の素描に演出を加え、今で言う「やらせ」を持ち込んでいたことはよく知られている。これは映画というものが、もともとドキュメンタリーとフィクションの境界線上を漂う「詐術」であることがよく判るエピソードだ。イニャリトゥは『レヴェナント』でこの「詐術」を確信犯的に利用しており、その端的な可視化がドキュメンタリー・タッチの画面に上塗りされたCGである。ディカプリオを襲う巨大な熊だったり、マジック・リアリズム風の風景描写だったり……。これらのトリッキーな映像処理もすべてフラハティ的な映画術の21世紀仕様――デジタル時代のアップデートだと筆者には思える。
ポスト・プロダクションの仕事で言うと、誰の耳にも圧巻なのが坂本龍一のスコアだ。ミニマル・ミュージックのシンフォニー的展開とでも言うのか、凝りに凝りまくった多層的なサウンドスケープ。これは明らかに『バードマン』で、アントニオ・サンチェスの非常に快楽的で吸引力のある凄腕のドラミングを、そのまま映画のリズムに同期させてしまった成果の延長である。『レヴェナント』は3D作品ではないが、この「立体的な音響空間」はその「体感」に代わるものだ。

ここで『バードマン』が提起した「小さな映画」の危機感というテーマに戻ろう。その問いを裏返すと、現在浮上しているのは「新しい劇場対応型の表現とは何か?」という模索である。その課題にまず応えたのが『アバター』(09年/監督:ジェームズ・キャメロン)が嚆矢となったデジタル3Dであり、これがリーマン・ショック以降のハリウッド業界のカンフル剤になった。3Dは「映画ならざるもの」だとする意見もあるが、単純明快な「見世物」の復権という意味では、むしろ映画の本来性――100年以上前の黎明期の志向にもう一度戻っているとも考えられる。
実際、筆者がいま「新しい映画」だと思えるものは、すべて「初期映画」の貌を備えたものだ。前衛的とも呼べる手法でプリミティヴなパワーを発揮した『レヴェナント』がロバート・フラハティだとすると、『ゼロ・グラビティ』はジョルジュ・メリエスの『月世界旅行』(1902年)につながっている。ここにもう一本並べるとすれば、やはり『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(15年/監督:ジョージ・ミラー)になるだろう(奇しくも『レヴェナント』とはトム・ハーディの出演が共通している)。あの大傑作がジョン・フォードの『駅馬車』(39年)を彷彿させることはたくさんの識者に指摘されたが、もちろんそのルーツにはリュミエール兄弟やエジソンの発明がある。そう、おそらく我々はいま21世紀の技術で更新された「二回目の映画史」に立ち会っているのだ。
■森直人(もり・なおと)
映画評論家、ライター。1971年和歌山生まれ。著書に『シネマ・ガレージ~廃墟のなかの子供たち~』(フィルムアート社)、編著に『21世紀/シネマX』『日本発 映画ゼロ世代』(フィルムアート社)『ゼロ年代+の映画』(河出書房新社)ほか。「朝日新聞」「キネマ旬報」「TV Bros.」「週刊文春」「メンズノンノ」「映画秘宝」などで定期的に執筆中。
■公開情報
『レヴェナント:蘇えりし者』
公開中
監督:アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ
脚本:マーク・L・スミス アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ
撮影:エマニュエル・ルベツキ, ASC/AMC
オリジナル・ミュージック:坂本龍一、アルヴァ・ノト
出演:レオナルド・ディカプリオ、トム・ハーディ、ドーナル・グリーソン、ウィル・ポールター、フォレスト・グッドラック
(c)2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.
公式サイト:http://www.foxmovies-jp.com/revenant/